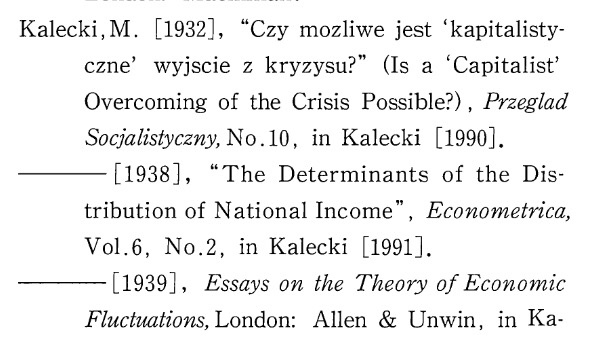グルントリッセ1857~8...(+資本論草稿関連)
http://nam-students.blogspot.com/2016/07/blog-post.html
http://nam-students.blogspot.jp/2015/11/blog-post_3.html
『マゾッホとサド』ドゥルーズ
http://nam-students.blogspot.jp/2015/11/blog-post_88.html
NAMs出版プロジェクト: ドゥルーズ体系:メモ
http://nam-students.blogspot.jp/2015/10/blog-post_72.html
NAMs出版プロジェクト: 独占、寡占、完全競争(サミュエルソン経済学)
http://nam-students.blogspot.jp/2015/02/blog-post_17.html
独占資本関連:
《もし生産コストが下がらないなら、資本主義は現存の設備を維持し、これと併行して他の領域に投資するほかはない(86)。
…
(86)Paul Baran et Paul Sweezy, Le Capitalisme monopoliste , 1966, tr. fr. Maspero, pp. 96-98.〔ポール・バラン、ポール・スィージー『独占資本』小原敬士訳、岩波書店、1967、112-118ページ〕》116~118頁
スウィージーは1:15:9(英語版章分け★)資本論を参照している。
《アンドレ・ゴルツが「科学的技術的労働者」を描いた二重のポートレートは、まったく意味深いものだ。彼は、知識、情報、教育の流れの先生であるが、しかしあまりにもみごとに資本の中に吸収されているので、公理系に組み入れられ組織化された愚昧の逆流に完全に巻き込まれることになる。このため、この労働者は、晩になって自分の家に帰ってから、テレビをいじりながらやっと自分の小さい欲望機械を取りもどすというわけなのだ。ああ、何という絶望(89)。確かに学者は、あるがままでは何ら革命的な力をもってはいない。彼は、統合作用に統合される最初の手先であり…
(89) A. Gorz, Stratégie ouvrière et néo-capitalisme , Ed. du Seuil, p. 57.〔アンドレ・ゴルツ『労働者戦略と新資本主義』小林正明訳、合同出版、1970、118ページ〕》
《Alors que la croissance du secteur des serviees a partiellement compensé l effets « destructeurs d'emploi de lIa teclmologie mo de e, celle-ci I(en conjonction avec des phénomènes induits) a ajouté une dimension nouvelle à la deshumanisation du processus de travail en régime capitaliste. Il n'est guère besoin de répéter ici ce qui a été tellement souligné dans les ch'apitres précédents, à savoir qu'une partie de plus en plus grande du produit de la société de capitalisme monopoliste est, - d'après des critères fondés sur les véritables besoins humains, - inutile, super ue ou bien franchement destructrice. L'illustration la plus frappante de eeci se trouve dans le
fait que des dizaines de milliards de dollars de biens et services sont engloutis tous les ans par l'appareil militaire, dont le seul but est d'empêcher les peuples du monde de résoudre leurs problèmes par l'unique moyen véritablement effieace, par le socialisme révolution naire. Cependant, ceux qui actionnent et qui approvisionnent l'ap pareil militaire ne sont pas les seuls à être engagés dans une entreprise anti·humaine. Les millions d'ouvriers qui produisent (ce qui créent une demande pour) des biens et services inutiles sont également. et à
des degrés divers, concernés. Les divers secteurs et branches de l'éco. nomie sont tellement interdépendants que presque tout le monde se trouve impliqué d'une façon ou d'une autre dans une activité anti· humaine ; le fermier fournissant des produits alimentaires aux trou· pes luttant contre le peuple vietnamien, les fabricants des instruments complexes nécessair à la création d'un nouveau modèle automobile, les fabricants de papier, d'encre ou de postes de télévision dont les produits sont utilisés pour contrôler et empoisonner les prits des gens, et ainsi de suite. 仏訳303~4
《このようなシステムにおいては、生産システム全体に生気を吹き込む反生産の活動との結びつきを誰ものがれることはできない。「軍事的装備を稼働させ補給する人びとだけが、反人間的な企てにかかわっているわけではない。何百万もの労働者が無用の財や仕事を生産し(このことがまたこれらに対する需要を創りだす)、さまざまな度合で、このことにかかわっている。経済の異なる諸分野や諸部門は深く相互依存しあっているので、ほとんど全世界の人びとが何らかの仕方で反人間的な活動の中に巻き込まれている。ヴェトナム人民と戦争する軍隊に食糧品を供給する農夫。新しい自動車の型を創造するのに必要な、複雑な道具を作る製造者たち。人びとの精神を統制し腐敗させるために用いられる製品となる紙、インク、テレビの製造者たち。以下同様(90)。」こうして、たえず拡大する資本主義的再生産の三つの線分が完結し、これはまた、それの内在性の三つの様相を規定する。1、労働の脱コード化した流れと生産の脱コード化した流れとの微分の比の関係から、人間による剰余価値を引きだし、また中心から周縁へと移動しながらも、やはり中心に膨大な残滓的地帯を保持しているという様相。2、中心の「最尖端」の個所において、科学的技術的コードのもろもろの流れの公理系から、機械による剰余価値を引きだしてくるという様相。3、流れの剰余価値のこれら二つの形態の創出を保証し、生産装置の中にたえず反生産を注入することによって、これらの二形態を吸収し、あるいは現実化してゆく様相。ひとは周辺において分裂症化するが、しかし中心や中間においてもやはり分裂症化するのである。
剰余価値の定義は、可変資本資本に由来する〈人間による剰余価値〉とは区別される〈機械による剰余価値〉との関連において、また流れの剰余価値全体の測定不可能な性格をも考慮に入れて、手直しされなければならない。剰余価値は、労働力の価値と労働力によって創造される価値との差異によって定義されうるものではない。そうではなくて、これら二つの流れがたがいに内在し合っているにもかかわらず、この二つの間に通約不可能性があることによって定義される。一方の流れは真の経済の力を測り、他方の流れは「収入」として規定される購買力を測るものであるからである。第一は莫大な脱領土化した流れであり、この流れは資本の充実身体を構成するものである。ベルナール・シュミットのような経済学者は、無限負債のこの流れを特徴づけるために、〈瞬時の創造的流れ〉といった抒情的な奇妙なことばを見いだしている。銀行は自発的に自分自身への負債としてこのような流れを創造する。銀行のこの創造は無からの創造であって、これは支払い手段としてあらかじめ準備された貨幣を流布させるのではなく、負の貨幣(銀行の債務として登記された負債)を充実身体の一方の極に深く埋めこみ、正の貨幣(生産経済が銀行に対してもつ債権)を他方の極に突出させる。これは「突然変異の力をもつ流れ」であるが、この流れは収入の中には入らず、購買には向けられない。つまり純粋な待機であって、所有物でもなく、富でもない(91)。これに対して、貨幣のもうひとつの様相は、貨幣が次のように還流する事態を表わしている。すなわち、貨幣が労働者たちや生産諸因子に分配され収入として配分されて購買力を獲得することになると、たちまち貨幣はもろもろの財と関係をもつことになり、この収入が現実の財に変換されると直ちに、この貨幣は財との関係を喪失するのである(この場合、すべては新しい生産によって再開されるが、新しい生産はまず貨幣の第一の様相において生まれてくる……)。ところで、流れと還流というこの二つの様相の通約不可能性は次のことを示している。名目賃金は国民の収入の全体を包括するものであるが、賃金労働者は、企業によって捕獲された大量の収入を漏出させるのである。今度はこの収入が連接によって合流し、新たに粗利益の連続的流れを形成し、この合流は「ひとつの流れとして」、たとえその割り当てはもろもろに異なるにしろ(利息、配当金、管理職給与、生産財購入、等々)、充実身体の上を流れるひとつの不可分な量を構成することになる(92)。事情に通じていない観察者は、この経済的図式そのもの、この歴史そのものが深く分裂的であるという印象をもつ。こうした理論の目的は自明である。しかし、この理論は、あらゆる道徳的関心をみずからに禁じているのだ。〈誰が盗まれるのか〉という疑問…
…
(90) Paul Baran et Paul Sweezy, Le Capitalisme monopoliste , p. 303.〔『独占資本』〕邦訳416~7頁、#11:2
http://digamo.free.fr/barans68.pdf フランス語訳全336p
(91) Bernard Schmitt, Monnaie, salaires et profits , P. U. F., 1966, pp. 234-236.
(92) ib. p. 292.》
独占資本:
___
ジル・ドゥルーズ「思い出すこと」(聞き手:ディディエ・エリボン、鈴木秀亘訳、『批評空間』誌第II期第9号、太田出版)、p.11-12
〈マルクス〉
私は共産党に入ったことは一度もありません。(精神分析を受けたことも一度もありません。そういったことはすべて免れました。)60年代以前は、自分をマルクス主義者だと思ったこともありません。共産党員にならなかったのは、党が党員の知識人に何をさせていたかを見て知っていたからです。
当時私がマルクス主義者でなかったわけは、つきつめればマルクスを知らなかったからだということもことわっておかなければなりません。
マルクスを読んだのはニーチェと同じ時期でした。素晴らしいと思いました。彼の生み出したさまざまなコンセプトは、私にとって今でも役立つものです。そこにはひとつの批判、根本的な批判が存在しています。『アンチ・オイディプス』と『千のプラトー』はマルクスに、マルクス主義に完全に貫かれた作品です。現在私は、自分を完全にマルクス主義者だと考えています。例えば、「管理社会」について書いた記事は(月刊ロートル・ジュールナル1号 1990年5月号に掲載、ミニュイ社刊『記号と事件』に収録、邦訳河出書房新社)、マルクスが彼の時代には知りえなかったことを語っているにもかかわらず、完璧にマルクス主義的なテクストです。
マルクスは間違っていたなどという主張を耳にする時、私には人が何を言いたいのか理解できません。マルクスは終ったなどと聞く時はなおさらです。現在急を要する仕事は、世界市場とは何なのか、その変化は何なのかを分析することです。そのためにはマルクスにもう一度立ち返らなければなりません。
〈著作〉
次の著作は『マルクスの偉大さ』というタイトルになるでしょう。それが最後の本です。
〈絵を描くこと〉
私は今もう文章を書きたくありません。マルクスに関する本を終えたら、筆を置くつもりでいます。そうして後は、絵を描くでしょう。
http://nam-students.blogspot.jp/2013/04/blog-post_2074.html
________________
http://yokato41.blogspot.jp/2013/12/blog-post_2.html
《サディスム=マゾヒスムが同一者であるという言葉を聞かされすぎてきた。ついにそれを信ずるまでに至ってしまった。すべてを始めからやりなおさねばならない》
医学には、徴候群と徴候の区別がある。すなわち徴候とは、一つの疾患の特徴的な符牒であるが、徴候群とは、遭遇または交叉からなる幾つかの単位であり、大 そう異質な因果系統や可変的なコンテキストとの関係を明らかにする。サド=マゾヒスム的なる実体は、それじたいで一つの徴候群で、他には還元しがたい二系 統に解離すべきものとは確信をもって主張しがたい。(『マゾッホとサド』)
サド=マゾヒスムは、(……)誤って捏造された名前の一つである。記号論的怪物なのだ。みかけは両者に共通するかにみえる記号と遭遇したとき、その度ごとに問題となっていたのは、還元不能の徴候へと解離しうる一つの徴候群だったのである。要約しておこう。
①サディスムと思弁的=論証的能力、マゾヒスムの弁証法的=想像的能力。
②サディスムの否定性と否定、マゾヒスムの否認と宙吊り的未決定性。
③量的な繰り返しと、質的な宙吊り。
④サディストに固有のマゾヒスム、サディストに固有のサディスム、そして両者は決して結合しない。
⑤サディスムにおける母親の否定と父親の膨張、マゾヒスムにおける母親の「否認」と父親の廃棄。
⑥二つの場合における物神的な役割と意味の対立関係、幻影についても同様の対立関係。
⑦サディスムの反審美主義、マゾヒスムの審美主義。
⑧一方の「制度的」な意味、他方の契約的な意味。
⑨サディスムにおける超自我と同一視、マゾヒスムにおける自我と理想化。
⑩性的素質の排除と再強化の対立的二形態。
⑪全篇を要約するかたちで、サド的意気阻喪とマゾッホ的冷淡さとの根源的命題。
以上の十一の命題は、サドとマゾッホの方法の文学的な違いにおとらず、サディスムとマゾヒスムの幾多の違いをも明白に表明すべきものであろう。(『マゾッホとサド』p163)
期待と宙吊りという体験は、根本的にマゾヒズムに属するものだ。(……)マゾヒズムに特有の形態とは期待なのだ。マゾヒストとは、待つことを純粋状態にお いて生きるものである。それ自身が二つの分身となり、同時的な二つの推移へと変ずることは、純粋なる期待の属性である。そしてその二つの推移の一方は、待 たれている対象を表現し、それは、本質的な引き伸ばしであり、つねに遅刻状態にあって延期される。いま一方のものは、予期している何ものかを表現し、それ のみが待たれている対象の到来を性急に繰りあげうるかも知れないものだ。かかる形態、二様の流れからなる時間的リズムが、まさにある種の快楽=苦痛という 組み合わせによって充たされているという事実は、一つの必然的な帰結なのである。苦痛は、予期しているものの役割を演じ、それと同時に、快楽は待たれてい る対象の役割を演じることになるのだ。マゾヒストは、快楽を、根本的に遅延する何ものかとして待ち、最終的に快楽の到来を(肉体的にして精神的に)可能に する条件として、苦痛を予期しているのである。したがって、それじたいとして待つことの対象たる苦痛が、自分を可能ならしめるのにいつも必要としている快 楽を、マゾヒストは未来へと押しやっているのだ。マゾヒストの苦悩は、ここでは、不断に快楽を待ちはするが、その方法として苛烈なまでに苦痛を予期してか かるという、二重の限定作用をとることになるのだ。(ドゥルーズ『マゾッホとサド』蓮實重彦訳 91~92頁)
◆『批評空間』1996Ⅱー9共同討議「ドゥルーズと哲学」(財津理/蓮實重彦/前田英樹/浅田彰/柄谷行人)
柄谷行人)ぼくはドゥルーズがいった概念の創造ということに関して大きな誤解があると思う。概念の創造というのは新しい語をつくることだと思っている人が多い。その意味でいうと、『千のプラトー』はものすごく新しい概念に満ち満ちているように見えるけれど……。
ぼくはそんなものは感嘆に形式化できると言っている。だからそこに新しさを見てはいけない。概念を創造するというのは、あたりまえの言葉の意味を変えるこ となんですよ。しかし、そうやって意味を変えるときに、必ずドゥルーズならドゥルーズという名前がついてくるんです。たとえば、マルクスが「存在が意識を 決定する」と言ったときの「存在」は、マルクスによって創造された概念なんで、その一行は「事件」なんです。ぼくはそれが概念の創造だと思う。
浅田彰)だから、たとえばデカルトの「コギト」(われ思う)というのが概念の創造なんですね。
蓮實重彦)まさにそのとおりだと思うけれども、ちょっと違う角度から言うと、たとえば『マゾッホ』、あれはサディズムの概念をおもしろく定義したからいいのではないし、マゾヒズムの概念をおもしろく定義したからいいのではなくて、ふたつを分けたことが概念の創造なんです。
浅田)「マゾヒズム」はサディズムと関係ないというのが概念の創造なんですね。
(……)
音楽でいうと概念というのはライトモチーフなんですよ。だから、一回聴いたらそれがだれのものかわかるんですね、どういう変奏のもとに出てきたとしても。
蓮實)そこで、まさに概念は署名と不可分だということになる。それで、ドゥルーズという署名の問題が出てくるんだけれども、彼がガタリと創造した概念を、あたかもそれがCMでいうコンセプトであるかのようにして流通させている人は、まさに固有名を背後に感じていながらもこれを切断しているという、悪しき流通形態に陥ってしまう。それに対してドゥルーズは非常に厳しく批判していますね。
浅田)たとえば「スキゾ」という概念が80年代の日本で結果的にCMのコンセプトのようなものとして流通したことは事実だし、その責任の一端は感じますけど……。
蓮實)ありますよ、それは(笑)。…
浅田)しかし、本当は、「スキゾフレニー」(分裂症)という言葉だってそれまでにいろんな人たちによっていろんな形で使われてきたわけで、ドゥルーズとガ タリは新しい言葉を作るのではなくそういう既成の言葉を新しい形で使うことで概念を創造したんです。その点では、ガタリはまだ新しい言葉を生み出している として、ドゥルーズはほとんどそういう言葉を生み出していないとあえて言いたいぐらいなんですね。
蓮實)であるがゆえにすごいんだということでしょ。
浅田)そうです。つまり、ドゥルーズはやはり何よりも哲学史家だと思う。音楽の比喩で言うと、作曲家ではなくて演奏家なんです。ドゥルーズとガタリはグー ルドが好きだったけれど、グールドが弾くとバッハもベートーヴェンもグールドになってしまう、しかしそれはやはりバッハやベートーヴェンなんです。ガタリ との関係で言えば、ドゥルーズはほとんどガタリというピアノを弾いているんですね。
柄谷)カント論もニーチェ論もみなそうで、演奏なんですね。
浅田)演奏ってインタープリテーション(=解釈)ですから。
柄谷)ただし、解釈学とは違う解釈ですね。(……)
蓮實)……ドゥルーズは、共通の美的感性の持ち主のグループというのを想定しないと言いつつ、『シネマ』に関してはしているんですね。明らかに、ある種の 『カイエ・デュ・シネマ』的なシネフィリー(映画好き)というものの上に立っている。つまり、与えられた題材をもとにその分類と体験の質を分割しているだ けであの中で、あっと驚く映画はひとつも出てこない。もしそうなら、それは大した哲学者じゃないと言うべきじゃないの(笑)。
浅田)いや、哲学者はそれでいいんでしょう(笑)。
蓮實)ただし、それにもかかわらず、(……)概念化へと向かう言葉がまったく描写することがないのに、映画のひとつひとつのシーンが目に見えるようでしょ う。これはすごい才能だと思う。その才能に立ちあえば、それが、哲学であろうとなかろうといいと思う。概念化されたものが、あれほどまざまざと見えるって ことは、ちょっとないですよ。それは、同じ感性を持ってない人、そもそも映画に興味のない人には、ほとんど何もわからない。だけどそういう力を持っていた 人がいたということはすごいことです。
柄谷)それじゃあ、ぼくには関係ないな(笑)。
浅田)たしかに、『哲学とは何か』でも、哲学と科学に並んで、芸術を大きく取り上げている。芸術家は、自存する感覚のブロックをつくり、そこから、潜在的 でも顕在的でもない、可能性の宇宙を作り上げるのだ、と。とすると、それが哲学的に見ると浅いものかもしれない。にもかかわらず、ドゥルーズにとって はーーそして、柄谷さんはともあれ、蓮實さんと同じくぼくにとってもーーかけがえのないものなんです。
1. 序論
2.巨大株式会社
3.余剰の増大傾向
4.余剰の吸収。資本家の消費と投資。
5.余剰の吸収。販売努力。
6.余剰の吸収。 市民政府。
7.余剰の吸収。軍国主義と帝国主義 。
8.独占資本主義の歴史 。
9.独占資本主義と人種問題。
10独占資本主義社会の質的側面。
11. 不合理な体制。
(岩波とは別訳)
Kalecki, M. [1932], "Czy mozliwe jest kapitalisty- czne' wyjscie z kryzysu?" (Is a Capitalist' Overcoming of the Crisis Possible?), Przeglad Socjalistyczny, No. 10, in Kalecki [1990].
カレツキー『経済動学研究』初版。
ポーランドの経済学者で『一般理論』の同時発見者ともされるミハウ・カレツキは、マクロとミクロを結びつけた資本主義経済に関する大きな本を3冊書いている。”Essays in Theory of Economy Fluctuations, 1939” 、“Studies in Economic Dynamics, 1943”および “Theory of Economic Dynamics, 1954”である。
発行順でその中間に発行された本書は、”Essays” から“Theory”へ完成度を高めて行く中間段階の著作として大きな評価がなされていない(宮崎義一『近代経済学の史的展開』およびP.クライスラー 金尾敏寛他訳『カレツキと現代経済』等)せいか、翻訳もなされていない。
本書は、古書市場にも出て来ず、大学図書館の所蔵も少なく私製本が目録に載っているくらいだから稀覯本であろう。長らく探求書であった。このたび入手してみると、戦時経済統制下に発行された簡素な本であった。”BOOK PRODUCTION WAR ECONOMY STANDARD”とマークが標題紙裏に印刷されている。発行部数も少ない上、粗末な装丁のため保存されるのも少なかったと思える。
ちなみに、”Essays”の翻訳本の題名は『ケインズ雇傭と賃銀理論の研究』となっており、戦争文化研究所が昭和19年に発行したもの。こちらも、完全な戦時仕様である。題名がケインズ云々となっているのは、「カレツキはケインズの同工異曲であると誤解され・・・彼の経済思想が十分評価されるようになったのは、つい最近のことなのである。」(ブローグ 中矢訳『ケインズ以後の100大経済学者』)事情によるのであろう。
 |  | |
| 写真左が”Fluctuations”の翻訳書、右が本書 | (拡大可能) |
| (H16.12.記. H21.5.12写真追加 B) |
- 「投資は, 支出としてみると,繁栄の源泉であり,投資の増加は景気を好転させ,投資を刺激して,さらにそれを増大せしめる.しかし投資は同時に,資本設備の増加であり,したがって,生れたときから,この設備の旧式のものと競争する.投資の悲劇はそれが有用であるという理由から恐慌を生ぜしめる点にある.多くの人たちは,この理論をたしかにパラドクシカルと考えるであろう.しかしパラドクシカルなのは,理論ではない,その主題一資本主義経済一そのものである.」(Essays in the Theory of Economic Fluctuations pp189-9,1939)1937版と同じ最終部。新評論版(『経済変動の理論1958年』)訳者あとがきより孫引きWe see that the question, " What causes the periodical crisis ? " could be answered shortly: the fact that the investment is not only produced but also producing. Investment considered as capitalists' spending is the source of prosperity, and every increase of it improves business and stimulates a further rise of spending for investment. But at the same time investment isan addition to the capital equipment and right from birth it competes with the older generation of this equipment. The tragedy of investment is that it calls forth the crisis because it is useful. I do not wonder that many people consider this theory paradoxical. But it is not the theory which is paradoxical but its subject-the capitalist economy.London. MICHAL KALECKI.