マルクス1,6
☆
定理四三 真の観念を有する者は、同時に、自分が真の観念を有することを知り、かつそのことの真理を疑うことができない。
証明 我々の中の真の観念は、神が人間精神の本性によって説明される限りにおいて神の中で妥当な観念である(この部の定理一一の系により)。そこで今、神が人間精神の本性によって説明される限りにおいて神の中に妥当な観念Aが存在すると仮定しよう。この観念についてはまた、この観念と同様の仕方で神に帰せられるある観念が神の中に必然的に存在しなければならぬ(この部の定理二〇による。その証明は普遍的である〈そしてすべての観念にあてはめられうる〉から)。ところが、仮定によれば、観念Aは神が人間精神の本性によって説明される限りにおいて神に帰せられている。ゆえに観念Aの観念もまた同様の仕方で神に帰せられなければならぬ。言いかえれば(再びこの部の定理一一の系により)観念Aについての妥当なこの観念は、妥当な観念Aを有する同じ精神の中に在るであろう。したがって、妥当な観念を有する者、あるいは(この部の定理三四により)物を真に認識する者は、同時に、自分の認識について妥当な観念あるいは真の認識を有しなければならぬ。言いかえれば(それ自体で明らかなように)彼は同時にそれについて確実でなければならぬ。Q・E・D・
備考 この部の定理二一の備考の中で私は、観念の観念とは何であるかを説明した。しかし前定理はそれ自体で十分明白であることをここに注意しなくてはならぬ。なぜなら、真の観念を有する者は誰でも、真の観念が最高の確実性を含んでいることを知っているからである。というのは、真の観念を有するとは物を完全にあるいは最も善く認識するという意味にほかならないから。実際これについては何びとも疑うことができない。観念が画板の上の画のように無言のものであって思惟様態すなわち認識作用そのものではないと信じない限りは。あえて問うが、前もって物を認識していないなら自分がその物を認識していることを誰が知りえようか。すなわち前もって物について確実でないなら自分がその物について確実であることを誰が知りえようか。次に真理の規範として役立つのに真の観念よりいっそう明白でいっそう確実なものがありえようか。実に、光が光自身と闇とを顕(あら)わすように、真理は真理自身と虚偽との規範である。
参考:
アルチュセール オランダ語
https://www.marxists.org/nederlands/althusser/1978/1978crisismarxisme.htm#v1
2:43備考
真理は真理自身と虚偽との規範である。
http://nam21.sakura.ne.jp/spinoza/#note2p43n
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Marx,+Karl/Bemerkungen+%C3%BCber+die+neue+preu%C3%9Fische+Zensurinstruktion
「 プロイセンの最新の検閲訓令にたいする見解.一ライン州人」1.3で引用
Verum index sui et falsi
In einer anderen Sprache lesen
Seite beobachten
Bearbeiten
„Est enim verum index sui et falsi“ schrieb Baruch Spinoza in seinem 74. Brief an Albert Burgh, mit dem er auf dessen Brief vom 10. September 1675 antwortete: Denn das Wahre ist der Prüfstein seiner selbst und des Falschen.[1] Ähnlich äußerte er sich im 2. Buch seiner Ethik: „Sane sicut lux seipsam et tenebras manifestat, sic veritas norma sui et falsi est“, „Wahrlich wie das Licht sich selbst und die Finsternis offenbart, so ist die Wahrheit die Norm ihrer selbst wie des Falschen.“[2]
Die Verwendung des Ausdrucks durch Karl Marx
Literatur
- Henry Deku: Wahrheit und Unwahrheit der Tradition. Metaphysische Reflexionen. Herausgegeben von Werner Beierwaltes. EOS-Verlag, St. Ottilien 1986, ISBN 3-88096-033-X.
Fußnoten
- ↑ Benedicti de Spinoza Opera quae supersunt omnia, herausgegeben von Karl Hermann Bruder, vol. II. Leipzig 1844. p.351 books.google; Übersetzung Arthur Buchenau. Leipzig 1907. p.234 books.google
- ↑ s:Ethica - Pars secunda - De natura et origine mentis, Übersetzung Arthur Buchenau 1841 http://gutenberg.spiegel.de/buch/ethik-5217/6
- ↑ entstanden 1841/42, Erstdruck 1843
- ↑ Im Original: „Die Zensur wird keine ernsthafte und bescheidene Untersuchung der Wahrheit hindern, [...]“. http://www.heinrich-heine-denkmal.de/dokumente/zensurgesetz.shtml
- ↑ Karl Marx: Bemerkungen über die neueste preußische Zensurinstruktion. Von einem Rheinländer. In: Marx-Engels-Werke, Bd. 1: 1839–1844, Dietz, Berlin, 10. Aufl. 1976, S. 3–27, Zitat S. 6. http://www.zeno.org/nid/20009220712
上記の論理は、
マルクスがスピノザから引用したVerum index sui et falsi(1.6頁)
「真理は真理自身と虚偽との規範である」を想起させる。
ヘーゲルが引用した「あらゆる規定は否定である(Omnis determinatio est negatio)」☆☆
『スピノザ往復書簡』(238~9頁)よりもスピノザらしい
前者は光学モデルを想定しているからだ
《実に、光が光自身と闇とを顕(あら)わすように、真理は真理自身と虚偽との規範である。》
…エチカ2:43備考より
ただしそれを引用するマルクスは排中律にこだわりすぎ、依然法学モデルに囚われている。
経済学モデルに目覚めるのはプルードンとの往復書簡以降である。
排中律を濫用すると切り裂かれる中産階級の動学的課題(プカレリアート)
にうまく対応できない。
マルクスはカントの法学に限界を感じたらしいが(40.7~8頁父への手紙1837年☆☆☆)、それはアンチノミーを
放棄させる方向へ向かった。
むしろ経済学モデルはより高い倫理性を呼び込むという点でカントの再考でなければならなかった。
スピノザから排中律のみを取り出し、カントからアンチノミーを捨て去ったのがマルクスの限界だった。
柄谷行人はマルクスが間違えた地点からやり直しているのだ。

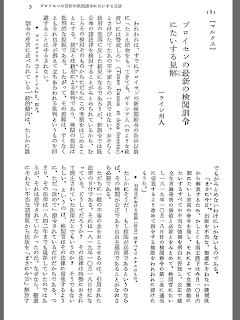



マルクスはスピノザに学びつつスピノザの体系に異議を唱えた。
「たとえばスピノザの場合でさえ、彼の体系の本当の内的構造は、彼によって体系が意識的に
叙述された形式 とはまったく違っている」
(マルクス、ラサール宛書簡1858年5月31日 大月全集29巻、438頁)
しかし、マルクスの体系こそスピノザに従属する(べきな)のである。
(例えば、マルクスが前提とした複利を伴った貨幣体系はその実体経済と一致しない。
スピノザの言葉で言えば、観念とその対象が一致しないのだ。〜エチカ1:a6〜)
マルクスは『神学政治論』の抜き書きをしているが、参照するべきは『エチカ』だ。
ヘーゲル、マルクスを読む際にもスピノザに立ち返る必要がある。そこからやり直すしかない。
ドゥルーズもスピノザ、ライプニッツ研究者であり続けた(この三者はともに並行論者だが、
ヘーゲル、マルクスは彼らとは違って弁証法信奉者だった)。