中野剛志 MMTが、こんなにも「エリート」に嫌われる理由 主流派経済学の理想は 「反民主的」な経済運営 2019/6/11 toyokeizai.net
keynes-yap(uap) 1915
参考:
フェリックス・マーティン『21世紀の貨幣論』2014
マネーとは何か。なぜ人はマネーに翻弄されるのか。
気鋭のエコノミストによる、定説を覆す斬新なマネーの進化史。マネーをめぐる6000年の歴史をひもとき、経済学と資本主義の未来を問う。
■伝説の哲学者ジョン・ロックが経済学に間違った思想を植え付けた!?
・経済学思想の源流をたどり、歯に衣着せぬ大胆不敵な主張を展開。
■物々交換の不便さから、マネーという最強の発明が生まれたという定説はウソ!?
・ケインズとフリードマン、なぜ2人の偉大な経済学者が
『ヤップ旅行記』という地味な本を賞賛したのか?
気鋭のエコノミストによる、定説を覆す斬新なマネーの進化史。マネーをめぐる6000年の歴史をひもとき、経済学と資本主義の未来を問う。
■伝説の哲学者ジョン・ロックが経済学に間違った思想を植え付けた!?
・経済学思想の源流をたどり、歯に衣着せぬ大胆不敵な主張を展開。
■物々交換の不便さから、マネーという最強の発明が生まれたという定説はウソ!?
・ケインズとフリードマン、なぜ2人の偉大な経済学者が
『ヤップ旅行記』という地味な本を賞賛したのか?
《ファーネスの本は 「通貨について 、おそらく他のどの国よりも哲学的な思想を持つ人々がいることを私たちに教えてくれた 。ヤップ島の慣行は現代の金本位制度よりも論理的であり 、学ぶことは大いにある 」と 、ケインズは書いている ★ 8 。 2 0世紀の最も偉大な経済学者がなぜ 、ヤップ島のマネーシステムにこのような重要で普遍的な教訓を見いだしたのか 。それが本書のテ ーマである。》
http://shavetail2.hateblo.jp/entry/20141112
http://www.randomhouse.com/highschool/catalog/display.pperl?isbn=9780345803559&view=excerpt
http://www.randomhouse.com/highschool/catalog/display.pperl?isbn=9780345803559&view=excerpt
When it was published in 1910, it seemed unlikely that
Furness' eccentric travelogue would ever reach the notice of
the economics profession. But eventually a copy happened to
find its way to the editors of the Royal Economic Society's
Economic Journal, who assigned the book to a young
Cambridge economist, recently seconded to the British
Treasury on war duty: a certain John Maynard Keynes. The
man who over the next twenty years was to revolutionise the
world's understanding of money and finance was astonished.
Furness' book, he wrote, "has brought us into contact with a
people whose ideas on currency are probably more truly
philosophical than those of any other country. Modern
practice in regard to gold reserves has a good deal to learn
from the more logical practices of the island of Yap."8 Why it
was that the greatest economist of the twentieth century
believed the monetary system of Yap to hold such important
K e y n e s , J . M . ( 1 9 1 5 a ) , “ T h e I s l a n d o f S t o n e M o n e y ” . E c o n o m i c J o u r n a l 2 5 ( 9 8 ) , 2 8 1 -3 .
Keynes 1915 The Island of Stone Money Economic Journal 25 (98) 281~3
マーティンはFurness, William H. 3rd. (1915) “The Island of Stone Money.” Economic Journal, 25, 281-3.の無署名原稿をケインズ著と考えている
The Island of Stone Money
The Economic Journal, Volume 25, Issue 98, 1 June 1915, Pages 281–283, https://doi.org/10.2307/2222196
Published:
01 June 1915
- Notes and Memoranda
貨幣と通貨の法文化 | 投資信託の投信資料館
https://www.toushin.com/market-market/column/money_08152016/
11章では、清水義範と谷崎潤一郎の“お金”の誕生にまつわる小説二篇を紹介し、カロリン諸島のヤップ島の石貨フェイについてのケインズとフリードマンの考察を取り上げます。ついでながら、2人が依拠しているのは、ウィリアム・ヘンリー・ファーネスが1910年に著した『石貨の島』で、この石貨のことをフェイというのですが、これは、日銀の貨幣博物館で見ることができます(来年は、ヤップ島に、ずらりと並んだストーン・マネー・バンクを見に行きたいと思っています)。また、コーヒートークン、つまり、いわゆるトラックシステムにおける代用貨幣も、2014年に中米コスタリカを訪ねたときに、博物館ではありましたが、見てきました。今年の春は、沖縄の南北大東島に行き、いわゆる玉置貨幣・通用引換券などと呼ばれた代用貨幣を見てきました。それらを紹介しながら、貨幣について考えるという趣向です。
https://www.coinbooks.org/esylum_v16n37a18.html
https://www.coinbooks.org/esylum_v16n37a18.html
Keynes does reference the phenomenon of Yap money in a footnote on pg. 292 of the second volume of A Treatise on Money (McMillan and Co. 1950, first published 1930). In the relevant passage, Keynes was making a point about how the function of gold in modern monetary management had been increasingly confined to a standard of value. Paradoxically, while gold was revered by its supporters as a tangible commodity, its actual monetary significance was henceforth to serve as an abstraction. As Keynes wrote about gold in his typically arch style:
"It no longer passes from hand to hand, and the touch of the metal has been taken away from men's greedy palms. The little household gods, who dwelt in purses and stockings and tin boxes, have been swallowed by a single golden image in each country, which lives underground and is not seen. Gold is out of sight--gone back again into the soil. But when gods are no longer seen in a yellow panoply walking the earth, we begin to rationalise them; and it is not long before there is nothing left" (p. 291).
I think Keynes had his ideas, and the stone money of Yap simply provided him with yet another deft way to illustrate his argument. There is also a highly interesting discussion of the Yap example on the blog Moneyness: http://jpkoning.blogspot.com/2013/01/yap-stones-and-myth-of-fiat-money.html
To read the earlier E-Sylum article, see: NOTES FROM E-SYLUM READERS: SEPTEMBER 1, 2013 : John Maynard Keynes and Yap Stone Money(www.coinbooks.org/esylum_v16n36a16.html)
中野剛志 MMTが、こんなにも「エリート」に嫌われる理由
主流派経済学の理想は「反民主的」な経済運営
2019/6/11
貨幣の本来の仕組みと、超インフレが起こりえない理由とは(写真:gzorgz/iStock)
前回記事「MMT『インフレ制御不能』批判がありえない理由」で、インフレ率との関係をていねいに解説した中野剛志氏。著書『富国と強兵 地政経済学序説』でいち早く日本にMMT(現代貨幣理論)を紹介した同氏が、今回は「そもそも貨幣とは何か」という視点から解説する。
MMTはなぜ嫌われているのか
MMT(現代貨幣理論)は、高インフレでない限り、財政赤字を拡大してよいと主張する。これに対して、主流派経済学者は、「そんなことをしたら、超インフレになる」と激しく批判している。
このように、超インフレの懸念によってMMTを批判するというのは、極端な議論にすぎないことは、別の記事で明らかにしてあるので、ここでは繰り返さない。
問うべきは、なぜ、このような極端な議論がまかりとおっているかということである。
日本は、20年という長期のデフレに苦しんでいる。そんな日本が超インフレを懸念して、デフレ下で政府支出の抑制に努めたり、増税を目指したりしている姿は、どう考えても異常である。「インフレ恐怖症」とでも言いたくなるほどだ。
なぜ、これほどまで極端にインフレが恐れられているのであろうか。
そして、なぜ、MMTは、こんなに嫌われているのであろうか。
その理由の根源は、貨幣の理解にある。
主流派経済学の標準的な教科書は、貨幣について、次のように説明している。
原始的な社会では、物々交換が行われていたが、そのうちに、何らかの価値をもった「商品」が、便利な交換手段(つまり貨幣)として使われるようになった。その代表的な「商品」が貴金属、とくに金である。これが、貨幣の起源である。
しかし、金そのものを貨幣とすると、純度や重量など貨幣の価値の確認に手間がかかるので、政府が一定の純度と重量をもった金貨を鋳造するようになる。
次の段階では、金との交換を義務付けた兌換(だかん)紙幣を発行するようになる。こうして、政府発行の紙幣が標準的な貨幣となる。
最終的には、金との交換による価値の保証も不要になり、紙幣は、不換紙幣となる。それでも、交換の際に皆が受け取り続ける限り、紙幣には価値があり、貨幣としての役割を果たす(N・グレゴリー・マンキュー『マンキューマクロ経済学I入門篇【第3版】』110~112ページ)。
このような貨幣論を「商品貨幣論」と言う。
しかし、この「商品貨幣論」は、実は、誤りなのである。
第1に、歴史学や人類学における貨幣研究は、軒並み、貨幣が物々交換から発展したという「商品貨幣論」を否定している(フェリックス・マーティン『21世紀の貨幣論』)。
第2に、1971年にドルと金の兌換が廃止されて以降、世界のほとんどの国が、貴金属による裏付けのない不換通貨を発行している。しかし、なぜ、そのような不換通貨が流通しているのかについて、商品貨幣論は納得できる説明ができない。主流派経済学は「他人が受け取ることがわかっているから、誰もが不換通貨を受け取るのだ」という説明をするが、そんな脆弱な大衆心理に依拠した通貨では、価値が不安定すぎて使い物にはなるまい。
では、現代の不換通貨は、どうして「貨幣」としての価値が保証され、使われているのであろうか。
政府の「徴税権力」が物価を調整する
MMTの答えは極めて明快だ。
まず、政府は、債務などの計算尺度として通貨単位(円、ドル、ポンドなど)を法定する。
次に、国民に対して、その通貨単位で計算された納税義務を課す。
そして、政府は、通貨単位で価値を表示した「通貨」を発行し、租税の支払い手段として定める。これにより、通貨には、納税義務の解消手段としての需要が生じる。
こうして人々は、通貨に額面どおりの価値を認めるようになり、その通貨を、民間取引の支払いや貯蓄などの手段としても利用するようになり、通貨が流通するのである。
要するに、人々がお札という単なる紙切れに通貨としての価値を見出すのは、その紙切れで税金が払えるからということだ。
通貨の価値を裏付けているのは、金などの価値のある「商品」ではない。通貨を法定し、その通貨による納税義務を法定する権力をもつ「政府」である。政府の徴税権力こそが、通貨の価値を担保するアンカーとなっているのだ。
それゆえ、内乱などで無政府状態に陥った国家では、政府の徴税権力も弱体化するから、通貨はその価値を失い、超インフレに見舞われる。逆に言えば、政府権力が正常に機能していれば、戦争や石油危機のような有事でもない限り、インフレが制御不能になるなどということはありえない。
政府が徴税権力を強めれば(緊縮財政)、納税という通貨の需要が増えるので、人々はモノよりもカネを欲しがるようになる。その結果、通貨の価値が上昇(物価が下落)する。つまり、増税は、デフレ圧力を発生させるのだ。
反対に、政府が徴税権力を緩めれば(拡張財政)、納税という通貨の需要は減るので、通貨の価値が下落(物価が上昇)する。減税は、インフレ圧力を発生させるのである。
こうして、政府は、財政を拡張させたり、緊縮させたりすることによって、物価を上下させることができる。財政政策とは、物価調整という機能をもつ金融政策でもあるのだ。
貨幣に関する無知が招く「インフレ恐怖症」
さて、主流派経済学は、依然として「商品貨幣論」という誤った貨幣論に立脚している。
実は、この誤った貨幣論こそが、「インフレ恐怖症」の原因なのである。
改めて説明すると、「商品貨幣論」は、金などの貴金属のような、それ自体に価値がある商品が貨幣の価値を裏付けていると考えている。
かつて、金本位制の下においては、通貨には、金との兌換が義務付けられていた。各国政府が発行する通貨の価値は、金という商品によって担保されていたのである。
しかし、現代の通貨は、金との兌換が保証されていない「不換通貨」が一般的になっている。このことを、主流派経済学は「商品貨幣論」によってどう説明するのか。
すでに述べたように、主流派経済学は、「他人が受け取ることがわかっているから、誰もが不換通貨を受け取るのだ」と説明している。つまり、「みんながお金がお金だと思っているから、みんながお金をお金だと思って使っている」という苦し紛れの循環論法である。
もし、この説が正しいとすると、通貨の価値は、「みんなが通貨としての価値があると信じ込んでいる」という極めて頼りない大衆心理によって担保されているということになる。
しかし、もし人々が一斉に通貨の価値を疑い始めてしまったら、通貨はその価値を一瞬にして失ってしまうだろう。紙幣は、単なる紙切れとなってしまうのだ。これが、通貨価値の暴落、すなわちハイパーインフレである。
主流派経済学者が、なぜインフレを極端に恐れているのか、もうおわかりだろう。「もし、人々が通貨に対する信認を失い、通貨の価値を保証するものがなくなってしまったら、どうしよう」と不安で仕方がないのだ。
要するに、主流派経済学者は、それ自体に商品価値がないはずの不換通貨が、なぜ通貨として流通しているのかについて、本当のところをわかっていないのだ。だから、通貨の価値が失われることを極端に恐れているのである。
「インフレ恐怖症」の原因は、貨幣に関する無知にある。
そうであるならば、主流派経済学者は、MMTの正しい貨幣論を受け入れればよいではないかと思われるかもしれない。
それが、残念ながら、そう簡単にはいかないのである。
なぜなら、MMTは「通貨の価値を保証するのは、政府の徴税権力である」という理論である。
国民主権である民主国家においては、政府の徴税権力の根源は民主政治にある。わが国でも、憲法第83条において、国会が予算や税を議決する「財政民主主義」を定めている。
このように、現代民主国家においては、通貨の価値を保証するのは「徴税権力=民主政治」である。したがって、民主政治は、貨幣価値(物価)を調整するうえで、決定的に重要な役割を担うこととなる。
しかし、このような結論は、主流派経済学者には、とうてい受け入れられるものではない。
なぜならば、民主政治は、民意や政治的な利害調整によって決まるものである。そのような恣意的・裁量的な民主政治が財政を決め、物価の調整に深く関与することを、主流派経済学は極端に恐れるのである。
だから、主流派経済学者は、財政規律を重視し、民主政治による財政権力に制限を加えようとする。そして、物価の調整機能は、民主政治ではなく、中央銀行に委ねるべきだとする。主流派経済学者は「中央銀行の独立性」を強調するが、それは、民主政治からの「独立性」を意味しているのだ。
要するに、主流派経済学は、エリートや専門家による経済運営を理想とするのである。言い換えれば、主流派経済学は、その本質において、反民主主義的である。
こうした主流派経済学の理解に基づき、現実の経済運営は、中央銀行の金融政策が主導するものとなり、財政政策に対する評価は消極的・否定的なものとなった。
MMTは経済政策の「民主化」
しかし、今日、アメリカでも欧州でも日本でも、その金融政策主導の経済運営が完全に行き詰ってしまった。近年では、クルーグマン、サマーズ、ブランシャールのような主流派経済学者ですら、金融政策の限界を認め、財政赤字の拡大を強く主張するようになっている(オリヴィエ・ブランシャール「日本の財政政策の選択肢」)。
とくに日本では、量的緩和という金融政策主導によるデフレ脱却は、明らかに失敗に終わった。昨今では、金融政策の限界どころか、その弊害すら懸念されるようになっている(「危険なMMTがそれでも気になる理由」)。
しかし、こうした従来の金融政策主導の経済運営は、その根拠となっている主流派経済学が貨幣論からして間違っている以上、失敗に終わって当然だったのである。
ここで重要なのは、財政主導の経済運営とは、民主政治主導の経済運営を意味するということだ。経済政策の「民主化」と言ってもよい。
MMTは、経済政策を「民主化」すべきだと主張しているのだ(だから、アメリカでは、反エリート主義的な民主党左派などがMMTを支持するのである)。
超インフレは本当に起こるのか?
民主政治が完全なものではないのは、事実である。賢明とは言えない判断もする。しかし、主流派経済学に基づいたエリート主義的な経済運営が失敗に終わった以上、民主政治の判断で財政政策を発動するほかないのだ。
その民主政治をより賢明なものにするか否かは、われわれ国民の責任にかかっている。財政規律などインフレを抑制する制度を導入するにしても、国民が民主的に決めなければならないのだ。
筆者は、日本の政治、そして日本国民が、財政支出を拡大しすぎて超インフレを引き起こすほど愚昧だとはまったく思っていない。普通に考えて、国民が、自分たちの生活を破壊する超インフレを招くような政権を支持するはずがないではないか。「MMTを実行したら、超インフレになる」などという者は、日本の有権者をバカにしているのだ。
日本の民主政治は、確かに完全なものではない。しかし、超インフレを防げないほどではない(「MMT『インフレ制御不能』批判がありえない理由」)。
他方、主流派経済学の理論は、もっと不完全である。それどころか、貨幣論からして間違えている。
MMTの批判者たちは、エリートぶって民主政治を見下す前に、せめて貨幣について正しく理解してはどうか。そうすれば、どんなに不完全であっても、民主政治によって経済運営を運営するしかないのだと分かるだろう。
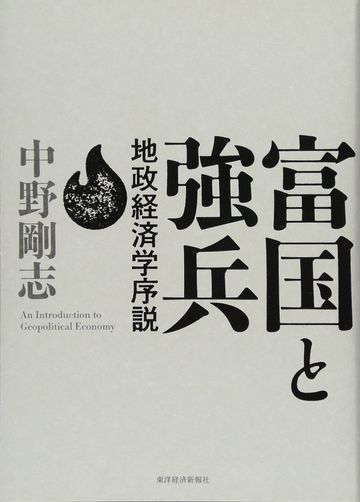

0 Comments:
コメントを投稿
<< Home