https://love-and-theft-2014.blogspot.com/2021/07/18-7-2011127-ukiuki-54.html
佐村論考
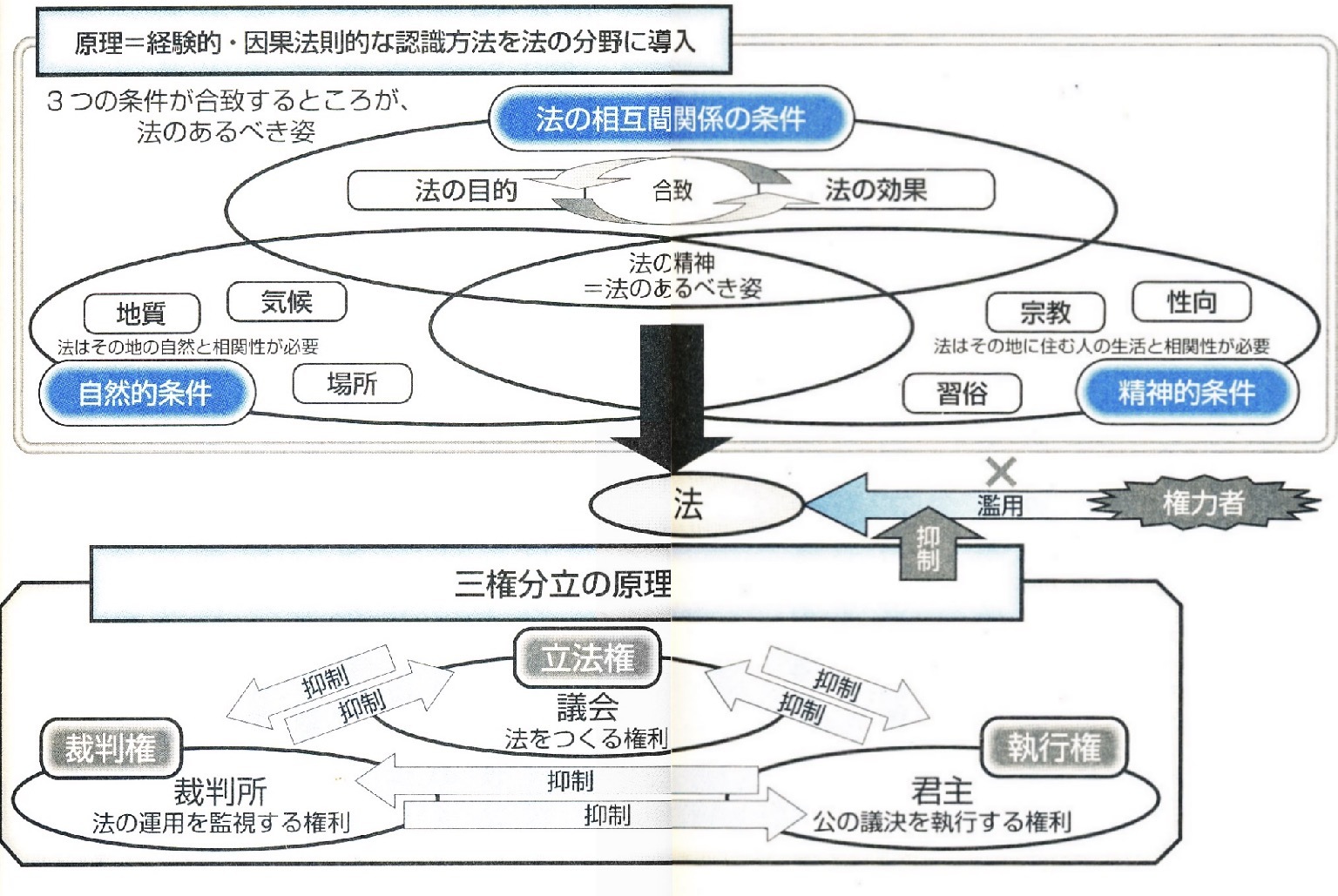
第 十五 篇 市民的奴隷制の法は風土の性質とどのような関係を有するか
《…籤による投票は民主制の性質をもち、選択による投票は貴族制の性質をもつ。
抽籤はだれをも苦しめない選び方である。それは、各市民に、祖国に奉仕したいというもっともな希望を残す。
しかし、それは、それ自体として欠陥をもっているから、偉大な立法者たちは、それを規制し、矯正するために競いあった。
アテナイでは、ソロンが、全軍職は選択により任命され、元老院議員と裁判官は、籤で選ばれるよう定めた。
彼は、大きな出費を要する政務官職は選択にょり与えられ、他の職は籤で与えられることを望んだ。
しかし、抽籤を修正するために、彼は、立候補した者の中からしか選べないこと、選ばれた者は、裁判官により審査されること、だれもが、選ばれた者を不適格として弾劾しうることを規定した。それは、同時に、抽籤にも選択にも相通じていた。政務官職の終わりには、人は、自分の行動した仕方について、いま一度審査を受けなければならなかった。無能な人々は、抽籤に自分の名を出すのを、大いにきらったにちがいない。…》
…セイは暗黙のうちに、経済システムは常に容量いっぱいで動いているものと想定し、新しい活動は常に他の活動に代替されるもので、決して追加はされないのだと考えていました。その後のほぼあらゆる経済理論は、これがなければ成立しないという意味で、この想定に依存していました。でもそんな基盤の理論は明らかに、失業と事業サイクルの問題に取り組む能力を持ちません。たぶんフランスの読者に対して本書の主張をできるだけうまく表現するなら、それはJ・B・セイのドクトリンからの最終的な決別であって、そして金利の理論においてそれはモンテスキューのドクトリンへの回帰なのです。
J. M. ケインズ
1939年2月20日
キングスカレッジ、ケンブリッジ
|
福田歓一『近代政治原理成立史序説』岩波書店、1971年
ホッブズ(英,1588~1679)→ロック→ルソーという政治思想史のストーリーを定着させた古典。
ホッブズ→ロック→モンテスキュー→トクヴィル→アーレント
↘︎ルソー//////////
☆☆☆『法の精神』目 次 (詳細目次:作業中)◆原 序第 一 部第 一 篇 法一般について第 一 章 法と諸存在物との関係について第 二 章 自然法について第 三 章 制定法について第 二 篇 政体の本性に直接由来する法について第 一 章 三種の政体の本性について ○第 二 章 共政体について、および民主政に関する法について ☆A第 三 章 貴族政の性質に関する法について第 四 章 君主政体の本性との関係における法について ☆B第 五 章 専制国家の本性との関係における法について第 三 篇 三政体の原理について ##第 一 章 政体の本性とその原理との差異第 二 章 各種の政体の原理について第 三 章 民主政の原理について第 四 章 貴族政の原理について第 五 章 徳性は君主政体の原理ではないこと第 六 章 君主政体において徳性のかわりとなるものは何か第 七 章 君主政の原理について第 八 章 名誉はけっして専制国家の原理ではないということ第 九 章 専制政体の原理について第 十 章 制限政体と専制政体における服従の差異第 十一 章 以上すべてについての省察第 四 篇 教育法は政体の原理と関係せねばならぬ…第 五 篇 立法者の制定する法は政体の原理と関連していなければならぬこと…第 六 篇 各種政体の原理の帰結と民法、刑法の簡単さ、裁判の形式および刑の決定との関係…第 七 篇 奢侈禁止法、奢侈および婦人の地位に関する三政体の種々の原理の帰結…第 八 篇 三政体の原理の腐敗について…第 二 部第 九 篇 法と防禦力との関連について…第 十 篇 法と攻撃力との関係…第 十一 篇 政治的自由と国家構造との関係における法について第 一 章 一般的観念第 二 章 自由なる語にあたえられる多様な意義第 三 章 自由とは何であるか第 四 章 同じ題目のつづき第 五 章 諸種の国家の目的について第 六 章 イギリスの国家構造について ###第 七 章 われわれの知る君主国について第 八 章 なぜ古代人は君主政について明確な観念を持たなかったか第 九 章 アリストテレスの考え方第 十 章 その他の政治学者の考え方第 十一 章 ギリシャにおける英雄時代の諸王について第 十二 章 ローマの王政について、および、その三権分配の態様第 十三 章 国王放逐後のローマの状態についての一般的省察第 十四 章 国王放逐後三権の分配がいかに変わりはじめたか第 十五 章 ローマは共和政の繁栄状態において、いかにして突然その自由を失ったか第 十六 章 ローマ共和政における立法権について第 十七 章 同じ共和政における執行権について第 十八 章 ローマの統治における裁判権について第 十九 章 ローマの州政治について第 二十 章 本篇の結尾…第 十二 篇 政治的自由を構成する法と市民との関係について…第 十三 篇 租税の徴集と国家収入が自由にたいして持つ関係…第 三 部第 十四 篇 法と風土の関係…第 十五 篇 市民的奴隷制の法は風土の性質とどのような関係を有するか
…
第 十六 篇 家内奴隷制の法はいかに風土の性質と関係するか…第 十七 篇 政治的奴隷制の法は風土の性質といかに関係するか…第 十八 篇 法と地味の性質の関係…第 十九 篇 国民の一般精神・習俗・生活様式と法との関係…第 四 部第 二十 篇 本質ならびに種別において考察せる商業との関係における法について…第二十一篇 世界においてその経験せる諸変革において考察せる商業と法との関係…第二十二篇 貨幣の使用との関係における法について第 一 章 貨幣使用の理由第 二 章 貨幣の性質について第 三 章 観念的貨幣について第 四 章 金と銀との量について第 五 章 同じ題目のつづき第 六 章 アメリカ発見後、金利が半減した理由第 七 章 物の価格はいかにして富の表徴の変動において定まるか第 八 章 同じ題目のつづき第 九 章 金と銀との相対的稀少性について第 十 章 為替について第 十一 章 貨幣に関してローマ人のとった処置について第 十二 章 ローマ人が貨幣にたいしてその処置をとった事情第 十三 章 皇帝時代の貨幣にたいする処置第 十四 章 いかに為替は専制国に妨げとなるか第 十五 章 イタリヤの二、三の地方の慣行第 十六 章 国家が銀行家から引き出しうる援助について第 十七 章 公債について第 十八 章 公債の支払いについて第 十九 章 利子つき貸借について ☆☆第 二十 章 海上高利について第二十一章 ローマにおける契約による貸借と高利について第二十二章 同じ題目のつづき第二十三篇 住民の数との関係における法について第 一 章 種の繁殖との関係における人間と動物について第 二 章 婚姻について第 三 章 子の身分について第 四 章 家について第 五 章 適法の妻の順位について第 六 章 各種政体における庶子について第 七 章 婚姻にたいする父の同意について第 八 章 同じ題目のつづき第 九 章 娘について第 十 章 婚姻を決意せしむるもの第 十一 章 統治の苛酷について第 十二 章 諸国における女児と男児の数について第 十三 章 海港について第 十四 章 多少とも人手を要する土地の生産物について第 十五 章 工業との関係における住民の数について第 十六 章 種の増殖についての立法者の関心について第 十七 章 ギリシャとその住民の数について第 十八 章 ローマ以前の人口状態第 十九 章 世界の人口減少第 二十 章 ローマ人は種の繁殖のための法を作る必要にせまられたこと第二十一章 種の繁殖に関するローマ人の法について第二十二章 子の遺棄について第二十三章 ローマの滅亡後の世界の状態について第二十四章 住民の数に関してヨーロッパにおいて生じた変化第二十五章 同じ題目のつづき第二十六章 結論第二十七章 種の繁殖を助長するためフランスで作られた法について第二十八章 いかにして人口減退を救済しうるか第二十九章 救済院について第 五 部第二十四篇 法と、宗式およびそれ自体において考察せられたる各国に行なわれる宗教との関係第 一 章 宗教一般について第 二 章 ベイルの逆説第 三 章 制限政体はキリスト教によりよく適合し、専制政体は回教に適すること第 四 章 キリスト教の性格と回教のそれの結果第 五 章 カトリック教は君主政によりよく適合し、新教は共和政によりよく調和すること第 六 章 ベイルの他の逆説第 七 章 宗教における完全の法について第 八 章 道徳の法と宗教の法との一致について第 九 章 エッセニヤン派について第 十 章 ストア派について第 十一 章 瞑想について第 十二 章 難行苦行について第 十三 章 つぐないえぬ罪について第 十四 章 いかにして宗教は市民法に影響しうるか第 十五 章 いかにして法は時として虚偽の宗教を矯正するか第十六 章 宗教の法はいかにして政体の欠陥を矯正するか第 十七 章 同じ題目のつづき第 十八 章 いかに宗教法が市民法の効果を持つか第 十九 章 教義を社会にとって有益か危険かにするものは、その真実性と虚偽性よりもむしろその利用または悪用であること第 二十 章 同じ題目のつづき第二十一章 輪廻について第二十二章 どうでもよいことにたいし宗教が嫌悪の情をおこさせるのはいかに危険であるか第二十三章 祭典について第二十四章 地方的な宗教の法について第二十五章 宗教を一国から他国へ移動する不便第二十六章 同じ題目のつづき第二十五篇 各国の宗教の設立とその対外政策との関係における法について第 一 章 宗教にたいする感情について第 二 章 諸宗教にたいする愛着の動機第 三 章 寺院について第 四 章 司祭について第 五 章 法が聖職階級の富にたいして加えるべき制限について第 六 章 修道院について第 七 章 迷信の奢侈について第 八 章 司祭長の位置について第 九 章 宗教に関する寛容について第 十 章 同じ題目のつづき第 十一 章 宗教の変更について第 十二 章 刑法について第 十三 章 スペインおよびポルトガルの宗教裁判官にたいするうやうやしき建言第 十四 章 なぜキリスト教は日本でかくも嫌われるのであるか第 十五 章 布教について第二十六篇 法が判定を下す事物の秩序との問に持つべき関係における法について #第 一 章 本篇の概要第 二 章 神法および人法について第 三 章 自然法に反する市民法について第 四 章 同じ題目のつづき第 五 章 自然法の原理を修正し、市民法の原理によって判断しうる場合第 六 章 相続の順序は政法または市民法の原理によるもので、自然法の原理によるものでないこと第 七 章 自然法の掟に関する事項を宗教の掟で決定すべきでないこと第 八 章 市民法の原理によって規定される事物をいわゆる『カノン法』の原理によって規定すべきでないこと第 九 章 市民法の原理によって規正さるべき事物が、宗教法の原理によって規正されうることはまれであること第 十 章 いかなる場合に、許容する市民法にしたがうべきで、禁止する宗教法にしたがうべきでないか第 十一 章 来世に関する裁判所の格律によって人間の裁判所を規正すべきでないこと第 十二 章 同じ題目のつづき第 十三 章 婚姻に関していかなる場合に宗教法にしたがい、いかなる場合に市民法にしたがわねばならぬか第 十四 章 親族間の婚姻はいかなる場合に自然法により、いかなる場合に市民法によって規定さるべきか第 十五 章 市民法の原理に依存する事柄を政法の原理によって規正してはならぬこと第 十六 章 政法の規定によって決定すべき場合に市民法の規定によって決定すべきでないこと第 十七 章 同じ題目のつづき第 十八 章 たがいに矛盾するように見える法は同じ秩序に属するものかどうかを調べねばならぬこと第 十九 章 家法によって決定さるべきことを市民法によって決定してはならぬこと第 二十 章 万民法に属することを市民法の原理によって決定してはならぬこと第二十一章 万民法に属することを政法によって決定してはならぬこと第二十二章 インカ皇帝アチュアルパの不幸な運命第二十三章 何かの事情により政法が国家にとって破壊的となる場合、国家を保全し、またしばしば万民法となる他の政法によって決定すべきこと第二十四章 警察規則は他の市民法とは別の秩序に属すること第二十五章 それ自身の性質から引出される特殊な規定にしたがうべき事物に関する場合、市民法の一般的規定にしたがってはならぬこと第 六 部第二十七篇 相続に関するローマ人の法の起源および変遷について単一の章 相続に関するローマの法について第二十八篇 フランス人における市民法の起源ならびに変遷について…第二十九篇 法のつくり方について…第 三十 篇 (第 一 章 封建法について 他)…第三十一篇 フランク人における封建法の理論とその君主政の変遷との関係…








れがあまり高価であれば「商人はその取引において儲けうるよりも、金利にいっそう費用がかかるであろうと考えて、何
ごとをもくわだてない。金銭がぜんぜん代価を持たぬと、だれもそれを貸さないので、同じく商人は何もわだてない。
ところで、わたしがだれも金を貸すやつはいないといったのはまちがいである。社会の諸事業はたえず進行しなければな
らぬ。そこで闇金利(ウズラ)が成立する。しかしあらゆる時代に人々が経験した混乱をともなうのである。…》
(『法の精神』河出書房新社版338頁)
ケインズは上記のモンテスキュー『法の精神』22巻19章(「第十九章 利子つき貸借について」)に流動性の原理、有効需要の精神(というより金利と自然成長率との関係)を見出している(講談社学術文庫一般理論、フランス語版序文より)。