漸、竪出
聖道門、難行道、自力、竪{ }
頓、竪超
二双{ }四重
漸、横出
浄土門、易行道、他力、横{ }
頓、横超
\菩提心 竪 横 ←二双
教\ 自力 他力
I
竪出 I 横出
出 漸教\聖道門 I 漸教\浄土門
-----------+------------ ←四重
竪超 I 横超
超 頓教\聖道門 I 頓教\浄土門
(空海) I (親鸞)
竪超 (しゅちょう) 厳しい修行をして一気に悟ろうとする。
横超(オウチョウ)とは - コトバンク kotobank.jp/word/横超-449177
仏語。阿弥陀仏の本願の力によって迷いの世界を 跳び越えて、
浄土に往生すること。真宗の説く、他力浄土門の中の絶対他力の教えを いう。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
二双四重
にそうしじゅう
\心 竪 横 二双
教\
出 漸教\聖道門 漸教\浄土門
四重
超 頓教\聖道門 頓教\浄土門(親鸞)☆
竪の聖道門に成仏の遅速に応じて漸教と頓教を分けられ、竪出、竪超とされる。
大乗は二乗・三乗あることなし。二乗・三乗は一乗に入らしめんとなり。一乗はすなはち第一義乗なり。ただこれ誓願一仏乗なり。
http://wikidharma.org/4b9399ba7bf3a
【52】 しかるに菩提心について二種あり。一つには竪、二つには横なり。
また竪についてまた二種あり。一つには竪超、二つには竪出なり。竪超・竪出は権実・顕密・大小の教に明かせり。歴劫迂回の菩提心、自力の金剛心、菩薩の大心なり。また横についてまた二種あり。一つには横超、二つには横出なり。横出とは、正雑・定散、他力のなかの自力の菩提心なり。横超とは、これすなはち願力回向の信楽、これを願作仏心といふ。願作仏心すなはちこれ横の大菩提心なり。これを横超の金剛心と名づくるなり。
http://wikidharma.org/4b93a105abf98
【73】 横超断四流といふは、横超とは、横は竪超・竪出に対す、超は迂に対し回に対するの言なり。竪超とは大乗真実の教なり。竪出とは大乗権方便の教、二乗・三乗迂回の教なり。横超とはすなはち願成就一実円満の真教、真宗これなり。また横出あり、すなはち三輩・九品、定散の教、化土・懈慢、迂回の善なり。大願清浄の報土には品位階次をいはず。一念須臾のあひだに、すみやかに疾く無上正真道を超証す。ゆゑに横超といふなり。
http://wikidharma.org/4b93acfa2387b
【35】 おほよそ一代の教について、この界のうちにして入聖得果するを聖道門と名づく、難行道といへり。この門のなかについて、大・小、漸・頓、一乗・二乗・三乗、権・実、顕・密、竪出・竪超あり。すなはちこれ自力、利他教化地、方便権門の道路なり。
安養浄刹にして入聖証果するを浄土門と名づく、易行道といへり。この門のなかについて、横出・横超、仮・真、漸・頓、助正・雑行、雑修・専修あるなり。
正とは五種の正行なり。助とは名号を除きて以外の五種これなり。雑行とは、正助を除きて以外をことごとく雑行と名づく。これすなはち横出・漸教、定散・三福、三輩・九品、自力仮門なり。
横超とは、本願を憶念して自力の心を離る、これを横超他力と名づくるなり。これすなはち専のなかの専、頓のなかの頓、真のなかの真、乗のなかの一乗なり。これすなはち真宗なり。すでに真実行のなかに顕しをはんぬ。
http://wikidharma.org/4b936885c5865
聖道・浄土の教について、二教あり。
一には大乗の教、 二には小乗の教なり。
大乗教について、二教あり。
一には頓教、 二には漸教なり。
頓教について、また二教・二超あり。
二教とは、
一には難行聖道の実教なり。いはゆる仏心・真言・法華・華厳等の教なり。
二には易行浄土本願真実の教、『大無量寿経』等なり。
二超とは、
一には竪超 即身是仏・即身成仏等の証果なり。
二には横超 選択本願・真実報土・即得往生なり。
漸教について、また二教・二出あり。
二教とは、
一には難行道聖道権教、法相等、歴劫修行の教なり。
二には易行道浄土の要門、『無量寿仏観経』の意、定散・三福・九品の教なり。
二出とは、
一には竪出 聖道、歴劫修行の証なり。
二には横出 浄土、胎宮・辺地・懈慢の往生なり。
http://wikidharma.org/4b93a35c8a81a
\心 竪 横
教\
出 漸教\聖道門 漸教\浄土門
超 頓教\聖道門 頓教\浄土門(親鸞)☆
三節 善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや。
【訳】 善人ですら往生をとげられるのだから、まして悪人が往生できないはずがありません。
「丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。私がきたのは、義人を招くためではなく、罪人を招くためである」(「マルコ伝」二章十七節)
PHP文庫より
概要
影響
中国
- 前述のとおり、菩提流支が漢訳する。
- 菩提流支と交友のあった曇鸞が、この『無量寿経優婆提舎願生偈』(『浄土論』・『往生論』)を再注釈し、『無量寿経優婆提舎願生偈註』(『往生論註』・『浄土論註』)を撰述する。☆
日本
脚注
参考文献
- 勧学寮 編 『浄土三部経と七祖の教え』 本願寺出版社、2008年。ISBN 978-4-89416-792-6。
- 石田瑞麿 『親鸞思想と七高僧』 大蔵出版、2001年、新装版。ISBN 4-8043-3057-7。
- 黒田覚忍 『はじめて学ぶ七高僧-親鸞聖人と七高僧の教え』 本願寺出版社、2004年。ISBN 4-89416-238-5。
関連項目
外部リンク
内容
科文
- 「総讃」………「帰命無量寿如来 南無不可思議光」
- 「依経段」
- 「依釈段」
関連項目
- 勤行 (浄土真宗本願寺派)
- 勤行 (真宗大谷派)
- つボイノリオ-楽曲「本願寺ぶるーす」の歌詞に取り入れている。
- 山本正之-楽曲「おきょードドンパ」の歌詞に取り入れている。
外部リンク
- 正信偈の教え 東本願寺

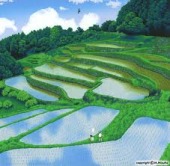 | ◇白骨の章 葬儀や中陰の法事などでしばしば拝読される「白骨の章」は、無常観をそそる御文章としてよく知られています。今回は、この「白骨の章」について講じていただきました。『和漢朗詠集(わかんろうえいしゅう)』や『無常講式』など、この御文章が成り立った背景にふれるとともに、「はやく後生の一大事を心にかけて、阿弥陀仏をふかくたのみまゐらせて、念仏申すべきものなり」とお示しくださった蓮如上人のおこころを、しっかりと味わわせていただきましょう。 |
(1)これを機会に正しい浄土真宗の葬儀について学びたいものです。
(2)日頃から御文章に親しむために、すすんで拝読するようにしましょう。
それ、人間の浮生(ふしょう)なる相をつらつら観ずるに、おほよそはかなきものはこの世の始中終、
まぼろしのごとくなる一期(いちご)なり。さればいまだ万歳(まんざい)の人身(にんじん)をうけたりといふことをきかず、
一生過ぎやすし。いまにいたりてたれか百年の形体(ぎょうたい)をたもつべきや。
われや先、人や先、今日ともしらず、明日ともしらず、おくれさきだつ人はもとのしづくすゑの露よりもしげしといへり。
されば朝(あした)は紅顔ありて、夕(ゆうべ)には白骨となる身なり。
すでに無常の風きたぬれば、すなはちふたつのまなこたちまちに閉ち、ひとつの息ながくたえぬれば、
紅顔(こうがん)むなしく変じて桃李のよそほひを失ひぬるときは六親眷属(ろくしんけんぞく)あつまりてなげきかなしめども、
さらにその甲斐あるべからず。さしてもあるべきことならねばとて、
野外におくりて夜半(よわ)の煙(けぶり)となしはてぬれば、ただ白骨のみぞのこれり。あはれといふもなかなかおろなり。
されば人間のはかなきことは老少不定のさかひなれば、たれの人もはやく後生の一大事を心にかて、
阿弥陀仏をふかくたのみまゐらせて、念仏申すべきものなり。
あなかしこ、あなかしこ。
【意 訳】
さて、人間の定まりない有様をよくよく考えてみますと、およそはかないものとは、
この世の始めから終わりまで幻のような一生涯であります。
だから、人が一万年生きたということを聞いたことがありません。
一生は過ぎやすいものです。末世の今では、いったい誰が百年間身体を保つことができましょうか。
私が先か、人が先か、今日かもしれず、明日かもしれず、おくれたり、先立ったり、人の別れに絶え間がないのは、
草木の根本にかかる雫(しずく)よりも、葉先にやどる露よりも数が多いと、いわれています。
だから、朝には血気盛んな顔色であっても、夕方には白骨となってしまう身であります。
現に無常の風が吹いて、二つの眼がたちまち閉じ、一つの息が永久に途切れてしまえば、
血色のよい顔も色を失って、桃や李(すもも)のような美しいすがたをなくしてしまうのです。
その時に、家族・親族が集まって嘆き悲しんでも、もはや何の甲斐もありません。
そのままにしておけないので、野辺の送りをし火葬すれば、夜半の煙となってしまい、ただ白骨が残るだけです。
あわれという言葉だけではいい表し尽くすことができません。
人間のはかないことは、その寿命が老少定まりのない境界なのですから、
どのような人も早く後生の一大事を心にかけて、阿弥陀仏を深くたのみにして、念仏するのがよいでしょう。
- あなかしこ、あなかしこ。
- あなかしこ:
- [連語]《感動詞「あな」+形容詞「かしこし」の語幹》
- 1 恐れ多く存じます、の意で、手紙文の終わりに用いて相手に敬意を表す語。多く女性が用いる。
- 2 ああ、恐れ多い。
- 「―とて箱に入れ給ひて」〈〉
- 3 呼びかけの語。恐れ入りますが。
- 「―、このわたりに若紫やさぶらふ」〈〉
- 4 (あとに禁止の語を伴って副詞的に用いて)決して。ゆめゆめ。
- 「―、道にて斬られたりとは申すべからず」〈・一二〉
- [補説]「穴賢」と当てて書くこともある。







