NAMs出版プロジェクト: ヨーゼフ・シュンペーター - Wikipedia
http://nam-students.blogspot.jp/2016/11/blog-post_28.html
ケインズ=カレツキ往復書簡 Keynes ,Kalecki Correspondence 1937
http://nam-students.blogspot.jp/2015/12/keynes-kalecki-correspondence-1937.html
http://nam-students.blogspot.jp/2015/12/keynes-kalecki-correspondence-1937.html
NAMs出版プロジェクト: ハロッド=ケインズ往復書簡1938
http://nam-students.blogspot.jp/2015/12/1938.html(ケインズはティンバーゲンに批判的だった)
NAMs出版プロジェクト: カレツキの分配論(支出→生産→分配)1939 ○
http://nam-students.blogspot.jp/2016/12/blog-post_5.html
カレツキ:「投資と資本家消費が利潤と国民所得を決定する」という命題
http://nam-students.blogspot.jp/2012/01/blog-post_17.html
循環を見据えた動学化でないと意味がない。例えば季節毎なら最低4期のデータがいることになるにしても。カレツキはここでも重要。カレツキ自身はケインズを立てているがケインズにないものがある。「長期的」には「死んでいる」のではなく復活するのだ。戦争がかき消した部分もあるがカレツキには一貫した哲学がある。合成循環のアイデアはシュンペーターよりもティンベルゲンの方が早いのかもしれない。どちらにせよ両者にカレツキは影響を与えている。
投資と投資意志の差異はソローに繋がる。さらにラムゼーの仕事を総括する。
Jan Tinbergen - Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Tinbergen
___
econometrica 1935年7月 Tinbergen ティンバーゲン 展望
Annual Survey: Suggestions on Quantitative Business Cycle Theory ...
J. Tinbergen. Econometrica, Vol. 3, No. 3. (Jul., 1935), pp. 241-308.
http://repub.eur.nl/pub/9964/1935Econometrica.pdf
15,16
関連:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cobweb_modelNicholas Kaldor, "A Classificatory Note on the Determination of Equilibrium", Review of Economic Studies, vol I (February 1934), 122-36. (See especially pages 133-135.)
関連:
計量経済学 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/計量経済学ラグナル・フリッシュ - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%83%AB%
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%83%AB%
フリッシュは経済学の分野においていくつかの重要な発展に貢献し、計量経済学やマクロ経済学などの新語を創出した。フリッシュが1926年に発表した消費者理論に関する論文では新ワルラス理論の構築に貢献し、1965年には生産理論を定式化した。計量経済学の分野では、1927年には時系列分析、1934年には線形回帰分析に関する研究を行った。また、フリッシュが1933年に研究したインパルス伝播の景気循環理論は、現代の新古典派経済学の景気循環理論の原則の1つとなった。
フリッシュは計量経済学のモデルを政府の経済企画部門や経済会計部門に紹介する役割を果たした。フリッシュは計量経済学会の創設者の1人であり、20年以上に渡って計量経済学会誌の編集者としても活躍した。
- Frisch, Ragnar (1926). "Kvantitativ formulering av den teoretiske økonomikks lover [Quantitative formulation of the laws of economic theory]". Statsøkonomisk Tidsskrift. 40: 299–334.
- Frisch, Ragnar (1926). "Sur un problème d'économie pure [On a problem in pure economics]". Norsk Matematisk Forenings Skrifter, Oslo. 1 (16): 1–40.
- Frisch, Ragnar (1927). "Sammenhengen mellem primærinvestering og reinvestering [The relationship between primary investment and reinvestment]". Statsøkonomisk Tidsskrift. 41: 117–152.
- Frisch, Ragnar (1929). "Correlation and scatter in statistical variables". Nordic Statistical Journal. 1: 36–102.
- Frisch, Ragnar (1929). "Statikk og dynamikk i den økonomiske teori [Statics and dynamics in economic theory]". Nationaløkonomisk Tidsskrift. 67: 321–379.
- Frisch, Ragnar (1933). "Propagation problems and impulse problems in dynamic economics". Economic Essays in Honour of Gustav Cassel: 171–205.
There is a bibliography of Frisch's writings up to 1960 in
- Arrow, Kenneth J. (1960). "The Work of Ragnar Frisch, Econometrician". Econometrica. 28 (2): 175–192. JSTOR 1907716.
and there is a collection of selected essays
- Bjerkholt, Olav, ed. (1995). Foundations of Modern Econometrics: The Selected Essays of Ragnar Frisch. 2 volumes. Aldershot, UK: Edward Elgar.
- 1969年 ヤン・ティンベルヘンとともに世界最初のノーベル経済学賞を受賞した。
ティンバーゲン:
べてのものを表現しょうとするなら、これがおくれのいりこむやり方である。すなわち、¨=日嗜‐・H(・‐一)または、ど=日【CI(日キこと含10これがティンバーゲン教授のおかげで経済学者に周知のものとなり、かれの造船業の場合に発揮されるであろう技術を応用するためにわれわれの必要とする混合定差微分方程式である。 一つの指数に復素指数を代置することによつて、容易に同期的過程の可能なことが示される。カレッキー氏は、米国と独逸の資料を使つて、 一〇ヵ年の周期を示す一つの重要な構成部分に、ほとんど困難を感じることなしに、到達した。この構成部分は、この模型によれば、たしかに、始発的な衝撃――たとぇば、ァダムとイヴが楽園に住んでいた時代に、リンゴ栽培業におこったある事件――を必要とするが、その後永久に進行しつづける景気循環を説明する。そしてこれはつぎのような理由からそうなのである。すなわち、『資本家の支出と考えられる投資は好況の源泉である。……しかし同時に、投資は資本設備への追カ11であり、全く生れながらにこの設備の古い世代と競争する』(゛ヾ一ヽ筐ミゃSsヽミむミ03誌第四巻九一(頁)。読者がこれを『逆説』だと考える場合、カレッキー氏は、 かれ以前に自身のつくったぁりょぅはずのない結果に当面したはなはだ多くの経済学者になぐさめを与えた、っどのような回答、すなわち『逆説的なのは理論ではなくて、その対象――資本主義経済――なのだ』といぅ回答を用意している。(1)この理論はくりかたし発表されてきた。最初の説明はポーランド語でのものであり、従つて著者にはしられていない。この英語での説明は一九二五年六月号のbヽoヽ゛S一ヽヽヽこ8誌上で発表され(それにたいする註釈は、なかんずく、価格、賃銀がどのように暗黙的に模型にはいりこむかを示す筈であるが、bヽミミミヽ」8誌一九二六年一〇月号中にある)、もう一つはヽこ0ヽ一cミ詢ヽsヽもヽ゛ゃいミヽ」0誌一九二七年二月号中に発表された。後者の中では、この理論はケインズ氏の理論と対比されている。本問題の細目にはここではたちいるわけにいかない。本書ではただ基本的な観念と含まれている原理についての註釈が示されるだけである。(2)ティンバーゲン教授の造船業循環の模型の中にも、もちろんそれらはあるが、ただ合蓄的にあるにすぎない。これが不適当であり、カレツキー氏の意味での投資は、単独で、他の要因がなければ、どんな波動も、恐慌も、引起さないということは前章A節0で示された。だがカレツキー氏流の議論には非常にしばしば出くわすし、逆説の尽きることのない源泉でもあるので、 一見融和しがたい原理上のちがいとも考えられるものの原因や性質をハッキリさせることは無駄ではないだろう。まず最初に、現にあるようなちがいは、考えられるだろうように、貯蓄の定義のちがいか、またはわれわれの実物投資とよんでいるものと貯蓄との関係についての意見のちがいからくるものではない。反対に、第二章での貯蓄についてのわれわれの議論の中では、われわれは、カレツキー氏が貯蓄がたちまち新設備への注文をもたらすとするのと全く同じように、貯蓄はたちまち設備に転化されるものと仮定した――本書中でのその他のどの個所でも、このようには考えなかつたのだが。カレツキー氏が二つの段階を区別することなく、 一つにまとめており、このことがかれが到達した結論となんらかの関係をむすんでいることは、まもなくわかるように、事実である。しかし根本的には、この点になんのちがいもない。ちがいは、われわれが他のあらゆる点では定常的な過程の場合について論じているということである。もしわれわれが貯蓄と投資そのものが変動をもたらすかどうかをみいだすために、こうしたのだということをもう一度いうなら、カレツキー氏の模型をはたらかせるためには、どのみち、最初の攪乱はかくことをえな
景気循環の動態学
叢書名 現代経済学名著選集
著者名等 J.ティンベルゲン/著
著者名等 飯塚仁之助/訳
出版者 文雅堂書店
出版年 1959.8
大きさ等 22cm 437p
NDC分類 337.9
書誌番号 3-0190453144
(オランダ語版は1942年なので第二次大戦は考察対象外。)
国立国会図書館デジタルコレクション - 景気循環の動態学
・ 目次
・ 著者近影
・ 訳者序文
・ はしがき ジェ・ジェ・ポラーク
・ 日本版への序文 ティンペルゲン、ポラーク
・ 第一篇 槪說/p1
・ 第一章 序説 動向の型/p3
・ 第二章 長期間的な発達/p29
・ 第三章 構造の中断と突然の変化/p46
・ 第四章 循環的な動向/p67
・ 第五章 季節変動/p81
・ 第六章 無作為的な動向/p85
・ 第七章 各国別の相違/p91
・ 第八章 個別的な市場にみる変動/p100
・ 第二節 經濟変動の說明/p111
・ 第九章 経済静学と経済動学/p113
・ 第十章 長期間的な発達の過程/p129
・ 第十一章 戦争とインフレーションの期間/p160
・ 第十二章 長期波動/p182
・ 第十三章 景気循環変動/p187○
・ 第十四章 個別の市場における循環的な動向/p277
・ 第十五章 外生的な動向/p293
・ 第十六章 理論的な追記/p300
・ 第三篇 景気循環政策/p311
・ 第十七章 序説/p313
・ 第十八章 趨勢政策と景気循環政策の目的/p324
・ 第十九章 間接的な政策 そのI 租税政策/p339
・ 第二十章 間接的な政策 そのII それ以外の形態/p355
・ 第二十一章 直接的政策 そのI 支出政策/p379
・ 第二十二章 直接的な政策 そのII それ以外の形態/p407
・ 第二十三章 摘要―敵限政策の選択/p416
・ 索引/p437
一層複雑した関係の相対的に単純な例は(これは偶然にも規則性に之しい型の波動を生ずることがないもので
ある)、これをカレツキの学説からひきだすことができるであろう。この例の目的は、ーつの循環的な動向を手
にするために、投機的な所得現象を導人することがとくに必要ではないということを示すことでもある。
カレツキの学説は、われわれの例三とはちがって、彼が、支出は所得水準には依存しないで、資本に対する所
得の比率に依存すると仮定したというふうに解釈することができよう。彼はこの仮説をつぎの考慮に立脚させる。
(い) 投資のための支出は、これが消費者の所得水準を決定するから、それ以外の支出全体を決定するであろう。
(ろ) 投資は、絶対的な利潤の水準によるよりも、むしろ利潤率、すなはわち資本に対する利潤の割合によって決
定される。
(は) 利潤にみる変動は、国民所得にみる変動と平行している(利潤は国民所得のうちもっとも変動的な部分を
形成している)から、ーつの接近としては、投資は国民所得全体と資本との比率によって決定されるのと結論
してもさしつかえないであろう。
240頁
Amazon | Essays in the Theory of Economic Fluctuations [Kindle edition] by M. Kalecki | Economics | Kindleストア
https://www.amazon.co.jp/Essays-Theory-Economic-Fluctuations-Kalecki-ebook/dp/B00FQDGFM8/
CONTENTS
Part One
1. The Distribution of the National Income
2. Investment and Income
3. Money and Real Wages
Part Two
4. The Principle of Increasing Risk ☆☆☆☆
5. The Long-Term Rate of Interest
○6. A Theory of the Business Cycle (1937)↓
Index
“The Distribution of the National Income,” from Econometrica, April 1938, “The Principle of Increasing Risk,” from Economica, November 1937, and “A Theory of the Business Cycle,” from the Review of Economic Studies, February 1937.
シュンペーター、ケインズも参照される。ハイエクも賞賛される。
____
(ケインズはティンバーゲンに批判的だった)
経済学は論理学、そしてモラル・サイエンス ( 景気 ) - 平井俊顕 (ひらい・としあきToshiaki Hirai)ブログ - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/olympass/49280998.html経済学は論理学、そしてモラル・サイエンス
経済学は論理学の一分野であり、思考の一方法です。……経済学は本質的にモラル・サイエンスであって自然科学ではありません(ハロッド宛書簡、一九三八年七月四日付。JMK. 14, pp. 296-7)。
これは計量経済学の先駆的業績であるヤン・ティンバーゲン(Tinbergen[1939])をめぐり、ケインズとハロッドのあいだで交わされた書簡の一節である。ティンバーゲンに対するケインズの評価は徹頭徹尾、厳しいものであった。その際、ケインズは自らの経済学に対するスタンスを次の二点におく。一つは、経済学を論理学の一分野とみなすスタンスである。経済学はモデルの改善によって進歩するが、可変的な関数に実際の数値を当てはめるべきではない。統計的研究の目的は、モデルのレリヴァンス・有効性をテストすることにある。この背後には『確率論』(JMK. 2)で展開した理論が確実に存在する。だがケインズの経済学が、計量経済学および一般均衡論の発展と連携してマクロ経済学の主流となったのは皮肉である。もう一つは、経済学をモラル・サイエンスと特徴づけるスタンスである。これは、内省と価値判断を用い、動機、期待、心理的不確実性を扱う科学と定義されている。「新しい古典派」のような「形式主義」と真っ向から対立する方法論である。
コーヒーの本からコーセーの実がとれるまでには七年かかる。それゅぇ、価格の状況が有利であり、栽培の増加を生ずるとすれば、生産の増加が市場にぁらわれるまでには、少くとも七年かかるでぁろう。追加的な栽培に着手するまでには、 一定期間が経過するから、通例はやゃ一層長期間を必要とするでぁろう。それゆえ、ゎれわれはこの期間のほぼ二倍の期間をもった変動を予想することができるし、事実またこの変動が発生するのでぁる。これら0変動は、何等かぁる反作用が市場にぁらわれるまでに七年間高い価格水準が持続するにしたがって、とくにはっきりとしたものになるでぁろう。この七年間には、相当多量の栽培がおこなわれるでぁろう。
豚の市場にぉけるとおなじように、攪乱が発生する。このあいだでは、コーヒーの本の収穫の相違がとくに述べられるべきでぁる。多収穫がみられるときには、そこにはこれが価格ひきさげをめざす傾向がみられ、循環の正常進路を中断することがある。
280:
ティンバーゲンによって発見された蜘蛛の巣の定理の例に挙げられるのが豚の市場とコーヒー市場。
以下は『計量経済学』1961(1951)より
___
ヤン・ティンバーゲン - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/ヤン・ティンバーゲン
ヤン・ティンバーゲン(Jan Tinbergen、1903年4月12日 - 1994年6月9日)は、オランダのハーグ出身の経済学者である。計量経済学の誕生期1930年代からすでに計量分析に関わってきた。
略歴
- 1903年 ハーグで生まれる。
- ハーグの高校に通う。
- 1922年 ライデン大学で物理学を学ぶ(~1926年)。
- 1929年 物理学と経済学の極大・極小問題に関する論文で博士号を取得。
- 1929年 オランダ中央統計局に勤務し、景気循環研究に入る。
- 1931年 アムステルダム大学の統計学の非常勤講師となる。
- 1933年 オランダ経済大学(ネーデルランド・スクール・オブ・エコノミックス、現エラスムス・ロッテルダム大学)の非常勤講師となる。
- 1936年 オランダのマクロ経済モデルを作る。
- 2年間、ジュネーブの国際連盟に勤務(中断期間)。
- 1945年 オランダ中央統計局を辞め、新設されたオランダ経済計画局の長官を務める(~1955年)。
- 1955年 オランダ経済大学(現エラスムス・ロッテルダム大学)の開発計画学の教授となり、同大学付設のオランダ経済研究所の所長を兼務した。
- 1966年 - 1975年 国連開発計画委員会の委員長を務めた(別の資料によると1965年~1972年)。
- 1967年 エラスムス賞受賞。
- 1969年 計量経済学への貢献とのその政策分野への応用等の功績により、第1回ノーベル経済学賞を授与された。
- 1970年 国連開発計画委員会が発表した『Preparation of Guidelines and Proposals for the Second United Nations Development Decade(第二次国連開発10年のためのガイドラインと提案)』は1970年代の開発戦略の方向付けに大きな影響を及ぼした。この報告は『ティンバーゲン報告』とも呼ばれる。
- 1973年 ライデン大学にある国際協力の教授となる。
- 1975年 退官。
- 1994年 ハーグで死去(91歳)。
業績
- ティンバーゲンは国家規模のマクロ経済学のモデルを初めて開拓した人物であり、最初にオランダの経済モデルを構築し、その後アメリカ合衆国とイギリスに対して経済モデルを適用した。ティンバーゲンはエラスムス・ロッテルダム大学に計量経済学研究所を設立した。
- ティンバーゲンの主要研究領域は、大きく3つの分野に分けられる。
1つは、ミハウ・カレツキ・ラグナル・フリッシュ等の巨視的景気循環モデルとアーヴィング・フィッシャー・ラグナル・フリッシュなどが考案した多元相関分析を利用したものであり、後の展開の源流となった景気循環のマクロ計量経済的モデルを構築した。『An Econometric Approach to Business Cycle Problems(景気循環の諸問題に対する計量経済学的接近)』(1937年)、『Statistical Testing of Business Cycle Theories(景気循環理論の統計的検証)』(1939年)等が主要文献である。同時期にユリシーズ・リッツらとともにくもの巣理論を発表し、経済動学理論の幕開け的役割を果たした。
- 2つ目は経済計画の作成に計量経済学的手法を適用して、短期政策モデル(オランダ・モデル)を作成したことである。主要文献として『Centralizatoin and Decentralization in Economic Policy』(1954年)、『On the Theory of Economic Policy』(1952年)、『Economic Policy: Principles and Design』(1956年)等がある。
- 3つ目は、長期経済計画、発展途上国の開発、経済体制の問題の研究である。
- ティンバーゲンの業績は後にローレンス・クラインによって体系化され、クラインのノーベル経済学賞の受賞にも貢献した。
くもの巣理論
詳細は「:en:Cobweb model」を参照
- pt, qtd, qts をそれぞれある財の t 期の価格、需要量、供給量とし、qtd = D (pt) および qts = S (pt-1) と表されるとする。今期の供給量は前期の価格に応じて固定されているため、今期の価格は qtd をこの固定的な供給量に一致させるように決定される。この価格の変動経路を需要曲線が通常の勾配を持つとするならば、「くもの巣」状になる。
- また、この体系の定常解 p* は、|D’ (p*)| > |S’ (p*)| を満たせば安定であることも明らかである。一般に、農産物の収穫量は、前期の価格水準に応じて定まる作付け規模等に支配されるため、くもの巣理論は、しばしば農産物価格の変動を説明するために利用される。
ティンバーゲンの定理
- N個の独立した政策目標を同時に達成するためにはN個の独立な政策手段が必要である、という定理[1][2]。たとえば、固定相場制度(為替レートの固定)と景気安定化政策(インフレやGDPギャップの調節)という2つの目標を達成するには、金融政策と財政政策のような2つの独立した政策手段が必要となる。一方で、変動相場制度に移行した場合、為替レートを固定するという政策目標がなくなって景気安定化という一つの政策目標だけとなるので、金融政策だけで達成が可能になる。また、景気安定化に金融政策が用いられる場合、バブル回避などの資産価格問題には金融政策を使うことが出来ないということになり、別の政策手段が必要となる。
- なお、どの目標にどの手段を当てはめるべきかについては、その目標達成のために相対的に最も有効な手段を割り当てるべきであるというマンデルの定理などがある[1][2]。
その他
- 弟であるニコ・ティンバーゲン(ニコラス・ティンバーゲン)とルーク・ティンバーゲンは著名な鳥類学者であり、ニコ・ティンバーゲンは1973年にノーベル生理学・医学賞を受賞している。
脚注
- ^ a b 為替政策は構造問題を解決できない - 求められるポリシーミックスの発想 -RIETI 2005年12月7日
- ^ a b 最終回 経済学を勉強しよう!ワイアードビジョン アーカイブ 2008年5月7日
関連項目
外部リンク
- O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., "ヤン・ティンバーゲン", MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews.
- TINBERGEN, Jan in: Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland
- Jan Tinbergen (1903-1994) Koninklijke Bibliotheek
- Jan Tinbergen
- Jan Tinbergen College (Dutch website)
- IDEAS/RePEc
- Profile at The International Institute of Social Studies (ISS)




























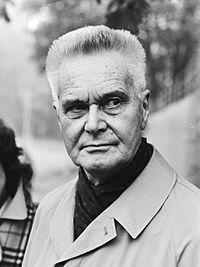

1 Comments:
経済学には、「ティンバーゲンの定理」といわれている命題があります。内容は「政策当局がN個の独立した目標を同時に達成しようとするときは、N個の独立した政策手段がなければならない」というものです。
岩村充 中央銀行…
コメントを投稿
<< Home