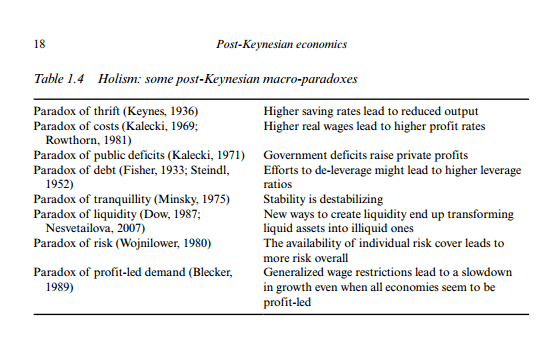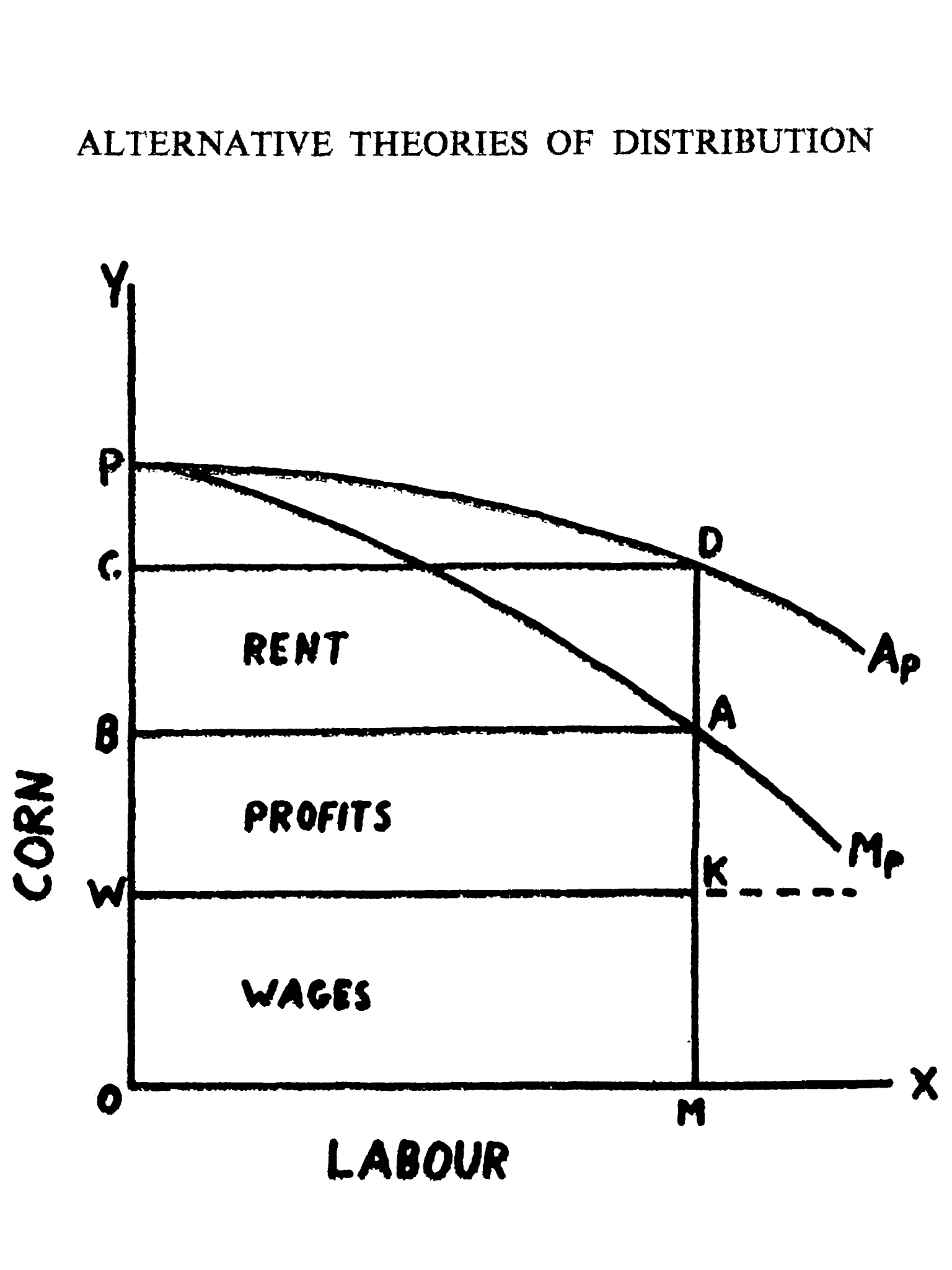マーク・ラヴォアMarc Lavoie
— luminous woman (@_luminous_woman) December 11, 2020
Curriculum Reform & Rethinking Economics 2015https://t.co/5rb8j9Fr5b
10:02
Sectoral financial balances pic.twitter.com/kGsbvTEcRM
L:
well the sectoral balanced approach starts from the national identities.
and we just rearrange it in a way that well for instance we we look at what is the balance of the private sector.
what is the financial balance of the government sector which is then the government surplus or government deficit.
and what is the external balance so that's a good radio equipment once we put into the current account balance.
and we know that the sum of those three things has to be equal to zero.
Q:
but at any given time any one of those sectors can run a deficit or a surplus product a--they another sector is prepared to accommodate it.
L:
exactly so if you make some predictions regarding the about the financial balance of the private sector.
and you already know what's the situation of the order likely situation of the external sector.
then you have a good idea of what's going to be the deficit or the surplus of the government.
and then if your if your predictions about these various things don't add up then it means one of your assumptions is wrong.
Q:
…there was little sensitivity to the huge buildup in private sector debt which would have been picked up had there been more focused on this sectoral balanced approach well.
L:
yes you you know I had many discussions about this with Wynne Godley.
so he was more optimistic than I was.
I must say on the usefulness of these balances.
I mean it's highly useful as I said to identify whether or not.
you're making a very bad forecast with respect to one of the balances .
or one of the assumptions about economic growth and so on.
…
L:
Well and it has been used by companies like Goldman Sachs and it is now generalized I mean it's not something that when Godley himself invented because it's a national account identity. but he's certainly the the person who emphasized it most. and who induced other people to discover it and to use it. and as I said now in many financial offices they are using this to better understand what's going on.
L:
セクター別のバランスの取れたアプローチは、国家のアイデンティティから始まります。
例えば、民間部門のバランスはどうなっているのか、政府部門の財政収支はどうなっているのか、そして政府の黒字か赤字か、というように。
政府部門の財政収支はどうなっているのか、これは政府の黒字、赤字です。
政府の財政収支は、政府の黒字か政府の赤字です。そして、対外収支は何ですか。
そして、この3つの合計がゼロになることがわかっています。
Q:
しかし、いつでも、これらの部門のいずれかが赤字や黒字を出すことができますが、他の部門がそれに対応する準備をしている場合はどうなるのでしょうか?
L:
あなたが民間部門の財政収支についていくつかの予測を立てれば、まさにそうです。
民間部門の財政収支についていくつかの予測を立てれば
そうすると、あなたは、政府の赤字や黒字がどうなるかについて、良い考えを持っていることになります。
そして、これらの様々なことについての予測が合わない場合は、あなたの仮定の一つが間違っているということになります。
Q:…民間部門の債務の膨大な蓄積に対しては、ほとんど感度がありませんでした。
L:
そうですね......このことについては何度も議論しました。
彼は私よりも楽観的でした
私はこの天秤の有用性について言わなければなりません。
つまり、私が言ったように、この天秤は非常に有用なのです。
天秤の一つに関して、非常に悪い予測をしているかどうかを見極めるのに非常に役立ちます。
または経済成長などの前提条件の一つに関して、非常に悪い予測をしているかどうかを特定するのに非常に役立ちます。
…
L:
ゴールドマン・サックスのような企業で使われてきましたが 今では一般化しています つまり ゴッド・リー自身が考案したものではありません 国家口座のアイデンティティですから しかし 彼が最も強調した人物であり 他の人々にそれを発見させ 使うように誘導したのは間違いありません そして今 私が言ったように 多くの金融機関では 何が起こっているかをよりよく理解するために これを使っています。
参考:
マーク・ラヴォア 講演
マーク・ラヴォア インタビュー
ラヴォア、発表資料
https://www.slideshare.net/mobile/UmkcEconomists/2014-stock-flow-consistent-modeling-workshop
参考:
元ネタは、マルク・ラヴォワMarc Lavoir の 2003年の論文「内生的信用貨幣論入門」 “A Primer on Endogenous Credit-Money” です。 これは『現代の貨幣理論』(本当は『現代貨幣理論』 と訳す方がいいんだけれど、それだとMMTと 区別がつかなくなっちゃうから。。。。) Modern Theories of Money, 2003 ルイ=フィリップ・ロションおよびセルジオ・ロッシ編 Louis=Philippe Rochon and Sergio Rossi ed 所載の論文です。 マルク・ラヴォワという人については このブログでも過去に何回か、名前だけは触れたことが あったように思うけれど、ウィン・ゴドリー Wynne Godley のMonetary Economics の共著者で 学者になりたての全くの若手のころから ゴドリーの独創性と革新性にいち早く目をつけて 永らくStock=Flow Consistent Approach (ラヴォワ自身は どちらかというと、Coherent Stock=Flow Approachというような 表現の方を好んでいたようだったけれど)の 開発・普及の協力者として、いわゆる「第二バイオリン」的な 立場でかかわってきた。ただし、 ラヴォワ自身はカナダのケベックの出身のフランス系カナダ人で ケベックでは公用語としてフランス語がつかわれていたので 本人もフランス語は使える。実際、フランス語の論文もある。 このことはGodley に早くから理解を示していたことと 無関係ではない。というのはゴドリー 自身 フランスやイタリアのケインズ派理論(CT)の影響を 大きく受けており、CT派に対する理解の違いが ゴドリーを適切に評価できるか否かの違いに つながっていた面があるからである。現に ラヴォワ自身、Foundations of Post-Keynesian Economic Analysis, Introduction to Post Keynesian Economics、 Post-Kenesian Economics: New Foundations と、まあ、 3冊にも及ぶ「ポスト・ケインジアン」を冠した 単著を出版しているにもかかわらず、永らく 「サーキュレーショニスト」として、 PK派内部からは疎外されていたもようで、 Modern Theories of Money の編集に際しては、 ラヴォワより自分のことを PK派とかCT派とかの区別する部には 載せないでほしい、と編集者に要望が出されたとの話がある。…
https://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Lavoie
Marc Lavoie (born 1954)[1] is a Canadian professor in economics at the University of Ottawa and a former Olympic fencing athlete.
…
ミハウ・カレツキ (Michal Kalecki):マクロ経済学の知られざる英雄
http://nam-students.blogspot.jp/2015/10/michal-kalecki.html
ラヴォアのMMT評
- Lavoie、Marc、ネオチャタリズムの通貨と財政の関連性(PDF)
- Lavoie, Marc, The monetary and fiscal nexus of neo-chartalism (PDF)
邦訳された入門2008^2004より包括的な以下2014の邦訳が待たれる
マルク ラヴォア (著), Marc Lavoie (原著), 宇仁 宏幸 (翻訳), 大野 隆 (翻訳)
L'économie postkeynésienne 2004
著者 マルク・ラヴォア 著
宇仁 宏幸 訳
大野 隆 訳
ジャンル テキスト
経済・経営 > 経済学
教養・共通科目 > 教養科目
出版年月日 2008/07/01
ISBN 9784779502675
判型・ページ数 4-6・222ページ
定価 本体2,400円+税
http://www.nakanishiya.co.jp/book/b134567.html
日本語版への序文
はじめに
I ポストケインズ派という異端
1 誰がポストケインズ派なのか
2 異端派経済学の特徴
3 ポストケインズ派経済学の本質的特徴
4 ポストケインズ派理論のさまざまな潮流
II 異端派ミクロ経済学
1 消費選択理論
2 寡占的な市場と企業の諸目的
3 費用曲線の形状
4 価格設定
5 費用マージンの決定要因
6 マクロ経済理論にとっての含意
III マクロ経済的貨幣サーキット
1 ポストケインズ派の貨幣分析のおもな特徴
2 民間銀行と中央銀行の関係
3 銀行と企業の関係
4 貨幣的経済の体系的見方
IV 短期:有効需要と労働市場
1 有効需要とその構成
2 カレツキ・モデル
3 カレツキ・モデルのさらなる展開
V 長期:古い成長モデルと新しい成長モデル
1 古いポストケインズ派成長モデル
2 新しいカレツキ・モデル
3 カレツキ・モデルの拡張と批判
VI おわりに
参考文献
訳者あとがき
索引
マルク ラヴォア (著), Marc Lavoie (原著), 宇仁 宏幸 (翻訳), 大野 隆 (翻訳)
5つ星のうち 5.0 2件のカスタマーレビュー
その他()の形式およびエディションを表示する
市場への介入と完全雇用政策を主張し、自由市場政策と新古典派経済学への体系的な代替案を提示するポストケインズ派。従来難解で知られたその理論を初学者向けに平易に解説し、その政策的含意を明らかにする入門書。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
ラヴォア,マルク
オタワ大学社会科学学部経済学科教授。カールトン大学卒業。パリ第1大学で修士号・博士号取得
宇仁/宏幸
京都大学大学院経済学研究科教授
大野/隆
立命館大学経済学部准教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
登録情報
単行本: 205ページ
出版社: ナカニシヤ出版 (2008/07)
言語: 日本語
ISBN-10: 4779502675
ISBN-13: 978-4779502675
発売日: 2008/07
5つ星のうち5.0ポストケインズ派経済学における中心的論客の案内書―新自由主義に対抗する新しい代替理論の提起
2017年5月16日
形式: 単行本|Amazonで購入
内外のポストケインズ派経済学の入門書をすべてフォローしているわけではない私なので、あくまで個人の主観だが、同派の撮要的書物として、私は本書とA.S.アイクナー編『ポスト・ケインズ派経済学入門』(緒方俊雄他訳,日本経済評論社,2003年)を挙げたい。ただ、アイクナーNY州立大学教授(刊行時)が編著した同書は、アイクナー教授以外の学者も執筆している関係から、教科書的であり、そういった意味で、私はポストケインズ派経済学の出発点としては、マルク・ラヴォア教授(オタワ大学,同上)の本書を、まずお薦めしたい。ただし、ラヴォア教授の説明に関しては、鍋島直樹・名古屋大学教授などが「カレツキ派(Kaleckian)に偏重している」旨指摘されているみたいだが(wiki.)、私自身はカレツキ(Michał Kalecki,1899~1970)に親和的であるため、全く違和感がないことを付け加えておきたい。
ここで、カレツキの名が出てきたので、まず「異端派経済学の1つ」(本書p.1)であるポストケインズ派理論の「3つの異なる潮流」(p.27)を通覧してみたい。この3つの潮流とは「ファンダメンタリスト(「ケインズ原理主義」ともいう)」「スラッファ派」及び前記の「カレツキ派」である。それぞれの潮流の特徴についての詳言は避けるけれども、例えば上述のアイクナー教授は、ラヴォア教授によれば「3つのポストケインズ派すべてから影響を受けたことを認めるポストケインズ派経済学者」とされている(p.29)。逆に、ラヴォア教授は「カレツキ派」を自認している(p.33)。それはさておき、本書では、最初に異端派と新古典派の前提条件の違いを大枠で示した後、ラヴォア教授はポストケインズ派経済学の本質的特徴として2点、補助的特徴として5点を挙げている。以下、これらの諸点を見てみよう。
まず、ポストケインズ派経済学の本質的特徴として、「有効需要原理」と「動学的歴史的時間」がある。次に、補助的特徴として、「価格の伸縮性がもつマイナス(不安定化)効果」「貨幣的な生産経済の存在」「根元的な不確実性」「適切で現代的なミクロ経済学」及び「方法と理論の多元的共存(理論化に対する多元的なアプローチ)」がある。これらのポイントの含意するところは、本書を直にあたってもらいたいと思う。そして、こうした諸点を踏まえ、解説が進んでいくわけだが、無論、その論理展開にあたって、ラヴォア教授はマルクスに学んだカレツキのモデルも応用する。実際、教授は「ケインズ経済学の根本的な内容を明らかにするためには、「ケインズよりカレツキ」に学ぶべきである」(p.123)との文言も記している。今、資本主義は新自由主義の旗の下、自由市場主義(市場至上主義)に毒され、規制緩和、民営化、緊縮財政等が持て囃されているが、その「解毒剤=代替理論」としてポストケインズ派経済学がある。
もっと少なく読む
5つ星のうち5.0ポストケインズ派の入門書として最良
2008年8月20日
形式: 単行本
本書はポストケインズ派の経済学を、コンパクトに解説した本です。
本書は、ポストケインズ派の歴史と特徴、その諸潮流の解説、ミクロ、マクロ理論、そして短期、長期の理論に項目を分け、解説しています。多種多様なポストケインズ派を一括りにして解説するわけですから、全体としては共通する部分を、そして部分的に諸潮流間の違いを提示するという形になっています。ただ、カレツキやカレツキ派をベースに、全体が叙述されているような気がします。
また、新古典派理論との対比もはっきりしており、論点がとても分かりやすくなっています。援用される数式が最小限に留められており、参考として必要なものは欄外のコラムにまとめてあるために、取りあえず全体像を把握した初心者にとっては、数式で躓くことなく読み進められるのも大きな特徴です。経済学の入門書で得た新古典派の知識と比べあわせ、数式に惑わされずにスムーズに全体を読むことができるこの構成は、大変画期的です。
なかなか分かりにくく、体系的に全体像の見えなかったポストケインズ派の入門書として、他に比類のないほど適した本です。経済学を学ぶすべての人に読んでもらいたい本です。
13人のお客様がこれが役に立ったと考えています
役に立った
役に立たなかった
|コメント|違反を報告
- 季刊 経済理論 第47巻第4号(2011年1月) 特集◎カレツキ経済学の現代的評価

| 構造変化と資本主義経済の調整 | |
| 著者名等 | ボブ・ローソン/著 ≪再検索≫ |
| 著者名等 | 横川信治/〔ほか〕訳 ≪再検索≫ |
| 出版者 | 学文社 |
| 出版年 | 1994.06 |
| 大きさ等 | 22cm 235p |
| 注記 | 文献:p222~228 |
| NDC分類 | 332.06 |
| 件名 | 資本主義 ≪再検索≫ |
| 目次 | 第1章 需要、実質賃金、経済成長;第2章 不均等発展と利潤率;第3章 雇用の構造 とその進化―脱工業化の理論;第4章 構造変化の簡単な数学;第5章 西ヨーロッパの 失業―コーポラティズムと構造変化;第6章 集権化、雇用、賃金分散;第7章 集権的 交渉、効率賃金、フレキシビリティ |
| ISBN等 | 4-7620-0537-1 |
ポストケインズ派経済学とは何か —主流派経済学と非主流派経済学
The Paradox Of Costs And Other Macro Paradoxes
The paradox of costs, in its static version, says that a decrease in real wages will not raise the profits of firms and will instead lead to a fall in the rate of employment. This was explained by Kalecki in a Polish paper first written in 1939, where he concluded that ‘one of the main features of the capitalist system is the fact that what is to the advantage of a single entrepreneur does not necessarily benefit all entrepreneurs as a class’. Its dynamic version has been proposed by Robert Rowthorn. It says that rising real wages (relative to productivity) can generate higher profit rates. This flies in the face of a microeconomic analysis that would demonstrate that lower profit margins generate lower profit rates. But if higher real wages generate higher aggregate consumption, higher sales, higher rates of capacity utilization and hence higher investment expenditures, profit rates will be driven up.
リカード『経済学および課税の原理』(On the Principles of Political Economy, and Taxation)
http://nam-students.blogspot.jp/2015/04/on-principles-of-political-economy-and_25.html
Alternative Theories of Distribution (Adobe PDF) -piketty.pse.ens.fr/files/Kaldor1955.pdf Author(s): Nicholas Kaldor ... between Ricardo and Keynes
http://piketty.pse.ens.fr/files/Kaldor1955.pdf
- 代替的な分配諸理論
リカード
マルクス
新古典派
ケインズ派
を概観していて秀逸
根井雅弘『入門 経済学の歴史』ちくま新書70頁参照
|。 。
穀| 。 。
|_______。__。
物| 地代総額 | 。平均生産物(穀物産出量/労働投入量)
|__________。
| 利潤総額 | 。
|__________| 。限界生産物(穀物生産量増加分/労働投入量一単位)
| 賃金総額 |
0|__________|_____
労働投入量
Collected Economic Papers of Joan Robinson - Vol. 4 (英語) ハードカバー – 1980/10/14
- 「経済学を学ぶ目的は、経済問題に対する出来合いの対処法を得るためではなく、そのようなものを受け売りして経済を語る者にだまされないようにするためである」
- 「均衡の経済学は、モーラックの如く経済学徒を次から次へと生贄としてきた」
- 「縮尺1/1の地図は要らない(役に立たない)」(現実は複雑なので、単純化したモデルを用いた分析は非現実的で意味がないという批判に対して)
- マークアップ論の起源はカレツキにある。本章では、カレツキの資本主義経済の理論をみて、その中でどのようにミクロ分析を使ったかをみる。
- 非集計フレームワーク:資本主義経済
1)マクロ経済 - カレツキは、経済学にマルクス経済学から入った(これはケインズがマーシャル経済学から入ったことと対照的である)ので、マクロ経済の枠組みは自然と部門分割のモデルになった。カレツキの用いた部門分割は、労働者の消費財部門・資本家の消費財部門・投資財部門であり(それぞれ垂直統合され、一次産品などの原料は外部から)、労働者は貯蓄しないという典型的な古典派的仮定が置かれた。このモデルで特徴的なのは、資本家の支出が利潤を形成することである。「労働者は自らうるものを支出し、資本家は自ら支出するものをうる」のである。
- 2)不完全な競争
不完全な競争の認識
→(1)需要弾力性によってマークアップが決定できる個別の右下がり需要曲線 - →寡占は相互依存関係を生むという問題
→(2)企業の需要曲線の不決定 - →価格設定力を寡占の程度と結びつけ、それを需要曲線の位置として解釈する
「このように、市場の不完全性と所与の寡占の程度に特徴づけられた産業において、企業は、直面する市場の不完全性と寡占の程度という観点から特定化された、個別のwell definedな需要曲線に直面する」(p.146)
=不完全競争における個別需要曲線の傾きに寡占を意味付けて入れて、限界主義(MR=MC)で価格付けを解釈する方法 - * 注5・6にあるように、不完全競争もしくは独占的競争において需要曲線をどのように考えるかには難しい問題があり、チェンバリンの議論は重要である。
- →チェンバリン『独占的競争の理論』(1962)、ハロッド「不完全競争論再考」(1952)、「収穫逓増」(1967)、宮崎義一『近代経済学の史的展開』(1967)を参照
- 企業・価格・投資
不完全競争による価格設定:MR=MC - (注10)マークアップとカレツキ
カレツキ自身は、ホール=ヒッチまで、マークアップという言い方をしていない
「おそらく、彼らによって示された手続きは、価格を固定する実際のプロセスではなく、純利潤を獲得できるかどうか理解するために、[彼らの手続きとは]別の方法を使って固定された価格をチェックするに過ぎないものだろう」
→カレツキは目の子算的な価格設定のルールがあるという考えよりも、独占度を規定している要因を考える道を選んだ - * 『経済変動論集』(1939)でのカレツキは不完全競争論だけなのか?そこには屈折需要曲線のイメージを含んだ寡占の考え方が入り込んでいるという解釈もある
- →金尾敏寛『価格・資金調達と分配理論』日本経済評論社、1997年、第二章参照
独占度の反循環的変動 - 過剰な設備をもち、参入の脅威が下がる不況期には独占度が高まり、原材料費の低下と反対方向に動くことで、粗利潤の分配率が景気循環を通じて安定的になる
- 長期的な独占度上昇傾向
- 「独占度は集中の進展によって長期において疑いなく上昇する傾向がある。産業の多くの分野で寡占的になり、寡占はしばしばカルテルになる」(Kalecki 1938, p.17)
- * 独占度の上昇傾向は、その後、バラン=スウィージー、スタインドル、カウリングなどが停滞要因として利用しているが、カレツキはこの考え方に確信をもっていなかった
- →鍋島直樹「カレツキアンの経済学とカレツキの経済学」(1999)、経済学史学会年報
- 投資決定
- 利潤機会は豊富に存在し、資金制約(危険逓増の原理)が投資量を制約する。
*カレツキについては、『経済変動の理論』と『資本主義経済の動態理論』が主著である。後者にはカレツキのエッセンスのほとんどが含まれている。
- ミクロ分析とマクロ経済
独占度の変化がもたらすマクロ経済への影響について
=独占度の上昇は労働分配率をさげ、総需要を下げる - →独占度の長期的上昇があれば、長期的な停滞が予想される
*カレツキが貨幣賃金の切り下げの持つ効果について特に関心があったことを付け加える - 不完全雇用を是正するための政府の行動は、資本の抵抗にあう(「完全雇用の政治的側面」)
<コメント>
戦前のカレツキの価格理論で重要な点は、寡占と不完全競争の衝突であろう。それはその後にカレツキが展開した寡占価格論との関係(差別化と独占的要素の混合、限界主義の放棄かどうかは意見が分かれる)でも重要であるし、また、限界主義とポスト・ケインジアンの立場(多くがフルコスト原理の立場に近い)の関係を考える上で、重要な論点である。これはカルドア・チェンバリン・ハロッドの問題意識である。 - 第9章 「カレツキとケンブリッジ学派の貢献」 瀬尾 崇
・戦後初期にカレツキのミクロ分析に対する多くの言及がなされた。
⇒理論上の重要な発展はない(一般に、カレツキの考えを要約したもの)
⇒カレツキのミクロ分析の理論上の発展は1954年の『経済変動の理論』以降
キ ミクロ分析(生産、価格形成、独占度の説明、投資決定)
※(part 9の)議論の流れ
・生産過程の分析→Production as a circular process ・価格形成、独占度の説明→Pricing and the degree of monopoly ・投資決定→Investment decisions
The theory of economic dynamics and afterPart.7 Part.8より
Production as a circular process・1930年代の「生産体系」の考え方
1. Austrian economistsのone-way street
⇒「原材料→中間生産物→最終消費財」という一方向(一方通行)の流れ
_F.Burchardt(←Kalecki採用)
⇒固定資本ストックの重要性(循環的生産の中で維持され、拡大される)
*1940年代のKalecki研究者は_と_の区別が曖昧だった(H.GaitskellやW.Leontiefの批判)
・循環的生産モデルの発展に対する重要な貢献⇒P.Sraffa
特に「a multi-industry price model(複数の産業価格モデル)」の発展
⇒mark up pricing equations(マーク・アップ価格方程式)やKaleckiの産業価格方程式と類似点を持つ
・1980年代までに、Sraffianの循環的生産モデルとマーク・アップ価格方程式の統合が完成し、ミクロ経済分析のモデルの基礎となった
Pricing and the degree of monopoly・Kaleckiのミクロ分析(「独占度」に関する分析)
⇒新古典派的にも、反新古典派的にもどちらにでも解釈(and 発展)できた
・新古典派的に解釈する立場
⇒Kaleckiのミクロ分析が限界主義的な枠組みの中にあると解釈(企業は利潤を最大化するように価格を設定する、「独占度(the gross profit margin)」は価格弾力性によって決定される)
・反新古典派的に解釈する立場
⇒_N.Kaldor「経済変動の理論」では独占度と価格弾力性の関係は排除されていて、平均直接費用に対する価格の割合を独占度と定義している
_P.Davidson_と同様
_S.Coontz産業(製造業)における総費用に対する総収入の割合は一定であるので、現代資本主義における独占力は平均直接費用を超える一定のマーク・アップを保証するためのものであるという立場が維持されている
・価格と平均直接費用の「short-run(短期)」の反限界主義的な行動の解釈
⇒P.Riach(→P.Relnold)より基本的なeconomic forces(市場集中、販売促進、直接費用に対する間接費用の割合、労働組合)の中に独占度を置こうというKaleckiの試みは、経験的なtestingに従った反限界主義的な説明になっている
*欠点:processの説明がない
・「longer-term(長期)」(___:_1960年、_:1960年代)
1. J.Robinson投資決定は粗利潤の蓄積と関係している
→経済成長に影響を及ぼすthe profit margin(利益マージン)の役割を強調
→(特に)独占度を測る基準として「the gross profit margin/average direct cost[総(粗)利益マージン/平均直接費用]」
→マーク・アップの大きさは競争の支配力と投資率によって調整される
→price leaders(価格先導者)は価格設定時に、投資計画にfinance
(融資)するのに必要とされる利益を考慮して利益マーク・アップを直接調整する
_R.HieserKaldorの考え(独占力→「参入を阻止する価格>平均総費用+標準利益」)を受けて、「独占」利益マージンは3つの参入障壁(規模の経済、マーケティングのコスト、専売特許の生産技術)の関数
_N.Kaldor利益マージンは、短期においては比較的安定しているが、長期においては(完全雇用のもとで)「thermostatically(自動調節的)」に総需要量(投資)と結び付けられている
_J.Ball企業は価格設定時にマーク・アップ原理を使っており(短期における市場管理と安定確保のため)、短期における利潤最大化ではなく、長期における売上の成長に関心がある
→固定資本に投資する必要がある
→価格と投資決定の関係が重要
→計画された投資の量によって(売上の期待成長率によって)マーク・アップは決まる
<計算式>
I=g×Q
⇒P=r[(Q)(ATC)]
⇒I=vP=vr[(Q)(ATC)]
⇒g×Q=I= vr[(Q)(ATC)]
⇒g=vr[ATC]/x
・J.RobinsonとN.Kaldorの経済成長に関する研究は、投資と価格とマーク・アップのつながりに関する2つのことなったアプローチを生み出した
_.The Robinsonian approach
⇒企業の役割を最小限にし、マーク・アップの決定の際のfinanceの役割を無視する
*A.Asimakopulos
Robinsonの経済分析を、一部門の成長モデルの点から修正
⇒産業集中の増大による独占度の増大は、マーク・アップが増大する(実際の収益率の増大)→投資計画の増大をもたらす
⇒目標収益率をマーク・アップ(価格)と結びつけることで、企業は投資計画にfinanceするのに必要な利益をあげることができる
欠点:マーク・アップの決定要因を、企業の外部環境に置いている
_.The Kaldorian approach
⇒マーク・アップの決定において、企業とfinanceの役割を強調
*J.Kregel、Harcourt、P.Kenyon、Awood、AEichner
_J.Kregel
⇒利益マーク・アップと投資決定をつなげる
企業の独占度の増大→価格の上昇と総利益の増大
→企業はdividends(利益配当)とretained earnings(利益留保)の分配を調整する
→retained earningsは投資計画にfinanceするために使う
企業はactual rate of capacity utilization(実際の稼働率)がほぼtargeted normal rate of capacity utilization(目標標準稼働率)になるように企てる
→両者の差をなくすような投資計画を実行する(利益の付加が投資計画のfinanceに十分になるように利益マーク・アップの水準を決める)
*investment-based pricing strategy(投資を基準にした価格戦略)は、短期の売上の変化が、価格の変化や投資計画によってではなく、実際の稼働率によって適合されているということを示している
_Harcourt(and P.Kenyon)
⇒長期のフレキシブルな利益マージンに注目
利益マージンの変化と短期の価格が投資のパターンによって決定されるときにKaldorのモデルは機能するということを示した短期も含めた長期の投資計画とprice leaderの作用を通じた利益マージンのつながりを前提とすることで、短期の価格設定に使用される利益に対する、長期のマーク・アップの説明に基礎を与えた
⇒なぜ短期における需要の価格弾力性が、短期のマーク・アップの決定に役立たないのかを示した
→長期の投資要求や貯蓄性向は、短期のcustomaryなマーク・アップの究極的な決定要因である
_Awood
profit margin:企業の「総利益/全売上(収入)」 ※生産過程全体
long term:(具体的に)3_5年
上記のような用語の定義づけをした上で、利益マージンの水準を企業の目的関数から説明する
<計算式>
pm=(1+f-x)gsk/r
欠点:product-specific(生産)にではなく、enterprise-specific(企業)に目が行っている
_AEichner
⇒企業はまず第一にretained earnings(利益留保)によって、第二にexternal finance(外部財源、資金調達)によって成長をfinanceする
⇒SATC(standard average total cost)に対する利益マージン(=rSATC)
→価格の下落、研究開発費や宣伝広告費や設備投資などのための自由に使える資金のために企業が留保しておく利益をカバーするものでなければならない
⇒追加的な投資ファンドのためには、マーク・アップも同様に増やさなければならない
Investment decisions・Kaleckiの企業家的投資決定の分析の基礎
⇒企業家が資本を投資したり貯蓄したりするa natural propensity(Keynesでいうanimal spirit)を持っているという前提
・J.Robinson
⇒資本蓄積の目的のための投資決定は、期待利益水準と競争の程度の関数
⇒企業家は、競争に生き残ったり企業を成長させたいという本質的な欲求があるため、利益に関しては少ないのより多い方を好むが、新古典派のように最大化しようとは思っていない
・N.Kaldor
⇒「animal spirit」と「企業家の欲求」は、Robinsonと共通
⇒投資決定はnormal capacity utilization(標準稼働率)と売上の伸びの関数
*Kalecki-Robinsonの考え方(投資決定は主に期待収益率のfunction(作用)によってきまる)
⇒時代が変わっても広く受け入れられている考え方- <参考文献>
植村博恭 磯谷明徳 海老塚明『社会経済システムの制度分析』,名古屋大学出版会,1998
Kalecki,M.『経済変動の理論』宮崎義一 伊東光晴訳,新評論,1958 - /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
・感想
この章はカレツキの考えを受けて、その後、様々な人が評価し、発展させていった様子が書かれてあり、ある意味で最も面白い部分なのだが、私自身がまだ十分にポスト・ケインズ派の考え方を理解していないため、テクニカルな言葉の訳や理論の内容など十分に紹介できてない。
しかし、ポスト・ケインジアンの価格理論は、現在の主流派(新古典派)とは違ってできる限り現実にそった理論作りをしてきていたのがよくわかった。
私の専門はマルクス経済学だが、その価格理論はポスト・ケインジアンのそれにかなり近く、また共有している部分もあることが分かった。修士論文では、マルクスの生産価格論(利潤論)を扱うが、マルクスも平均利潤(PKでいうマーク・アップ)の決定に関して十分な考察を行っていない。そういう意味でも、この章は、カレツキ以降の理論の発展の中にその解決のヒントがあるような気がする。
恥ずかしながらPKを勉強するのは初めてだったが、大変興味を持つことができ、マルクス経済学とあわせて研究していきたい。 - ____
- 10論』(以下,『一般理論』と略記する場合もある)において,生産と所得の水準が総需要によって決定されることを説く「有効需要の原理」という斬新な考え方を打ち出し,失業が需要の不足によって生じることを明らかにするとともに,雇用を改善するための国家の政策介入に理論的な根拠をあたえた。また, これとほぼ同じ時期に,カンツキも,マルクスの再生産表式分析から出発して,ケインズとは独立に同じ理論に到達していた。分析の枠組みに不完全競争を導入して価値と分配の理論を展開したカレツキの説明は,ある意味においてケインズの理論よりも「真に一般的な理論Jであつたとジヨーン・ロビンソンは述べている(Robinson[1972]p4:邦訳308頁): ・
- Robinson,J[1972],“The Sccond Crisis in Economic Thcov",И“′万ια″E00″ο“たRονJall,Vo1 61,No 2(「経済学の第2の危機J,山田克巳(訳)『資本理論とケインズ経済学』日本経済評論社,1988年,所収
- その生涯にわたつてカレツキの経済学の意義を熱心に説きつづけ,彼の理論的枠組みの拡張に力を注いだ有力な経済学者の一人が,前章でも触れたジヨーン・ロビンソンである。彼女は,1952年に次のように述べて,カンツキが「一般理論」の独立の発見者であるとともに,彼の理論が動学的な性格をもつものであることを指摘している。
- カレツキ氏がケインズとは独立に「一般理論」を発見したことは,科学の暗合の古典的な一例であった。彼の分析の形式は景気循環のモデルを直接に導いた(ケインズのものはそうではなかった)。彼の理論は短期均衡という同じ概念にもとづいていたから,おのずとケインズ体系に当てはまり,そうして「一般理論」のその後の発展においてケインズ体系に吸収されるに至った。現在では,人がいずれから何を学んだかを区別することは不可能である。(Robinson[1952]p159:非6副ヽ194-5頁)
- カレツキがケインズに先行して「一般理論」を発見したのか否かを判断する際には, まずもって「一般理論」の基本的な構成要素が何であるのかを確定する必要がある。J.ロビンソンは,ケインズ経済学の核心が,「貯蓄率は投資率によって支配され,物価水準は貨幣賃金率の水準によって支配され,利子率の水準は貨幣の需給によって支配される」という三つの命題に要約されるであろうと述べている(RoЫnson[1966]pp v面→x)。そのうえで彼女は,『一般理論』の公刊にいたるまでの間に,「たがいに何の接触もなしに, ミハウ・カレツキは同じ解決法を発見していた」(めブ′,p破)と結論している。
- さらに彼女は,次のように述べてカレツキの先行性を認めている。「カレツキがケインズに対して公刊上の先行性をもつのは,ポーランド語の著作だけではない。彼は,1933年10月に「景気循環のマクロ動学理論」に関する論文をエコノメトリック・ソサエティで報告した。その論文は,貯蓄。投資・雇用の理論の基本的要素を含んでいる」(Rounson[1977]p9)。そのうえで,「いくつかの面においては,カンツキの見解のほうがケインズのそれよりも頑健である」(プι″,p10)として,たんに公刊の先行性においてのみならず,その内容においてもカレツキの理論のほうが優れていると主張している。
- Robinson,J[1952],ル`Rαたグルた″S′α″グθ″`′島望ムLondon:Macmillan(大川一司。梅村又司(訳)『利子率その他諸研究』東洋経済新報社,1955年)
- プレカリアートは消費者中心の考え方
- マルクスの生産中心主義の欠点を補うもの
- マルクスの考え方だと会社を自分のものにした後の展望がない
- カレツキは史的唯物論における国家と資本の双頭性を把握しており、また剰余価値をマークアップと捉えたり、経済分析を経営に活かし得るものにしている。簡単に言えば資本を運営する側の視点がある。言い換えれば展望がある。
- ケインズとの違いは資本主義を不安定なものだと自覚していた点だ。ミンスキーに影響を与えている。
- The above discussion is summarised in Table 2. From this table, we seethat shifts in the realization curve always affect the rate of profit (andtherefore the rate of growth), whilst shifts in the profits curve only affectthe rate of profit (and the rate of growth) when the economy is operatingbelow full capacity and the accelerator effect is positive(iu > 0)Table 2: Effect of parameter changes on net profits and investmentUpward shift inDownward shift inrealization curve*profits curve**Full Capacityno effectExcess Capacity(a) iu = 0no effect(b) iu > 0*caused by a change in the 'demand' parameters sm,b,io.iu and im**caused by a change in the 'cost' parameters m, k, f, 8,tTParadoxesThe above discussion has revealed two kinds of paradox. First, there isthe paradox of thrift. If capitalists save a smaller fraction of their ncomelower ST or the government borrows more (higher b), the resultingincrease in demand causes profits to rise. As a result of this rise in profits,total saving and total investment both increase. Less thrift thereforeleads to more saving!A more striking, if less general, paradox is what might be called the"paradox of costs". Suppose the economy is operating below fullcapacity and that iu >0. Anything which increases the real cost ofproduction (including taxes and depreciation) will reduce the amount ofnet profit earned at the current level of capacity utilization. However,such an increase in costs will be followed by a rise in output, and so thelevel of capacity utilization will increase. Since u>0, the economies ofscale resulting from higher capacity utilization will more than offset theeffect of higher costs. As a result the rate of profit will increase. Thus,under the assumed conditions, higher costs lead to higher profits. Thisparadox holds no matter what the nature of the cost increase. Providedthe appropriate conditions are satisfied, higher wages, higher fixedcapital requirements, faster depreciation or higher taxes on profits will allbe of benefit to capital.14 They will reduce the rate of profit which can beachieved at any given level of output. But they will also increase the levelof output itself, and because of this the actual rate of profit will rise.18BIBLIOGRAPHYy of Income Distribution', CanadianJournal of Economics 8BARAN, P. and SWEEZY, P. 1966 Monopoly Capital, London.CUYVERS, L. 1979 RobiJoan Robinson's Theory of Economic Growth', Science andSociety, FallFEIWEL, G. 1975 The Intellectual Capital of Michal Kalecki, KnoxvilleHARRIS, D. J. 1978 Capital Accumulation and Income Distribution, StanfordHARROD, R. F. 1973 Economic Dynamics, London.LDOR, N. 1957 'A Model of Economic Growth' Economic Journal, Vol.67KALDOR, N.KALDOR, N. and MIRRLEES,1960 Essays on Economic Stability and Growth, LondonJ. A. 1961 'A New Model of Economic GrowthReview of Economic Studies, Vol.29Kingdom, CambridgeKALDOR, No. 1966 Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the UnitedKALDOR, N. 1978 Further Essays in Economic Theory, LondonKALECKI, M. 1939a Place Nominalne i Realne, Warsaw.KALECKI, M. 1939b Essays in the Theory of Economic Fluctuations, London.KALECKI, M. 1971 Selected Essays in the Dynamics of the Capitalist Economy,Cambridge.·1971, The Rate of Profit, Distribution and Growth, LondonKREGEL, JMALINVAUD, E. 1977 The TheoryMALINVAUD, E. 1980a, Profitability and Unemployment, CambridgeMALINVAUD, E. 1980b, 'Macroeconomic Rationing of Employment'of Unemployment Reconsidered, Oxfordinand Fitoussi, J. P. (eds.) Unemployment in WesternMalinvaud, M.Countries, London 1980ASINETTL L. 1974 Growth and Income Distribution, CambridgeROBINSON, J.ROBINSON,ROBINSON, J. 1969, The Accumulation of Capital, (3rd edition), London1960, The Theory of Distribution' in Collected Economic Papers,Vol.lll, Oxford 1960J. 1962, Essays in the Theory of Economic Growth, London.STEINDL, J. 1952, Maturity and Stagnation in American Capitalism, Oxford第1章需要,実質賃金,経済成長21図1-1費用上昇の効果π|利潤曲線π|利潤曲線π|利潤曲線実現曲線実現曲線実現曲線ti111 =0(a)完全稼働(b)過剰能力(b)過剰能力ǐzc >0表1-2純利潤と投資とへのパラメタ変化の効果実現曲線の上方移動*利潤曲線の下方移動**効果なし完全稼働状態過剰能力状態(a) įu_0効果なし*「需要」パラメタSn, b, to, ¡ 1xの変化によって生ずる.**「費用」パラメタ,n, k, f, δ, 1xの変化によって生ずる.逆説上の議論によって, 2種類の逆説が明らかとなった.第1は,節約の逆説である.あるいは政府が借り入れを増やす(bを高める)かするならば,その結果生ずる需要の増大が利潤を増加させる。この利潤増加の結果として,総貯蓄と総投資はともに増大する。したがって節約意欲の低下が貯蓄の増加へ導く!資本家がその所得のより少ない割合を貯蓄する(Srが低下する)か,これに比べるとあまり知られていないが, より印象的な逆説は,「費用の逆説」と呼んでよいものである·経済が不完全稼働状態で操業しており,心0であると仮定しよう.生産の実質費用(租税と減価償却を含む)を増加させるものはなんであれ, そのときの能力利用水準で獲得される純利潤の額を減少させるであろう. しかしながら,費用のそのような増加に続き産出の増加が起こり,そして能力利用の水準は上昇するだろう. iu > 0である以上, より高い能力利用から生ずる規模の経済は, より高い費用の効果を相殺して余りあるの結果利潤率が上昇するはずだ· こうして,仮定された諸条件のもとでは高費用は高利潤へ導く.この逆説は費用増加の性格がどのようなものであっても成立する適当な条件が満たされるならば, より高い賃金, より高い固定資本必要額, より速い償却,あるいはより高い利潤課税,それらすべてが資本にとって利益になるだろう. それらは,与えられた 能力水準において達成されうる利潤率を引き下げはするが, しかしまた,産出水準それ自体を引き上げもするのであり, このために現実の利潤率は高まるであろう.14)過少消費本モデルでは,消費が中心的役割を演ずる·経済停滞がある経済主体の側の行き過ぎた貯蓄性向によって引き起こされる可能性がある以上は,節約を差し控えてある種の消費を増加することにより、いっそう速い成長を促しうる.そうはいっても,本モデルはその性質において純然たる意味で過少消費説的であるというわけではない.ある種の消費が需要と投資を刺激しうるという事実にもかかわらず,一方における消費と他方における需要および投資とのあいだには,一意的で明瞭な連関も,あるいは因果的連鎖もない.経済が不完全稼働状態で操業しているときには, より高い投資とより高い消費はつねに相伴うのであり,総消費の増加は経済を刺激し産出の増加と成長の加速をもたらすだろう.しかし経済が完全稼働状態にあるときには,状況はまったく異なる.総産出は与えられているのであるから,投資を増加させるものはどれも,公的消費と民間消費とを合わせた総額を必ず削減するにちがいない. これは算術の問題である·たとえば,政府が支出を増やし民間部門から必要資金を借り入れると仮定しよう.われわれがみたように,これは投資の増加へ導く·しかしそれは物価その結出らbiurに実め昇をも伴うのであり,したがって利潤は上昇し実質賃金は下落する.上果として生ずる労働階級の消費減少は政府および財産所有者の消費増加を相殺して余りある.総消費は減退するのである.過少消費の問題は実際には,産出が需要にどのような仕方で反応するかにか定転高,それ故に,かっている.本モデルでの不完全稼働状態の場合のように,産出が相対的に弾れないということに留意すべをデブーイ経済をデフレある.たとえば,政府は賃金に対する労働組合の圧力に対して,経済化することによって(政府支出を削減したり,増税したり,あるいは利引き上げたり等々によって),対応するかもしれない.これは需要水準を引げ,利潤マージンを低下させる,このように,労働組合は完全稼働状態では所得分配に直接に影響を及ばすことができないとしても,需要に対する政府の政策への効果をとおして間接的に影響を与えることができる.7)新ケインズ派は,る (あるいはいおうとすべきである) ときに,「完全雇用」について論ずるためしばしば混乱を招いていることに注意しなければならない。マークアップに間接的に影響を及ぽすかもしかれらが事実上は完全稼働利用度のことをいおうとしてい,(1952)は見事な類推で,寡占下での余剰能力の理論を貨幣の流動性Steindl選好の理論になぞらえた。売上高の将来の成長を見越した余剰能力の需要は貨幣の取引需要に対応し,予見されない緊急事態に対処するための余剰能力の需要は貨幣の予備的需要に対応する。ただし貨幣の投機的需要にちょうど対応するものがなんであるかは,明明白白とはいえない。8 )9)カレツキ自身はi-0と仮定したが, しかしかれの追随者のほとんどはi>010)均衡という用語は, ここでは,貯蓄と投資が等しく,その結果全利潤が正確11)安定条件は次のようになると仮定したに実現されるというきわめて限定された意味で使われている.L 2]dS dlこの場合,導関数は利潤曲線に沿って求められる,完全稼働状態においては,この条件はSr>魂に等しく,tiuk/mに等しいそれはseiが働く一例であるまた完全稼働に満たない状態では,12)いうまでもなくハロッドの「不安定性原理」1973参照).これは,(Harrod,13)14)このための条件は,u<1かつiu > 0である.カレツキ自身はiu=0と仮定したこと,したがってまた,かれの理論においては賃金ないし他の費用の増加は利潤率あるいはむしろ成長率に対してなんの効果ももたないことに注意せよ.しかしカレツキの追随者のほとんどは,明示的にせよ暗黙のうちにせよ, iu >0と仮定する.この問題のやや異なった議論については,13]を参照せよ.Kaldor (1978)と仮定する.点Rでの利潤は点Pでの利潤と同一となろう.短期のモデルを用いている·iu=0ならば投資が固定され15)この説明はiu>0であることを前提とする,すでにみたように,16)Asimakopulos (1974)を参照.アシマコプロスはそこで,る事実上はかれは,本モデルにおいてi.>0,1,-t36図1-11バランとスウィージーのデフレ傾向利潤曲線実現曲線価値が実現されえないならば,経済は収縮するであろう.産出と雇用は低下し,経済は究極的には,以前よりも少ない剰余価値しか創造されない新しい均衡で安定することになろう。その場合われわれは,剰余価値の増大傾向が現実にはその反対のかたちで,すなわち,実際に創造される剰余価値の量の減少となってあらわれるという逆説に直面することになろう·すべての過少消費説的逆説と同じように, この結果は剰余価値の創造とその実現とのあいだの相互依存によるものである.結語この論文を締めくくるのには,以下の言葉が妥当であろう.能力利用度の重要性需要と成長についてのこれまでの議論は能力利用度の重要性を示している.完全稼働をかなり下回る状態で操業している経済では,実質賃金を引き下げることなしに利潤率を引き上げ投資を促すことができる.それどころか,実質賃金を引き上げることさえも有利になるかもしれない。なぜなら,これが需要を刺激して, より大きな産出, より大きな利潤,そしてより多くの投資へと導く第1章需要,実質賃金,経済成長3723)ことになるかもしれないからであるいうまでもなくこれは, より高い実質賃金についての過少消費説的議論である. しかしながら,経済が完全稼働状態にあるときには, この議論はもはや有効ではない.その場合には賃金と利潤とのあいだに明らかな対立がある.実質賃金のいかなる増大も利潤を犠牲にするであろうし, したがって投資と成長への意欲を阻喪させるであろう.こうして,経済が不完全稼働状態で操業しているときには実質賃金の上昇は成長を促進しうるのに対して,完全稼働状態そのものにおいては逆のことが真となる.そのうえ賃金と需要とのあいだの関係は,完全稼働か不完全稼働かでまったく異なってくる.不完全稼働状態では因果作用は実質賃金から需要へと,典型的な過少消費説的方法で働き, より高い賃金は需要への効果をとおして成長を刺激する·完全稼働状態においては因果作用は需要から実質賃金へと反対の方向をとり,そして,より大きな需要はそれがインフレを助長して労働者所得の購買力を削減するがために成長を刺激するのである. この2つの状態の対照性は,因果作用の連鎖を描く次の図式からみて取れよう過剰能力:より高い→より大きな→より多くの→より多くの賃金 需要 産出 投資完全稼働:より大きな→より高い→より低い →より多くの需要 物価 実質賃金 投資最初の連鎖は,成長の過少消費説型理論を具体化しており, これに対し第2の連鎖は成長の「インフレ型」理論と呼びうるものを具体化している.収穫逓減本論文で用いられたモデルにおいて成長の過少消費説型理論は,現存の設備を使ってより多くを生産することが物理的に不可能となる点にちょうど至るまでの産出の全範囲にわたって適用される.この点に達してはじめてその理論
表1.4ホリニス:ケインズ後のマクロパラドックス
節約のパラドックス(ケインズ、1936年):
節約率が高いほど、生産量は減少します。
コストのパラドックス(Kalecki、1969; Rowthorn、1981):
実際の賃金が高いほど利益率が高くなります。
公的赤字のパラドックス(Kalecki、1971):
政府の赤字は民間の利益を上げる。
債務のパラドックス(Fisher、1933; Steindl、1952):
レバレッジ・レバレッジへの取り組みは、レバレッジ・レシオの向上につながる可能性がある。
平静のパラドックス(Minsky 1975):
安定性は不安定化している。
流動性のパラドックス(Dow、1987; Nesvetailova、2007):
流動性を創出する新しい方法は、液体資産を流動性のない資産に変えることに終わります。
リスクのパラドックス(Wojnilower、1980):
個々のリスクカバーの可用性により、全体的にリスクが増加します。
利益主導の需要のパラドックス(Blecker、1989):
全般的な賃金制限は、すべての経済が利益を上げているように見える場合でも、成長の減速につながる。
アメリカ資本主義の成熟と停滞―寡占と成長の理論 単行本 – 1988[1952]
節約のパラドックス(ケインズ1936、ロビンソン1956)
貯蓄率が高いほど生産量が減少し、成長率が低下する
公的債務のパラドックス(Kalecki 1971)
政府の赤字は民間の利益を上げる
コストのパラドックス(Kalecki 1969、Rowthorn 1981)
実質賃金が上昇すれば、利益率が上昇する(活動、賃金主導の成長)
利益主導の需要のパラドックス(Blecker 1989)
すべての国が利益を上げているにもかかわらず、賃金の低下は成長の遅れにつながる可能性がある
柔軟性パラドックスI(Krugman 2012)
より柔軟な賃金と価格があるほど、フィッシャーの倒産の影響はより劇的になります
柔軟性パラドックスII(Seppecher 2012、Dosi et al。2016)は、
雇用者が従業員を雇って雇うことが容易になればなるほど、雇用は少なくなる
____
すべての政策立案者が知っておくべき危機関連のマクロ経済のパラドックス
平穏のパラドックス(Minsky 1975)
安定性が不安定化している
債務のパラドックス(I.フィッシャー1933、Steind 1952)
デフレバレッジへの取り組みは、より高いレバレッジ率につながる可能性がある
流動性のパラドックスI(Minsky 1986 Nesvetailova 2007)
金融革新は、実際には流動性を低下させている
流動性のパラドックスII(Dow 1987)
より流動性の高い液体資産を非流動的資産に変換しようとする努力 - ミンスキーモーメント
リスクのパラドックス(Wojnilower 1980)
個々のリスク・カバー(MBS、CDS)の可能性は、全体的なリスクを全体的に高める
劣化基準のパラドックス(McCauley 2009)
引受基準の低下のためデフォルト率は低い
フィレンツェEPOG 2011年7月
オタワ大学