http://nam-students.blogspot.jp/2016/08/blog-post_4.html (本頁)
http://nam-students.blogspot.jp/2015/11/heidegger.html
http://nam-students.blogspot.jp/2012/11/blog-post_1706.html
|形| | | オ |
|而|『形而上学』 |論|『カテゴリー論』 ル |
|上| | |『命題論』 ガ |
|学| |理|『分析論前書』 ノ 道 |
|_|_____________| |『分析論後書』 ン=具 |
| |『自然学』運動、時間論他 |学|『トピカ』 所 |
| | 一部が『天について』| |『詭弁論駁論』 収 |
|自|「生成消滅論」 |_|_____________|
| |「気象論」 | |『ニコマコス倫理学』 |
| |_____________|実|『マグナ・モラリア』@ |
| |『動物誌』 | |『エウデモス倫理学』 |
|然|『動物部分論・動物運動論・|践|『美徳と悪徳について』 |
| | 動物進行論』 | |_____________|
| |『動物発生論』他 |哲|『アテナイ人の国制』 |
| |_____________| |『政治学』 |
|学|『霊魂論』 |学|『弁論術』 |
| |「夢について」 | |『詩学』 |
| |「呼吸について」他 | | |
|_|_____________|_|_____________|
(『イラスト西洋哲学史 上』127頁)
@『マグナ・モラリア』=『大道徳学』
http://urag.exblog.jp/6819878/
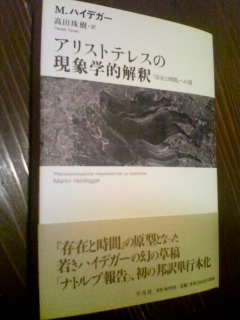 アリストテレスの現象学的解釈――『存在と時間』への道
アリストテレスの現象学的解釈――『存在と時間』への道マルティン・ハイデガー:著 高田珠樹:訳
平凡社 08年2月 定価2,940円 46判上製カバー装232頁 ISBN978-4-582-70277-4
帯文より:『存在と時間』の原型となった若きハイデガーの幻の草稿「ナトルプ報告」、初の邦訳単行本化。「若きマルティン・ハイデガーの草稿、それも本人の偉大な活動の始まりを示す原稿が出てきたというのは、まことにひとつの事件というほかない。……このアリストテレス理解は真にひとつの革命を引き起こすことになった。アリストテレスが、われわれのいる場に立ち現われ、われわれに向かって本当に語り始めたのである」(ハンス=ゲオルク・ガダマー:本書より)。
底本:"Phänomenologische Interpretationen zu Aristoteles (Natorp-Brecht)", hrg. von Günther Neumann, Reclam, 2003.
目次:
アリストテレスの現象学的解釈
序にかえて
解釈学的状況の提示
『ニコマコス倫理学』第六巻
『形而上学』第一巻の第一章と第二章
『自然学』第一巻から第五巻
〔第二部について、『形而上学』第七巻、第八巻、第九巻の解釈〕
ハイデガーの初期「神学」論文 (ハンス=ゲオルク・ガダマー)
編者あとがき (ギュンター・ノイマン)
付録『ナトルプ報告』の成立とその位置 (高田珠樹)
訳者あとがき
***
…「編者あとがき」や「付録」「訳者あとがき」を参照すると、本書の成立はおおよそ次のようになるかと思います。
新カント派の代表的哲学者の一人であるパウル・ナトルプの求めに応じて、マールブルク大学への就職のため自らの目下の研究内容を端的にまとめた「アリストテレス序論」、それが本書「ナトルプ報告」の名前の由来です。本稿は結局序論にとどまり、本編は執筆されませんでしたが、彼が試みた思索はやがて代表的著作『存在と時間』に結実します。その前哨地として長らく幻の草稿とされてきた「ナトルプ報告」が初めて公刊されたのは、ハイデガーの生誕百周年となる1989年でした。
高田珠樹さんによる初の日本語訳が発表されたのは、岩波書店の月刊誌「思想」813号(92年3月)でした。底本は89年に『ディルタイ年鑑』第6号に掲載されたいわゆる「ミッシュ・タイプ稿」です。「序論」はマールブルク大学に送付されると同時に、ゲッティンゲン大学のゲオルク・ミッシュのもとにも送られていたのでした。
「ナトルプ報告」には、ハイデガーの手元に残されていた、手書きの修正や加筆を含む「ハイデガー・タイプ稿」もあり、これが03年にレクラム文庫の元になっていて、ミッシュ稿との異同が注記されています。今回の単行本化においては、このレクラム文庫版を底本として改訳したとのことです。
本書に収録されたガダマーの論文の中で、彼は「ナトルプ報告」のインパクトをこう回想しています。「当時の読者にとって、このテクストの一文一文がどれほど新奇なものであったか、今日ではほとんど書きつくせそうにない。ハイデガー自身の面識を得て、彼から次第に何かを学ぶようになった後も、私は、その頃を思い出しては、ナトルプが、この大胆な思索の徒の語り口や文章に見られる伝統に逆らった一種独特の流儀にもかかわらず、その若き後学の天分を認めたのにはやはり敬服するほかないと密かに考えたものである」(111頁)。
かなり難解な著作であり、翻訳の苦労はつぶさに「訳者あとがき」に綴られています。「ナトルプ報告」は03年のレクラム版のあとに、05年にドイツ語版『ハイデガー全集』第62巻「存在論と論理学に関するアリストテレスの精選論文の現象学的解釈」に付録として収録されました。いずれは、創文社版『ハイデッガー全集』でも別訳が刊行されることになるのだろうと思います。創文社版では第62巻は、講義部門の初期フライブルク講義1919-1923のうち、1922年夏学期にあたり、邦訳題は「オントロギーと論理学に関するアリストテレスの精選諸論文の現象学的研究」と予告されています。
ハイデガーがここで言いたいのは、いわゆるプレ・ソクラティカーたちのフィシス(自然)についての思索と、プラトンのイデア論から始まる「哲学」との間には決定的な断絶がある、ということである。
ハイデガーによれば、プレ・ソクラティカーたちのフィシスとは、単なる物質的自然、死んだ自然ではなく、むしろ生成する自然、そして存在の根源そのものである。これに対して、プラトンが数学的な世界観(ピタゴラス主義)によって持ち込んだイデアという不変なるものは、存在そのもの(Sein)ではなく、あるものが「何であるか」という意味でのもの(Was-Sein)でしかなかった。この「本質-存在」に対置されるのが、現実に存在している物事としての「事実-存在」(Dass-Sein)である。プラトンが「本質-存在」を重視したのに対して、アリストテレスは「事実-存在」としての個体に注目した。これによって「形而上学」が始まったのだ、とハイデガーは言っている。
しかし、ハイデガーは、プラトンはもとより、アリストテレスにも味方しない。なぜなら、「事実-存在」というものは、そもそも「本質-存在」と対になって現れたものであるにすぎないからである。むしろ、「本質-存在」と「事実-存在」という区別の根源にあるもの、その区別によって引き裂かれたもの、つまり「存在そのもの」としてのフィシスこそが重要なのだとハイデガーは考えるのである。その意味でハイデガーにとって、アリストテレスはプラトンよりもましだが、アリストテレスもプラトンとワン・セットなのであって、ここで形而上学が始まると同時に「存在そのもの」が隠蔽され、忘却されたのだとするのである。これがハイデガーの言う「存在忘却」の歴史の始まりである。
http://heideggerforum.main.jp/ej2data/shoki.pdf
…そもそも、「アリストテレス解釈」を超越論哲学として解釈することは、若きハイデガーの思想形成におけるアリストテレスの位置づけからしても、是認できない。それというのも、ハイデガーは、カント、リッカート、フッサールらの超越論哲学から強い影響を受けつつも、アリストテレス的傾向に依拠して、それを批判するというスタンスにおいて思想形成を行ってきたからである。まず、ハイデガーが存在の問いへと向かう契機となったとされるブレンターノの『アリストテレスによる存在者の多様な意義について』はアリストテレスのカテゴリー論をカテゴリーの生成論として解釈するものであった。そして、ハイデガーが一番最初に公表した哲学論文「現代哲学における実在生の問題」は、アリストテレス的実在論に依拠しつつ、当時のカント主義を批判したキュルペの批判的実在論を評価するものであった。また、ハイデガーの教授資格論文『ドゥンス・スコトゥスの範疇論と意義論』はラスクの思想の影響下にあるが、ラスクこそ、リッカート的観念論に対して、アリストテレスに依拠しつつ、素材の意義を唱えた人物であった。このように、様々な経路を経由してではあるが、ハイデガーの思想形成において、アリストテレスは、カントの超越論哲学の可能性の条件を規定する役割を果たしてきたことがわかる。…
「実体」(例:人間、馬)
「量」(例:2ペーキュス、3ペーキュス)
「質」(例:白い、文法的)
「関係」(例:二倍、半分、より大きい)
「場所」(例:リュケイオン、市場)
「時」(例:昨日、昨年)
「体位」(例:横たわっている、坐っている)
「所持」(例:靴を履いている、武装している)
「能動」(例:切る、焼く)
「受動」(例:切られる、焼かれる)
「質」(例:白い、文法的)
「関係」(例:二倍、半分、より大きい)
「受動」(例:切られる、焼かれる)
「時」(例:昨日、昨年)
[×「所持」(例:靴を履いている、武装している)]
《どんな結合にもよらないで言われるものどものそれぞれが意味するのは、あるいは実体か、あるいは「なにかこれだけ」[量]か、あるいは「何かこれこれ様の」[質]か、あるいは「或るものとの関係において」[関係]か、あるいは「或るところで」[場所]か、あるいは「或る時に」[時]か、あるいは「位している」[体位]か、あるいは「持っている」[所持]か、あるいは「為す」[能動]か、あるいは「為される」[受動]かである。
しかし、実体というのは、大ざっぱに言って、例えば人間、馬。「何かこれだけ」は例えば二ペーキュス、三ペーキュス。「何かこれこれ様の」は例えば白い、文法的。「或るものとの関係において」は例えば二倍、半分、より大きい。「或るところで」は例えばリュケイオンにおいて、あるいは市場において。「或る時に」は例えば昨日、昨年。「位している」は例えば横たわっている、座っている。「持っている」は例えば靴をはいている、武装している。「為す」は例えば切る、焼く。「為される」は例えば切られる、焼かれる。
しかし上に挙げられたものどもは、それぞれがそれ自身としてただそれだけで言われることは、どんな肯定においても存しない、いや、これらのものどもの相互の結合によって肯定はできるのである。というのは肯定はそのすべてが真であるか、偽であるかと思われるのに、どんな結合にもよらないで言われるものどもの何ものも(例えば、人間、白い、走る、勝つ)、真でもなければ、偽でもないからである。 》
初期論文集 (ハイデッガー全集1) [単行本]1996 創文社
マルティン ハイデッガー (著),
辻村 公一 (編集), 上妻 精 (編集), 茅野 良男 (編集), 大橋 良介 (編集), Martin Heidegger (原著), Hartmut Buchner (原著), Evelyn Lachner (原著), 岡村 信孝 (翻訳), ハルトムート ブフナー (翻訳), 丸山 徳次 (翻訳), エヴェリン ラフナー (翻訳)
目次
現代哲学における実在性の問題 *
論理学に関する最近の諸研究
書評
序文―『初期論文集』(一九七二年)初版のための
心理学主義の判断論―論理学への批判的・積極的寄与
ドゥンス・スコトゥスの範疇論と意義論 **
自薦の言葉
歴史科学における時間概念
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11138642321
angelic_chakochanさん 2014/11/25 12:06:59
【100枚】アリストテレスの時間論はどんな内容なのか詳しく教えて下さい。
出来る限り分かりやすく教えて頂ければ幸いです。
回答数:1 閲覧数:375 お礼:知恵コイン100
ベストアンサー
fieskrlqrtlmnczairkさん 2014/11/25 13:49:35
アリストテレスの「自然学」第4巻、第11章「時間とは何であるか」で次のように言っています。
「時間は運動に対して、その性格において準じるからであり、運動における・より先とより後・はその存在主体からいえば運動そのものに他ならないが、しかし、その定義のされ方は別であって、運動と同じものではない。そしてわれわれが時間を識別するのは運動を、より先とより後の区別によって区分するときに他ならない。つまり時間とは、より先とより後の区別に基づくに他ならないからである。したがって時間は運動そのものではなく、数をもつ限りおいての運動なのである」岩波旧全集③別訳170頁参照219b
言っていることは、運動は連続しているけど、時間はその運動を、より先とより後に分割して、それを数えることだ、ということです。
アリストテレスは時間は出来事の前後関係、因果関係だと言っていることになります。
出来事のより先とより後を認識するための、一種の「枠組み」を時間と考えていた、ということ。
質問した人からのコメント2014/11/30 22:20:40
感謝 分かりやすくお答え頂きありがとうございました!
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E7%84%B6%E5%AD%A6_(%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%B9)
自然学 (アリストテレス)
『自然学[1]』(希: Φυσικῆς ἀκροάσεως (physikēs akroaseōs)、羅: Physica, Physicae Auscultationes、英: Physics)とは、古代ギリシアの哲学者アリストテレスによる自然哲学の研究書である。
アリストテレスは、「万学の祖」と呼ばれ、様々な領域の研究を行った傑出した哲学者であり、自然学的な研究も数多く残しており、現代の天文学、生物学、気象学 等々等々に相当する領域でも研究業績を残している。この『自然学』はそうした自然学研究群の基礎を構成し、なおかつアリストテレス哲学の中でも重要な位置を占めている[2]。
本書は全8巻で構成されており、第1巻から第2巻までは原理についての論述、第3巻では運動と無限なものについて、第4巻では場所、空間、時間について、第5巻から第8巻では運動と変化について考察されている。自然を研究する上でまず一般的な原理に基づきながら徐々に個別な対象を分析している。
目次
構成
全8巻から成る。
- 第1巻 - 自然学の領域と原理の概説。全9章。
- 第1章 - 自然学の対象と研究方法上の心得
- 第2章 - 自然の「第一原理」の数や種類についての諸難問、自然的実在はエレア派が想定するような「一者」ではない
- 第3章 - エレア派の論議に対する論理的検討
- 第4章 - 原理についての自然学者たちの所見会とこれらに対する批判
- 第5章 - 原理は反対のものどもである
- 第6章 - 原理は数において二つまたは三つ
- 第7章 - 生成過程の分析により著者の見解 --- 原理の数は二つ(質料と形相)または三つ(質料と形相と欠除)であること --- の正しさが示される
- 第8章 - この正しい見解によって原理についての諸難問が解決される
- 第9章 - 「第一原理」(質料と形相と欠除)についての補説
- 第2巻 - 自然学の対象と四原因。全9章。
- 第1章 - 自然・自然的とは何か、自然と技術
- 第2章 - 自然学の対象と「自然学研究者」の任務、彼らと「数学研究者」及び「第一哲学研究者」との相違
- 第3章 - 転化の四原因、自体的原因と付帯的原因
- 第4章 - 偶運と自己偶発、これらについての他の人々の見解
- 第5章 - 偶運とか自己偶発とかは存在するか、またどのように存在するか、偶運の定義
- 第6章 - 自己偶発と偶運の相違、これらは転化の自体的原因ではない
- 第7章 - 自然学研究者はその四原因の全てから考察し把握せなばならない
- 第8章 - 自然の合目的性、エンペドクレス等の機械的必然論への批判
- 第9章 - 自然の世界における必然性の意義
- 第3巻 - 運動、無限。全8章。
【運動について】- 第1章 - 運動の種類、運動の暫定的定義
- 第2章 - この定義を確証するための補説
- 第3章 - 動かすものと動かされるもの、それらの現実化、運動の定義
【無限について】 - 第4章 - 無限なものについての先人の諸見解、その存在を認める人々の説と彼らがそれを想定する理由、無限の諸義
- 第5章 - 実体としての無限なものを認めるピュタゴラス派の説とその批判、無限な感覚的物体は存在しない
- 第6章 - 無限なものは可能的に存在する、加えることによる無限と分割することによる無限、無限とは何か
- 第7章 - 諸種の無限なもの、数における無限と量における無限、空間的な大きさ及び時間の長さに関する無限と運動の関係、無限は四原因のいずれに関するものか
- 第8章 - 無限なものを現実的に存在するとする諸見解に対する批判
- 第4巻 - 場所、空虚、時間。全14章。
【場所について】- 第1章 - 場所の存否、それが何であるかについての諸難問
- 第2章 - 場所とは何か、それはものの質料なのか形相なのか
- 第3章 - 何ものかの内にあるということの諸義、ものはそのもの自らの内に存在するのか、場所は場所の内に存在するのか
- 第4章 - 場所の本質についての4つの見解、場所の定義
- 第5章 - この定義の補説、天界の外にこれを包む場所は存しない、第1章の諸難問に対する解答
【空虚について】 - 第6章 - 空虚についての他の人々の諸見解
- 第7章 - 一般に「空虚」という語で何が考えられているか、空虚の存在を肯定する諸説への反論
- 第8章 - 物体から離れて独立な空虚は存在しない、物体によって占められる空虚も存在しない
- 第9章 - 空虚はいかなる物体の内部にも存在しない
【時間について】 - 第10章 - 時間の存否についての諸難問、時間についての種々の見解
- 第11章 - 時間とは何か、時間と運動との関係、時間の定義、時間と「今」との関係
- 第12章 - 時間の諸属性、ものごとが時間の内にあるということの諸義
- 第13章 - 時間の過去・現在・未来と時間関係の諸語(いつか、やがて、先程、昔、突然など)の意味
- 第14章 - 時間論補稿 --- 時間と意識との関係、時間と天体の円運動との関係など
- 第5巻 - 諸運動の分類。全6章。
- 第1章 - 運動・転化の研究のための予備的諸考察、転化とその分類
- 第2章 - 運動の分類、動かされ得ないもの
- 第3章 - 「一緒に」「離れて」「接触する」「中間に」「継続的」「接続的」「連続的」の意味
- 第4章 - 運動が一つと言われる、その多くの意味
- 第5章 - 運動の反対性
- 第6章 - 運動と静止の反対性、「自然的」「反自然的」な運動と静止の反対性
- 第6巻 - 分割と転化、移動と静止。全10章。
- 第1章 - 連続的なものは不可分なものから成ることはできず、常に可分的である
- 第2章 - 前章の詳細
- 第3章 - 「今」は不可分なものであり、どんなものも「今」においては運動も静止もしていない
- 第4章 - 転化するものは全て可分的である、運動は時間と諸部分の運動とに関して可分的である、時間・運動・現に運動している状態・運動しているもの・運動の領域は全て同じように可分的である
- 第5章 - 転化し終えたものは転化し終えたまさにその時には転化の終端の内にある、転化し終えるのは不可分な時としての「今」においてである、転化するものにも転化する時間にも最初というものが無い
- 第6章 - 転化するものは転化の直接的な時間のどの部分においても転化している、転化しているものはより先に転化し終えたのであり転化し終えたものはより先に転化していた
- 第7章 - 運動するもの、距離、時間の有限と無限
- 第8章 - 停止の過程と静止について、運動するものがその運動の時間において静止しているあるものに対応していることは不可能である
- 第9章 - ゼノンの運動否定論への論駁
- 第10章 - 部分の無いものは運動し得ない、円環的な移動を除いて転化は無限でありえない
- 第7巻 - 動者。全5章。
- 第1章 - 動くものは全て何かによって動かされる、どんな他のものによっても動かされることのない第一の動かすものがある
- 第2章 - 動かすものと動かされるものとは接触していなければならない
- 第3章 - 性質の変化は全て感覚的諸性質に関する
- 第4章 - 運動の速さについての比較
- 第5章 - 力が重いものを動かす働きに関する原理
- 第8巻 - 第一動者(不動の動者)と宇宙。全10章。
- 第1章 - 運動は常にあったし常にあるだろう
- 第2章 - 前章に反対する見解への反駁
- 第3章 - 時には運動し時には静止している事物がある
- 第4章 - 動くものは全て何かによって動かされる、特に自然的に動くものについて
- 第5章 - 第一の動かすものは他のものによって動かされるのではない、第一の動かすものは動かされ得ないものである
- 第6章 - 第一の動かすものは永遠で一つである、それは付帯的にさえ動かされない、第一の動かされるものも永遠である
- 第7章 - 移動が第一の運動である、移動以外のどんな運動・転化も連続的でない
- 第8章 - 円運動のみが連続的で無限である
- 第9章 - 円運動が第一の移動である、以上のことの若干の再確認
- 第10章 - 第一の動かすものは部分も大きさも持たず宇宙の周辺にある
内容
各巻概略
【第1巻】 kinesis(キネーシス、“運動”[3])やmetabole(メタボーレ、変化)が可能であるためにはどのような原理が必要なのか、という問いが立てられる。そしてアリストテレス以前の哲学者たちの説が検討され、eidos(エイドス、形相)、steresis(ステレーシス、欠如態、hylee(ヒュレー、質料)の3つの原理が運動や変化を説明するのに必要でありかつ十分である、と述べる。
【第2巻】 ここでアリストテレスは自然学の対象と方法を規定する。まず自然物を「運動や静止の原理をそれ自体のうちにもつもの」と定義する。次に「〜のphysis」(「 〜のフュシス(自然)」)という表現の意味を分析し、それは「〜のヒュレー(質料)」と「〜のエイドス(形相)」の2つの意味でありうるとし、エイドスのほうが優先されるべきだ、と述べる。そして、ヒュレーとエイドスからなるものとして自然物を研究するのが自然学だ、とする。
また原因という概念が分析される。原因の中でも基本的なものとして質料因、形相因、目的因、始動因の4つを挙げ(四原因説)、さらに、派生的なそれとして付帯原因、偶然などにも言及し、自然学というのは上記基本的原因のすべてを解明すべきだ、と述べる(なお、目的因を認めないような機械論的考え方には反対する)。
【第3巻、第4巻】 運動の概念と、それに関係する連続・無限・場所・空虚・時間等の概念について考察する。
【第5巻】kinesisに関する問題
【第6巻】連続性の問題(ゼノンのパラドックス など)
【第7巻】kinesisに関する問題
【第8巻】kinesisするものは何かによって動かされるという事実から、その何かを動かした何かを遡ってゆけば、不動の動者(全ての運動を引き起こした究極の原因で、それ自身は動かないもの)が存在する、と論証する。
_____
https://www.iwanami.co.jp/moreinfo/092771+/top2.html




存在と時間 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%98%E5%9C%A8%E3%81%A8%E6%99%82%E9%96%93
『存在と時間』(そんざいとじかん、"Sein und Zeit"、1927年)は、ドイツの哲学者マルティン・ハイデッガーの主著。「ものが存在するとはどういうことか」というアリストテレス『形而上学』以来の問題に挑んだ著作であるが、実際に出版された部分は序論に記された執筆計画全体の約3分の1にすぎない。『存在と時間』は実存主義や構造主義、ポスト構造主義などに影響を与えた。…
序論第2章8節「論証の構図」で明らかにされる『存在と時間』の全体的構成の概要はおおむね以下の通りである。
第1部 現存在の解釈と時間の解明
第1編 現存在の基礎分析
第2編 現存在と時間性
第3編 時間と存在
第2部 存在論の歴史の現象学的解体
第1編 カントの時間論について
第2編 デカルトの「我あり」と「思う」について
第3編 アリストテレスの時間論について
このうち、実際に書かれたのは第1部第2編までにすぎず、そこで論じられているのは現存在と時間性についてである。序論以降ハイデッガーが何度も言明している「存在一般についての問い」に関する考察が書かれるべき〈本論〉は第1部第3編「時間と存在」という、書名自体にも似た標題をもつ章であると考えられるが、そこでハイデッガーが何を書くつもりであったのか、なぜそこへ至る前に中断されてしまったのかは長いあいだ謎とされてきた。
ナトルプ報告
ハイデッガー自身の証言などから、1923年には『存在と時間』の草稿が書かれていたことが知られていたが、その所在は長らく不明だった。同年にハイデッガーはフライブルク大学の非常勤講師からマールブルク大学への異動が決まっており、そのさいに現在執筆中の著書の概要をまとめたものを審査論文として提示するよう要求され、『アリストテレスの現象学的解釈──解釈学的状況の提示』と題した論考をパウル・ナトルプへ提出していた(通称「ナトルプ報告」)。この論考が『存在と時間』の初期草稿に当たるのではないかと推測する向きと、「アリストテレスの現象学的解釈」と『存在と時間』がいかなる関係をもつのか疑問視する向きとがあったが、この「ナトルプ報告」も行方不明となっていたため結論は出なかった。しかし1989年、マールブルク大学と同時期にやはりハイデッガーを招聘しようとしていたゲッティンゲン大学のゲオルク・ミッシュに提出した同内容の論考が発見され、その内容から「ナトルプ報告」が『存在と時間』の初期草稿であるとする推測の正しかったことが証明された。そこで明らかにされている本論はアリストテレスの読解を通した古代ギリシアから中世を経て近代に至る存在論、ひいては西洋哲学全体の読み直しであり、問題の第1部第3編「時間と存在」はこの歴史的考察の基盤となるものであること、また序論はその準備段階にすぎないものであること、したがって実際に刊行された『存在と時間』は長大に膨れ上がった序論が本論へたどりつく前に中断されたものであることなどが明らかになった[1]。
____