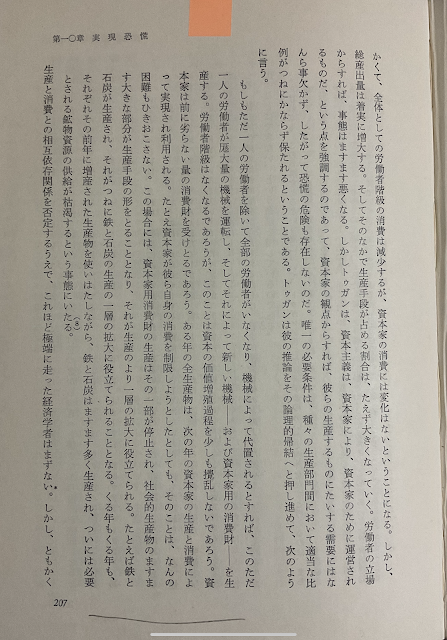時に、初春(しよしゆん)の令月(れいげつ)にして、気淑(よ)く風和(や は ら)ぎ、梅は鏡前(きやうぜん)の粉(こ)を披(ひら)き、蘭(らん)は 珮後 (はいご)の香(かう)を薫(かをら)す。
天平二年正月十三日に、師(そち)の老(おきな)の宅(いへ)に萃(あつ)まりて、宴会を申(ひら)く。時に、初春(しよしゆん)の令月(れいげつ)にして、気淑(よ)く風和(やはら)ぎ、梅は鏡前(きやうぜん)の粉(こ)を披(ひら)き、蘭(らん)は珮後(はいご)の香(かう)を薫(かをら)す。加之(しかのみにあらず)、曙(あけぼの)の嶺に雲移り、松は羅(うすもの)を掛けて蓋(きにがさ)を傾け、夕の岫(くき)に霧結び、鳥はうすものに封(こ)めらえて林に迷(まと)ふ。庭には新蝶(しんてふ)舞ひ、空には故雁(こがん)帰る。ここに天を蓋(きにがさ)とし、地を座(しきゐ)とし、膝を促(ちかづ)け觴(かづき)を飛ばす。言(こと)を一室の裏(うら)に忘れ、衿(えり)を煙霞の外に開く。淡然(たんぜん)と自(みづか)ら放(ひしきまま)にし、快然と自(みづか)ら足る。若し翰苑(かんゑん)にあらずは、何を以(も)ちてか情(こころ)を述※1(の)べむ。詩に落梅の篇を紀(しる)す。古(いにしへ)と今(いま)とそれ何そ異(こと)ならむ。宜(よろ)しく園の梅を賦(ふ)して聊(いささ)かに短詠を成すべし。
※1:「述」は原文では「手」遍+「慮」
-----------------------------------------------
天平二年正月十三日に、大宰師の大伴旅人の邸宅に集まりて、宴会を開く。時に、初春の好き[良き]月にして、空気はよく風は爽やかに、梅は鏡の前の美女が装う白粉のように開き、蘭は身を飾った香のように薫っている。のみにあらず、明け方の嶺には雲が移り動き、松は薄絹のような雲を掛けてきぬがさを傾け、山のくぼみには霧がわだかまり、鳥は薄霧に封じ込められて林に迷っている。庭には蝶が舞ひ、空には年を越した雁が帰ろうと飛んでいる。ここに天をきぬがさとし、地を座として、膝を近づけ酒を交わす。人々は言葉を一室の裏に忘れ、胸襟を煙霞の外に開きあっている。淡然と自らの心のままに振る舞い、快くそれぞれがら満ち足りている。これを文筆にするのでなければ、どのようにして心を表現しよう。中国にも多くの落梅の詩がある。いにしへと現在と何の違いがあろう。よろしく園の梅を詠んでいささの短詠を作ろうではないか。
-----------------------------------------------
この漢詩風の一文は、梅花の歌三十二首の前につけられた序で、書き手は不明ですがおそらくは山上憶良(やまのうへのおくら)の作かと思われます。
その内容によると、天平二年正月十三日に大宰府の大伴旅人(おほとものたびと)の邸宅で梅の花を愛でる宴が催されたとあります。
このころ梅は大陸からもたらされたものとして非常に珍しい植物だったようですね。
当時、大宰府は外国との交流の窓口でもあったのでこのような国内に無い植物や新しい文化がいち早く持ち込まれる場所でもありました。
この序では、前半でそんな外来の梅を愛でる宴での梅の華やかな様子を記し、ついで梅を取り巻く周囲の景色を描写し、一座の人々の和やかな様を伝えています。
そして、中国にも多くの落梅の詩があるように、「この庭の梅を歌に詠もうではないか」と、序を結んでいます。
我々からすると昔の人である旅人たちが、中国の古詩を念頭にして「いにしへと現在と何の違いがあろう」と記しているのも面白いところですよね。
この後つづく三十二首の歌は、座の人々が四群に分かれて八首ずつ順に詠んだものであり、各々円座で回し詠みしたものとなっています。
後の世の連歌の原型とも取れる(連歌と違いここでは一人が一首を詠んでいますが)ような共同作業的雰囲気も感じられ、当時の筑紫歌壇の華やかさが最もよく感じられる一群の歌と言えるでしょう。

令月(レイゲツ)とは - コトバンク
デジタル大辞泉 - 令月の用語解説 - 1 何事をするにもよい月。めでたい月。「嘉辰(かしん)令月」2 陰暦2月の異称。
令月(れいげつ)の意味 - goo国語辞書
れいげつ【令月】とは。意味や解説、類語。1 何事をするにもよい月。めでたい月。「嘉辰 (かしん) 令月」2 陰暦2月の異称。
嘉辰令月(かしんれいげつ)の意味・使い方 - 四字熟語一覧 - goo辞書
嘉辰令月(かしんれいげつ)の意味・使い方。めでたい月日のこと。よい日とよい月の意。 ▽「嘉」も「令」も、よい意。「辰」は日の ...
【備忘録 〜令和〜🖋】
調べてみた!
『令和』の語源はどこからか?_φ(・_・メモメモ
万葉集巻五
梅花の歌三十二首、并せて序
「初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香。」
初春の令月(れいげつ)にして、氣淑(よ)く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後(はいご)の香を薫(かをら)す。
令月
2月の意
冬に枯れた草花が再び芽生え始める季節
令和:復活
「令和」の典拠とされる『万葉集』が更に参照していたのは後漢の張衡の賦だろうが、この張衡という人、古代中国科学史では天文学の観測器具「渾天儀」を最初に作ったり、地震計を作った人としても知られている。巡り巡って、日本の年号の出典となってしまったというのは、何というか面白い。
https://www.kyotocity.net/diary/2019/0401-reiwa/
『萬葉集』(萬葉集)の「梅花謌卅二首」并序より。
「梅花歌三十二首」に序を合わせる、つまり、この後に続く歌の序文です。
梅花謌卅二首并序
天平二年正月十三日萃于帥老之宅申宴會也于時初春令氣淑風和梅披鏡前之粉蘭薫珮後之香加以曙嶺移雲松掛羅而傾盖夕岫結霧鳥對縠而迷林庭舞新蝶空歸故鴈於是盖天坐地促膝飛觴忘言一室之裏開衿烟霞之外淡然自放快然自足若非翰苑何以攄情詩紀落梅之篇古今何異矣宜而賦園梅聊成短詠
『紀州本萬葉集巻第五』
「国立国会図書館デジタルコレクション」 より
1941年(昭和16年)の紀州本複写を底本として手打ちしたため、他本とは異なる箇所あり。
紀州本では「于時初春令氣淑風和梅披鏡前之粉蘭薫珮後之香」となっていますが、「于時初春令月氣淑風和梅披鏡前之粉蘭薫珮後之香」。
この後、大貳紀卿らの歌に続きます。
江戸時代中期~の国学者である本居宣長の『萬葉集略解』より解説を引いておきますと、
梅花歌三十二首并序
目録に太宰師大伴卿宅宴梅花云云と有り。天平二年正月十三日。萃二于帥老之宅一。申二宴會一也。于レ時初春令月。氣淑風和。梅披二鏡前之粉一。蘭薫二珮後之香一。加以曙嶺移レ雲。松掛レ羅而傾レ蓋。夕岫結レ霧。鳥レ對穀而迷レ林。庭舞二新蝶一。空歸二故雁一。
帥老は大伴卿を言ふ。此序は憶良の作れるならんと契沖言へり。さも有るべし。鏡前之粉は、宋武帝の女壽陽公主の額に梅花落ちたりしが、拂へども去らざりしより、梅化粧と言ふ時起これりと言へり。此に由りて言へるなり。珮後之香は屈原が事に由りて言へり。傾蓋は松を偃蓋など言ふ事、六朝以降の詩に多し。對穀は宋玉神女賦に、動二霧穀一以徐歩と有り。穀はこめおりのうすものなり。さて霧を穀に譬へ、穀を霧に譬へて言へり。契沖は對は封の誤かと言へり。
『萬葉集略解』
太宰師として大宰府に着任していた大伴旅人宅での宴会。
ただし、この序文は山上憶良が作ったのであろうと、やはり江戸時代中期の国学者である契沖が言っている、としており、筆者である本居宣長も同意しています。
山上憶良は万葉の時代を代表する歌人の一人で、筑前守として筑紫に着任していました。
そのため、大宰府周辺で歌を多く詠んでいます。
また、本居宣長は「鏡前之粉」の話を引き合いに出し、宋武帝(南朝宋の武帝劉裕)の名前も挙げています。
このエピソードを見ると、万葉の時代の日本に南北朝時代の中国の話が伝わっていた可能性もあるでしょうね。
歸田賦
張衡
遊都邑以永久無明畧以佐時徒臨川以羡魚俟河淸乎未期感蔡子之慷慨感蔡子之慷慨從唐生以決疑諒天道之微昧追漁殳以同嬉超埃塵以遐逝與世事乎長辭於是仲春令月時和氣淸原隰鬱茂百草滋榮王睢鼓翼倉庚哀鳴交頸頡頏關關嚶嚶於焉逍遥聊以娛情爾乃龍吟方澤虎嘯山丘仰飛繊繳俯釣長流觸矢而斃貪餌呑鉤落雲間之逸禽懸淵沈之魦鰡于時曜靈俄景以繼望舒極盤遊之至樂雖日夕而忘劬感老氏之遺誡將廻駕乎蓬蘆彈五絃之玅指詠周孔之圖書揮翰墨以奮藻陳三皇之軌模苟縱心於域外安知榮辱之所如
『文選正文巻之三』
「国立国会図書館デジタルコレクション」 より
明治3年(1870年)の宝文堂版を底本として手打ちしたため、他本とは異なる箇所あり。
本によっては「倉庚」は「鶬鶊」。ウグイス(鶯)の意味。
張衡は後漢時代の人。
『歸田賦』(帰田賦)は南北朝時代の蕭統(昭明太子)が編纂したとされる『文選』に収められました。
日本の古人も目を通したかもしれませんね。
恥ずかしながら張衡を知らずwikiを覗いただけですが、あまりの経歴の持ち主に驚きました。
政治家として優秀で30代のうちに世界最初の水力の渾天儀(天球儀)、水時計、世界初の地動儀(地震感知器)発明をしたばかりでなく、文学にも才あり功績を収めているなんて超人じゃありませんか…すごい人だ…
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%B5%E8%A1%A1_(%E7%A7%91%E5%AD%A6%E8%80%85)
経歴
没落した官僚の家庭に生まれた。祖父張堪は地方官吏だった。青年時代洛陽と長安に遊学し、太学で学んだ。永元十四年(102年)、張衡24歳の時,南陽郡守の幕僚(南陽郡主簿)となった。永初元年(107年)には、29歳で洛陽を描いた「東京賦」と長安を描いた「西京賦」を著した(これらを総称して「二京賦」という)。当初は南陽で下級官吏となった。永初五年(111年)、張衡34歳の時、京官の郎中として出仕した。元初三年(116年)張衡38歳の時、暦法機構の最高官職の太史令についた。建光二年(122年),公車馬令に出任した。永建三年から永和元年(128年-136年)の間、再び太史令を勤めた。最後は尚書となった。
30歳くらいで、天文を学び始め、「霊憲」「霊憲図」「渾天儀図注」「算罔論」を著した。彼は歴史と暦法の問題については一切妥協しなかった為、当時争議を起こした。順帝の時代の宦官政治に我慢できず、朝廷を辞し、河北に去った。南陽に戻り、138年に朝廷に招聘されたが、139年に死去した。文学作品としては他に、「帰田賦」「四愁詩」「同声歌」がある。
張衡は力学の知識と歯車を発明に用いた。彼の発明には、世界最初の水力渾天儀(117年)、水時計、候風と名付けられた世界初の地動儀(132年)、つまり地震感知器などがある。地動儀は500キロメートル離れた地点の地震を感知することができた。ある日、地動儀の設置場所からみて西北方向の地震の揺れを感知したが、人々は少しの揺れも感じないことがあった。一部の人は地動儀の誤りを疑った。しかし数日後、甘粛から急使が来て、地震の発生のことを報告した。このことがあって以来、地動儀の正確性を疑うことはなくなったという[1]。
そのほか、彼は円周率も計算し、2500個の星々を記録し、月と太陽の関係も研究した。著書の「霊憲」において月を球形と論じ、月の輝きは太陽の反射光だとした。「霊憲」には以下の記述がある。
また続いて以下の記述があり、
張衡が月食の原理を理解していたことがわかる。
月の直径も計算したとされ、太陽の1年を、365日と1/4と算出した。小惑星(1802 張衡)には、彼の名がつけられている。なお、彼の天文の研究や地震計の発明には、2世紀に入り、後漢に天災が多発しだした時代背景がある。