【小浜逸郎】福沢諭吉は完璧な表券主義者だった(その1)
From 小浜逸郎@評論家/国士舘大学客員教授
このたび、5月にPHP研究所より『福沢諭吉 しなやかな日本精神』を上梓する運びとなりました。 宣伝を兼ねて、その一端を紹介させていただきます。
福沢が、明治初年代、 欧米列強の餌食にならないよう、 日本の自主独立を切に願っていたことは、 よく知られています。 しかし、彼が経済に対して どういう考え方をしていたかは、 ほとんど知られていません。 世の福沢論者も、あまりこの領域には 手を染めてこなかったようです。 このたび福沢論を書くにあたって、 彼の一連の経済論文にも 丁寧に目を通してみたのですが、 驚いたことに経済に対する彼の見識は、 現代の凡百の経済学者やエコノミストより はるかに高いものがありました。 ことに、明治11年に発表された 『通貨論 第一』では、 まだ本位貨幣制度も整っていない時代に、 それを飛び越して、 現代の管理通貨制度と完全に等しい考え方を 採っているのです。 福沢はまず、通貨の本質について、 それは単なる品物の預かり手形と同じであると 言い切ります。
これは最近、三橋貴明氏が強調している、 「貨幣は債権と債務の記録であり、借用証書である」 という本質規定とまったく同じです。 また、その「預り手形」として 金銀を用いようが紙を用いようが、 その機能において何ら変わるところがない とも言い切ります。
こちらも、最近、中野剛志氏が、 貴金属に価値の本源があると 錯覚してきた長きにわたる慣習(金属主義) が無意味であって、 貨幣はただ価値を明示する印(表券主義) と指摘した、 その議論とぴったり一致しています。 福沢は、前者の場合を次のような たいへんわかりやすい例で説明しています。
《たとえばここに、不用の米十俵を所持して これを綿に易えんと思えども、 差向き気に叶う綿の品物もなし、 さりとて、所持の米は不用なるゆえ、 まずこれを近処の綿屋に渡して 代金を受け取りおき、 追ってその店に綿の上物あるときに至りて 先に受け取たる代金をもって綿を買えば、 つまるところは米と綿と交易したる訳にて、 その代金はしばらくの間綿屋より受け取たる 米の預り手形に異ならず。(中略) この預り手形に金銀を用いれば 何程の便利あるや、 紙を用いれば何程の不便利あるや、 いささかも区別あるべからず。 ただ、その約束の大丈夫なるとしからざる との一事心配なるのみ。 この一段に至りて、金銀は人の苦痛の塊 (掘り出して精錬し鋳造する労働力 が込められている――引用者注) なるが故に、 これを質に取りて大丈夫なりと言わんか、 決して頼みにするに足らず。 紙にてもまた大丈夫なる訳あり。》
福沢は、取引においては、 互いの需要を満たすために 必ず時間差や空間差が介入してくるので、 そのために「預り手形」(約束の証書)が どうしても必要とされるというところに 通貨の本質を見ているわけです。 中略部では、それが不特定多数との間で 流通性を持てば、 通貨となるのだと説いています。 まことにその通りという他はありません。 ふつう貨幣のはたらきとして列挙される、 支払いの手段とか、蓄財の手段とか、 価値の尺度とか、富を誇示するためなどは、 あくまでその「機能」であって、 「本質」ではありません。 ところで引用部分の最後の指摘から、 それでは紙でも大丈夫だという信用 はどこから得られるのか という問いが出てきます。 福沢はこれに対して、 商売取引が現に繁多に 行われていさえすれば 世人はみな貨幣を大切に思うので、 その現実こそが信用を実現させている と答えます。
《しかりしこうしてその大切なる由縁は、 品の質にあらずして その働きにあるものなり。 今、金銀と紙とその質は異なれども、 これを貨幣に用いて 働きに異なる所あらざれば、 紙を大丈夫なりと言いて 毫も異論あるべからず。》
貨幣が大切であるポイントは、 品質の如何ではなく働きにこそある というこの指摘は、コロンブスの卵です。 真理を鋭く簡潔に言い当てていますが、 なかなかこううまくは 表現できないものです。 観点は違いますが同様の把握は この論考の後の部分にも出てきます。 世間の人々は千両箱が積まれていると すごい金持ちだというが、 本物の商人はそういう見方をせず、 千両が運用されずに一年間寝かせてあると 百両か二百両は損してしまうと考える。 活発に商取引や事業が行なわれている その実態こそ、 金持ち(豊か)である証拠なので、 だから元気旺盛な商人ほど、 帳簿を調べてみれば たくさん借金をしていることがわかる、と。 帳簿では貸方、借方のダイナミズムに 目をつけなくてはならないという、 当然と言えば当然の指摘ですが、 これなどは、 財政収支の黒字化ばかり気にして、 日本経済をひどい不活発に追いやっている 現在の財務省にぜひ 聞かせてやりたいくだりです。 しかし、と反論があるでしょう。
第一に、そもそも一つの閉ざされた 共同体市場(たとえば一国内)で 紙を使って商売取引が繁多になるためにこそ まず紙に対する信用が先立つのではないか。 それはどうして得られるのか。
第二に、貴金属に対する尊重の感情は 根深く人情として根付いているので、 簡単に金属主義を超えることは 難しいのではないか。 これらについても福沢は答えているのですが それは後述しましょう。
http://blog.goo.ne.jp/kohamaitsuo https://38news.jp/economy/11837 【小浜逸郎】福沢諭吉は完璧な表券主義者だった(その2) 小浜逸郎 From 小浜逸郎@評論家/国士舘大学客員教授
続いて彼は、金銀よりも紙を用いることの 便利さを列挙していきます。
第一、紙幣は運搬に便利。
第二、人の目に立たないので盗賊に会いにくい。
第三、金銀を紛失してしまうと、 再び「苦痛の塊」を苦労して作らなくてはならないが、 紙ならば、本人の損害だけで、 経済活動全体には影響がない。
第四、紙には偽札の危険があるという人がいるが、 それは印刷技術を高めればよいので、 金銀の場合も同じ偽造の危険はいくらでもある。
第五、紙幣は紙なので粗末に扱い、 浪費乱用の危険があるという人がいるが、 それは習慣の問題で、 すべて紙幣を用いる習慣が定着しさえすれば、 それを大切にするようになる。
この最後の指摘について、 福沢は、まだ中津にいた少年時代の 面白い経験を記しています。 夜分、使いに出されて、 一分銀か二朱金で支払おうとすると、 店の主人から、暗くて真贋を見極めにくいので、 札(藩札)の方がありがたいと言われたというのです。 商人が京大阪へ上った場合には、 札を両替して銀で取引したのでしょうが、 中津藩内では、藩札が重宝されて出回っていたわけです。 ここから、一藩(一国)の統治が安定していれば 信用が生まれてくるということが示唆されます。 次に福沢は、金銀は量に制限があるため むやみに通用させることはできないが、 紙幣の場合、政府の都合でいくらでも増刷できるから、 物価騰貴を抑えられないという反論に対して、 いかにももっともだが、と断ったうえで、 次のように答えます。 それは政府を信じないところから生まれてくる議論で、 初めから政府を疑うなら、紙幣の発行に限らず、 いくらでも疑いの材料はある。 年貢のつり上げ、小判の質の悪化、新紙幣の発行、 私有地の官有化など、 現に旧幕府は人民の信用を落とすことを いくらでもやってきた。 自分はともかく政府を信用する立場をとった上で 紙幣発行がいかに便利かという論点で議論を進める。
このように、議論の原則をはっきりさせるわけです。 するとここでも、どうしてその信用が得られるのか という議論が蒸し返されます。 先の中野剛志氏は、政府が徴税権を持ち、 それを国民が現金紙幣で納めることを 政府が承認しているという事実が、 一国の紙幣信用を生み出す要因である という説を打ち出しています (『富国と強兵』東洋経済新報社)。 これに対して、福沢は、 旧藩時代と違って今日は全国一政府の時代なのだから、 そこが発行する紙幣は拒むも拒まないも、 安心するも信用しないも、 現に毎日盛んに商取引が行なわれている以上、 その紙幣を使う以外他に方法がないのだという点を 強調しています。 福沢は、現に商取引において一紙幣を使うという 合意が遅滞なく成立している「事実」のほうを 信用成立の原因としてやや重く見ているわけです。
中野氏と福沢、 二人の議論は対立しているのでしょうか。 そうではありません。 租税を現金紙幣で納めることを 政府が承認しているという事実は、 全国一政府の下に、経済人としての人民の 国民意識が統合されていることそのものの証しです。 逆に、一つの通貨によって毎日盛んに 商取引が行なわれていることは、 人民がその国の統一性を信用していることの証しです。 両者は同じことを違った角度から視ているにすぎません。 これは、米本位制による物納でも、 預金通帳からの引き落としという 書類上の納入の場合でも同じです。 そもそも信用とは、 AがBを信用することだけを意味するのではなく、 常にそれを受けるBの側からもAを信用する という相互性の上に成り立つものです。 Aを国民、Bを政府とすれば、 Bに対するAの信用は、 現にBが発行した通貨を用いて 盛んに経済活動をやっているという 事実によって示され(福沢説)、 Aに対するBの信用は、 現金紙幣を租税徴収の手段として認めているという 事実によって示されます(中野説)。
また福沢は、開国以降、 国際的取引では金銀が本位通貨となるので、 紙幣の発行に関して警戒すべきことを、 実例を挙げて示しています。 まず国内での物価高は、 不換紙幣の名目として高くなっているだけで、 金銀との関係では、 逆に低いこともありうると注意を促します。 もしそういう時期に輸出をすると、 その輸出品は、より少ない量の金銀としか 交換できないので、 それで得た金銀は、国内で紙幣と両替すれば、 値打ちの低い物品と同じということになります。 つまり損をしてしまうわけです。 これは、現在の為替変動相場制における円高期 (少ない額のドルとしか交換できない時期) の輸出と似ていますね。 福沢は、幕末期にこういうことになったのは、 わが国で紙幣と同じ名目価値しか持たない 一分銀を通用させ、 金と銀との実質的な割合について おろそかだったからだと指摘します。 その上で、これを防ぐには、 万国普通の相場に従って金と銀との価値の比率を定め、 その貨幣の名目に準じて紙幣を発行するしかない という提案をします。 癪な話ではあるが、開国してしまった以上、 通貨問題は国際標準に合わせざるを得ない というわけですね。 この後『通貨論 第一』の白眉となります。
https://38news.jp/economy/11850 【小浜逸郎】福沢諭吉は完璧な表券主義者だった(その3) 小浜逸郎 From 小浜逸郎@評論家/国士舘大学客員教授
さて『通貨論 第一』の白眉に触れましょう。 福沢は、国内での通貨の安定を保つ方法にも 言及しています。 紙幣と同時に少し金貨銀貨を混ぜて通用させ、 これを通用の目安とします。 そして絶えず通貨量に対する監視と コントロールを怠らないようにします。 金銀の一円と紙幣の一円とがだいたい同様に 通用している時には通用している紙幣量は 適切であると判断し、 紙幣の相場が金銀に比べて下落した時には、 紙幣過多とみて回収するというのです。 この場合金銀は物価の代表を意味することになり、 ただの商品として扱われていることになります。 これは当時のインフレ対策としては、卓抜に思えます。 前回、福沢が金本位制度を飛び越して、 現在は当然とされている管理通貨制度の考え方を 先取りしていたと書きました。
ここで本位貨幣制度と管理通貨制度の違いについて 簡単に説明を加えておきましょう。 金本位制とは、一国の金の保有量に従って 通貨量を決める制度で、 商品価値もこれによって決まります。 本来は金を通貨として流通させる建前ですが、 実際には一国の経済活動にとって 金の量が十分とは限らないので、 金と交換可能な兌換紙幣や補助貨幣を発行して 間に合わせる形を取ります。 そのため政府は常に相当量の金を 準備しておかなくてはなりません。 それが政府に対する国民の信用を保証するからです。 紙幣は国際的には通用しませんから、 国際取引は普通、金で行われます。 すると、金の保有高の多少が一国の経済力にとって 決定的となり、それによって物価は 常に不安定にさらされます。 稀少にしか存在しない金の争奪戦も起きます。 先に述べた金属主義とは、 こうした貴金属に価値決定の基準を置く考え方で、 人々の経済的価値観は、 金銀という「モノ」に依存することになります。 どの国もずっと昔から この社会心理に支配されてきましたが、 これは、貨幣というものの本質を 理解しない間違ったあり方です。 経済学者のケインズは、 福沢がこの論考を書いてから約50年後に、 金本位制復活を唱えたチャーチルを批判して、 「金本位制度は未開の遺物だ」と喝破しました。 これに対して管理通貨制度は、 「モノ」の保有にいっさい依存せず、 通貨当局(政府及び中央銀行)が、 物価、経済成長率、雇用状態、国際収支など、 自国の経済情勢を常ににらみながら、 それに応じて通貨の発行量を決める制度です。 この制度は、貨幣価値が貴金属などの 「モノ」に拘束されるのではなく、 経済活動をする人々(政府も含む)の 相互信用にかかっているという考え(表券主義) を徹底させたものです。 この制度では、原則として通貨当局は いくらでも通貨を発行できます。
国民が政府・中央銀行を大筋で信用し、 政府・中央銀行が極端なバカ政策に走らない限り、 この制度が揺らぐことはありません。 これは貨幣価値の源は「モノ」に宿るのではなく、 人間どうしの関係のあり方に宿っている という正しい経済哲学が基本になっています。 福沢は、管理通貨制度の原理を周囲に先駆けて 展開していたばかりではありません。 本当は金準備は必要ないのだが、 長きにわたる習慣からくる民衆の人情を忖度して、 若干の金準備は必要だとまでことわっているのです。 そのフォローの手厚さには舌を巻かざるを得ません。
こういう考え方を 当時の政府の財政事情の苦しさに鑑みて、 楽観主義と批判する経済学者もいるようですが、 楽観主義かそうでないかといった政策論的な批評は 問題になりません。 福沢がここでなしていることは、 通貨とこれを管理する政府との関係に関する 「原理」の展開であり、 それゆえ、普遍的に当てはまる理論なのです。 少し長くなりますが、 ここはぜひ原文を味わっていただきましょう。
《かくのごとく内外の事情に注意して、 紙幣と金銀貨との間に大なる差もなくして いよいよ安心の点にあれば、 準備金はほとんど不用のものなり。 元来通貨の行わるるゆえんは、 前にも言えるごとく、 開けたる世の中に欠くべらざるの効能あるに よってしかるものなれば、 今世間の商売に定めて入用なる数の紙幣を 発行するときは、 その通用は準備の有無に関係あるべからず。》
《しかりといえども、余は初めにほとんど不用なり と言えり。 このほとんどの字は、 ことさらにこれを用いたるものなれば、 等閑に看過すべからず。 準備の正金は、経済論において事実不用なれども、 いかんせん今の不文なる通俗世界においては、 千百年来理屈にかかわらずして 金銀を重んずるの習慣を成し、 ただ黄白の色を見て笑みを含むの人情なれば、 いかなる政府にても、 紙幣を発行して絶えて引き替えをなさざるのみならず、 公然と布告して政府の金庫には一片の正金なし、 この紙幣は百年も千年も金銀に替えること あるべからずと言わば、 人民は必ず狼狽して、 事実入用の紙幣を厄介のごとくに思い、 様々にこれを用いんとして無用の品物を買入れ、 物価これがために沸騰して紙幣も いわれなく地に落つることあるべし。 これを西洋の言葉にてパニクと言う。 根も無きことに驚き騒ぐという義にして、 はなはだ恐るべき変動なり。 ゆえに愚民の心を慰むる為には 多少の準備金なかるべからず。 これ即ちそのほとんど不用にして 全く不用ならざる由縁なり。》
このほかに準備金(正金)が必要なケースとして、 福沢は、不時の災害や飢饉、戦争などのために 物資が不足して輸入に頼らなければならない時 を挙げています。 結局、政府が金銀をいくらか準備しておく必要は、
①紙幣発行額の目安として市場に少し混入させるため、
②金属主義に取りつかれた「愚民」の不安を鎮めるため、
③不時の異変に遭遇した時の輸入のため、
の三つということになります。
完全な管理通貨制度が定着している現在では、
①は主として日銀の公開市場操作 (公債の売り買いによる金利の調整)、
②は不要、
③は外貨(ドル)準備残高の維持 によってそれぞれ保障されているわけです。 この段階では、金銀などの貴金属は、 貨幣としての特権的地位を保てず、 ただの「商品」に下落しています。 こうして、140年も前の日本で、 経済の専門家でもない一人の思想家が、 貨幣の本質と妥当な通貨制度のあり方について、 ここまで考えていたのです。 福沢は、経済に関しては、 おそらくアダム・スミスとJ・S・ミル くらいしか読んでいなかったでしょう。 しかもこの二人はいずれも金属主義者でした。 「経済学」など学ばなくても、 社会を正確に見る目さえあれば、 経済についてこれだけのことができるのです。 現代にも多くの福沢が甦ってほしいと 切望するゆえんであります。
【小浜逸郎からのお知らせ】 ●新著『福沢諭吉 しなやかな日本精神』 (PHP新書)は5月15日に発売です。 どうぞご期待ください。 ●『表現者』76号「同第29回──福沢諭吉」 ●月刊誌『Voice』3月号「西部邁氏追悼」 ●『表現者クライテリオン』第2号 「『非行』としての保守──西部邁氏追悼」 ●月刊誌『Voice』6月号(5月10日発売) 「西部邁氏の自裁死は独善か」 ●現在、『日本語は哲学する言語である』(仮) という本を執筆中です。 ●ブログ「小浜逸郎・ことばの闘い」 http://blog.goo.ne.jp/kohamaitsuo
福沢諭吉貨幣論1411-7-550-11/13メルマガブログ転送
(見出し)
「2014-11-02 07:26:47NEW !
テーマ:書評・オススメ本
竹森俊平「世界デフレは三度来る 上」 ① 」
(引用開始)
19世紀終わりから21世紀初頭にかけての、経済政策・経済論戦の変遷をたどる大著です。経済だけでなく、歴史物語としても十分に楽しめる壮大なストーリーです。近代資本主義の発生以降に生じた2回のデフレと1回のインフレ、そして未遂になるだろうと書いている3回目のデフレについて書かれています。
上下巻で1000ページ以上もの大著ですが、より面白いのは上巻です。
竹森俊
平氏は慶応大学の教授で、経済書は他に「経済論戦は甦る」などで有名です。
重要な箇所を引用しながら、自分の感じたことを書いていきます。
まずは、「序」です。
P.3
「スピーチのはじめにアメリカの学者はジョークを言い、日本の学者は謝罪を述べる」という言葉があるので、
ここでは謝罪から始める。
それは題名についてである。ここで「世界デフレ」というのは、
ヴィクトリア朝に発生した一回目のもの(1873-1936)、
「
大恐慌」として知られる二回目のもの(1929-1936)、
そして二十一世紀の初めに可能性をいわれ、結局、未遂に終わりそうな三回目のものである。
題名からすると、本書はデフレだけを扱うようだが、実際にはインフレも扱う。
すなわち、1970年代の世界的な「高インフレ」を、起承転結の「転」の部分に盛り込んで、
都合、四部構成にしている。こうすると、十九世紀後半から今日までの歴史を中断なく展望できるからである。
それは一言でいって、インフレとデフレのあいだの経済変動に焦点を当て、
財政、金融政策によってその経済変動を管理するという思想がどのように深まったのかを振り返り、
さらにその思想が日本においてどのように受け入れられたのかをテーマにした「歴史物語」ということになる。
(中略)
本書の題名について、もう一つ謝らなければならないのは、三回目が「きたる」というのは不正確だという点だ。
つまり、三回目は二十一世紀の初めに「くる」と喧伝されたが、実際には来たらず、このまま回避されそうである。
この本は2006年発刊なので、この時点での「世界デフレ」は回避されそうだったのは事実なのですが、
その後は
リーマンショック、そして
ギリシャに端を発するユーロショックにより、
本物の「三回目のデフレ」がまさに来るような気配があります。
その後、「第一部 金の十字架」では、
ヴィクトリア朝のイギリスは、
市民が紅茶をすすりつつ世界中の物産を注文できる一方で、工業力でアメリカやドイツに追いかけられ、
国内投資が減って海外への投資が増えてデフレになっていくことが書かれています。
今の日本と似ているような気がしてなりません。
第一部の見どころは、アメリカを舞台とする大統領選(ブライアン対マッキンリー)における
金本位制を巡る論争と、
日本を舞台とする
松方正義VS
福沢諭吉の経済論争、そして
国立銀行の設立と日本における
金本位制VS銀本位制論争です。
二つ目の見どころに焦点を当てて、
福沢諭吉の経済認識について書かれた文章を引用したいと思います。
P.74
(前略)
それで明治10年に
西南戦争が勃発すると、その戦費の調達のために、
明治政府は不換紙幣の大量増発に追い込まれた。
その時、財政を仕切っていたのは
大隈重信である。
このころから福沢は大隈と協力関係にあり、時には言論によって大隈を援護した。
たとえば、不換紙幣が大量に増発されて兌換がますます遠のくのは嘆かわしいことだとする世論に対して、
福沢は、通貨など不換紙幣で十分だという開き直った議論をして、大隈を援護する。
明治10年の『通貨論』がそれである。不換紙幣を正当化するというのは、当
時の欧米の経済学界においても革新的な立場だった。
福沢の通貨論は革新的だったと書かれていますが、著者の竹森氏は他の書籍で、
最初の不換紙幣発行者としてジョン=ローを挙げています。
この人物は、新大陸(
ニューオーリンズ)で
ミシシッピ計画の
事業を起こし、
バブルを発生させました。
ゲーテの戯曲「
ファウスト」にも似たようなエピソードがあります。
皇帝をそそのかして、悪魔
メフィスト=フェレスが不換紙幣をばらまいて景気を回復させたエピソードです。
竹森氏は経済理論だけでなく、こうした深い教養に裏打ちされた記述が魅力です。
P.79
「
人民の一家ならば、貯蓄や貸金を増やすのを目的とするのも結構なことだが、
政府の経済は、たとえ負債があったとしても貯蓄は持つべきではない。
なぜなら政府は本来、元手があるわけではなく、ただ毎年国民の財を集めて、
毎年これを消費するだけのものであるので、もしも政府の財政に余裕が生じるくらいならば、
始めからこれを取りたてずに国民の手元に残しておいたほうが、経済にとり都合がよいからである。
このように一家の世帯と一国の経済は違うもので、政府が目的とするべきことは、
ただ全国の人民がその知力のあるかぎり、腕力のあるかぎり、心身を働かせて、
天然の人為を加え、それによって人間の快楽が多くなるようなそういう仕組みを作り、
また自然にそういう仕組みがある場合にはそれを妨害しないことにある。
その生産活動から生じた利益が誰の手に落ちようとも、自国内にあるならばそれで満足するべきである。
政府は極貧にして借金が山のようにあっても、人民が豊かなら少しも心配することはない。
なぜならば、その借金はすなわち人民の借金なのだから、
払おうと思えばいつでも容易に払うことができるからである。」 この文章が明確に述べているように、人的資源をフルに活動させることこそが、
経済政策の目的であるべきだというのが福沢の主張である。財政が緊縮型か、
積極型かによって、その目的の達成に違いが出てくることも、福沢はもちろん認識していた。
それで、この文章のように赤字財政でも構わないという主張をするわけである。
それはもちろん福沢の目的意識が、「自分は、国中に
身体障害者や病人の他は、
手を空しくしている者が一人でも少ないことを望む」(前掲書)というところにあったからである。
なんと、世界でも最も早い時点で、
ケインズ型の財政政策を主張していたことになるのです。
福沢諭吉がここまで経済について深い洞察をしていたとは、この本を読むまで知りませんでした。
今の日本の経済学者や政治家は、100年以上前の
福沢諭吉の認識に負けているといわざるをえません。
(私のコメント)
財務省とその犬の
マスゴミは「国の借金一千兆円、国民一人あたり300万円」などという。
しかし、この論理はウソゴマカシなのだ。
彼らはずる賢いから個別の数字などは正しくして「ウソでないでしょ」と言い張るのだが、
論理としては間違いだし、誤解されることを狙っているのだ。
他のことでも
マスゴミの論調はそういう論調が多いから気をつけないといけない。
だが、明治10年すでに
福沢諭吉がそのウソを論破しているというのは驚きだ。
国家と各個人の家計とは全然別の性質のものだが、それをわざと混同させようとしている。
国家は貨幣の発行権と徴税権を持っているから個人のサラリーマンのふところとは全く違う。
また、彼らは借金はいけない、と言う道徳律をうまく悪用して、皆の考えを間違った結論に導こうとする。
マクロ的な道徳律は又違うのだ。
これを同じに考えて間違えた人に
新井白石が居る。
新井白石は
儒学者でとても偉い人だが、経済は
儒学とは別の理屈で動くことを知らなかった。
そのため、
元禄期に繁栄をもたらした萩原重秀を敵視し、死なせてしまった。
福沢諭吉はその他でも大変良いことを言っている非常に卓見を持った人だ。
江戸時代の教育を受けているから
儒学的素養をもっているが、
新井白石と違って
陽明学的なのかもしれない。
つまり、
プラグマティズム的な考え方をしていたのだろう、と思う。
福沢諭吉を改めて見なおした。
(私のコメント終)
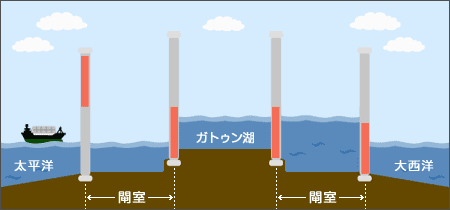


https://nam-students.blogspot.com/2020/04/blog-post_22.html
https://nam-students.blogspot.com/2020/04/blog-post_30.html@
https://love-and-theft-2014.blogspot.com/2021/05/blog-post_51.html
https://love-and-theft-2014.blogspot.com/2021/09/francis-wayland-wikipedia.html
小浜逸郎『まだMMT理論を知らない貧困大国日本 新しい「学問のすゝめ」』(2020)では
福沢諭吉の『通貨論』1878が重視されている。
《それ(通貨)が大切なのは、その質にあるのではなくて、働き(機能)にある。金銀と紙とは質が
異なっていても働きに何の違いもない。だから紙でも大丈夫であることには異論のさしはさむ余地はない》
《しかりしこうしてその大切なる由縁は、 品の質にあらずして その働きにあるものなり。 今、金銀と紙とその質は異なれども、 これを貨幣に用いて 働きに異なる所あらざれば、 紙を大丈夫なりと言いて 毫も異論あるべからず。》
通貨論1878
近年の福沢諭吉著作集では〈第6巻〉民間経済録・実業論に所収。
「甲申事変」の裏に日本がいると欧米に主張する清国に対抗するために「脱亜論」を書いた。つまり「亜細亜の旧体制からの脱却」がイコール「脱亜」であったと。
そして朝鮮国も日本同様、独立自尊の道を進むことを望んでいた、それで多くの留学生を受け入れたと。ふむ🤔
#歴史秘話ヒストリア #福沢諭吉
まだMMT理論を知らない貧困大国日本 新しい『学問のすゝめ』 Kindle版 2020/02/28
小浜逸郎 (著)
https://www.amazon.co.jp/dp/B0855L3763/
まだ M M Tを知らない貧困大国日本 ─ ─目次
はじめに
第 1章日本に迫りくる衰退の兆候
Ⅰ .貧困化する日本
Ⅱ .日本の科学技術が衰弱している
Ⅲ .国防の脆弱さ
Ⅳ .領土侵略に対しても無力
Ⅴ .情報戦における敗北
Ⅵ .少子高齢化のどこが問題か ?
Ⅶ .若者の生活不安定
第 2章なぜインテリは思考停止するのか
第 3章安倍政権はなぜ大失敗しているのか
第 4章よい学問と悪い学問の違い★
終章日本の凋落を克服するたった一つの方法
あとがき
ーーーちなみに以下にも福沢諭吉論がある(後述)
竹森俊平「世界デフレは三度来る 上」 ① 」
世界デフレは三度来る 上 (講談社BIZ) (日本語) 単行本 – 2006/4/21
5つ星のうち5.0 MMTと福沢諭吉、小浜逸郎さん渾身の良書です。
2020年3月4日に日本でレビュー済み
Amazonで購入
平成30年間の日本の衰退は緊縮財政とグローバリゼーションがもたらした政策的人災であることは明白です。
福沢諭吉は130年も前にMMT現代貨幣論の一歩手前まで自力で理論構築していた、と目の覚める論理構成です。
緊縮財政とグローバリゼーションで失われた国力を取り戻し、将来に希望を持てる日本国に再生させたい、そういう思いがふつふつと湧き上がり元気になりました。
この本や令和の政策ピボットメンバーの著書、講演、動画などで、緊縮財政脳から目を覚まして、正しい政治を選択しませんか。
16人のお客様がこれが役に立ったと考えています
以下の記事は★の後半部と内容が重なる