フーコーが生命政治について論じはじめたのは、一九六三年の『臨床医学の誕生』からである。フーコーの関心は、医療における倫理的問題の解決ではなく、そのような主題に顕著に出現してくる権力の働きを暴露することにあった。
精神:
つぎにベルクソンであるが、かれは、『創造的進化』(一九〇七年)において、生物の進化と、生物によって知覚される宇宙像の相互性について論じた。…植物には植物の、動物には動物の、そしてまた、本能には本能の、知性には知性の働きがある。どちらが優れているということはない。それゆえ、真理を捉えるものとしての知性のみが優位にあるということではないとベルクソンは主張する。
フェルディナン・ド・ソシュール(一八五七~一九一三)は、歴史言語学派を改革しようとした少壮文法学派のひとりであったが、やがてその関心は、ラングの歴史をも説明することのできるような言語(フランス語では「ランガージュ」)の本質へと向かっていった。
情報:
デリダは、サールとの論争において、オースティンが述べた、言葉の真の行為と演劇などでの「ふり」の行為の区別を問題にした(『有限責任会社』)。
暴力:
ドゥルーズとガタリは、「無意識しか存在しない」、「無意識は何も表象しない」、「われわれが意識だと思い、さらに主体だと思う経験は、その無意識の単なる効果(生産物)にすぎない」と主張するのである。
船木亨 『現代思想史入門』 -
http://unnamable.hateblo.jp/entry/20160418/1460909462
現代思想史キーワード年表
はじめに
今日を読み解く思想/近代の行きづまり/ツリーからリゾームヘ/現代思想の諸地層
序章 現代とは何か
1 近代の終わり
ソーカル事件/思想の難解さ/宴のあと
2 現代のはじまり
時代としての〈いま〉/一九世紀なかばの生活/歴史のなかに入っていく哲学/シェリー夫人の「フランケンシュタイン」/われわれのなかの怪物
第1章 生命――進化論から生命政治まで
1 進化論
生物学と自然科学/ドリーシュの「生気論」/ダーウィンの「進化論」/哲学から科学が独立する/ヘッケルの「系統樹」
2 優生学
優生思想/ゴールトンの「優生学」/タブーとなった優生学/出生前診断
3 公民権運動と生命倫理
アメリカ公民権運動/フェミニズム/生命倫理/生命倫理のその後
4 生命政治
医療のアンチ・ヒューマニズム/フーコーの「ビオ-ポリティーク」/人口政策/大病院の起源/臨床医学の病気観/政策と産業のための医療/病人の側から見た病院/予防医学/生と統計/死と生/病気における苦痛/フーコーの「狂気の歴史」/健康な精神なるもの/排除と治療
5 トリアージ社会
知と権力の結合/ベンタムの「パノプティコン」/アガンベンの「剥きだしの生」/生命の数/統計的判断の不条理/道徳の終焉/国家と健康/神なき文化的妄信
第2章 精神――宇宙における人間
1 進化論の哲学
スペンサーの「文明進化論」/ジェイムズの「プラグマティズム」/ベルクソンの「創造的進化」/ホワイトヘッドの「有機的哲学」/ビッグバン仮説/宇宙進化論/宇宙と神/歴史は進化の普遍的登記簿に
2 西欧の危機
シュペングラーの「西洋の没落」/フッサールの「西欧的なもの」/新たな哲学へ
3 生の哲学
存在と生/ディルタイの「解釈学」/ギュイヨーの「生の強度」/ニーチェの「ニヒリズム」/神の死
4 人間学
シェーラーの「宇宙における人間の地位」/文化人類学/レヴィ=ストロースの「構造人類学」/野生の思考/哲学的人間学
5 実存主義とは何だったのか
有神論と無神論/サルトルの「実存主義」/ハイデガーの「アンチ・ヒューマニズム」/存在論的差異/死に向かう存在/存在と言葉/存在か無か/〈わたし〉と〈もの〉/メルロ=ポンティの「両義性の哲学」/進化と宗教
第3章 歴史――構造主義史観へ
1 歴史の歴史
古代・中世・近代/歴史の概念/ヘーゲルの「歴史哲学」/ポパーの「歴史主義の貧困」/宇宙の歴史と歴史学/ナチュラルヒストリー/存在したもの/普遍的登記簿/歴史とポストモダン
2 現代哲学
哲学の終焉のはじまり/哲学の四つの道/哲学という思想/生か意識か/現象学/フッサールの「現象学的反省」/時間性/ベルクソンの「純粋持続」/ドゥルーズの「差異の哲学」/現代哲学の終焉
3 論理実証主義
心理学と心霊学/フレーゲの「意味と意義」/ウィトゲンシュタインの「語り得ないもの」/英米系哲学
4 構造主義
歴史言語学派/ソシュールの「差異の体系」/構造主義の出発/構造主義の三つの課題/ロラン・バルトの「エクリチュール」/構造主義的批評/フーコーの「エピステーメー」/構造主義的歴史/フーコー学
5 象徴から言語へ
メルロ=ポンティの「生の歴史」/象徴と記号/フーコーの「人間の終焉」
第4章 情報――ポストモダンと人間のゆくえ
1 ポストモダニズム
建築のポストモダン/メルロ=ポンティの「スタイル」/ベンヤミンの「アウラ」/芸術のポストモダン/文学のポストモダン/近代文学/映画のポストモダン
2 ポストモダン思想
リオタールの「ポストモダンの条件」/大きな物語/思想のポストモダン/ポスト構造主義/デリダの「脱構築」/ロゴス中心主義/デリダ=サール論争/前衛とポストモダニスト/状況なるもの/ポストモダン思想のその後
3 情報化社会論
ダニエル・ベルの「イデオロギーの終焉」/アルチュセールの「国家イデオロギー装置」/トフラーの「未来学」/ボードリヤールの「シミュラークル」/道徳と芸術のゆくえ/価値の相対化/マンフォードの「ポスト歴史的人間」
4 世界と人間とメディア
ルネサンス/世界の発見/人間の発見/時計の発明/大衆の出現とマスメディア/大衆社会論/マクルーハンの「メディアはメッセージである」/文明進歩の地理空間/帝国とグローバリゼーション/管理社会論
5 マルクス主義と進歩の終わり
文明の終わり/マルクスの「共産主義革命」/資本主義社会/共産主義社会/歴史の過剰と欠如/人間の脱人間化と世界の脱中心化/サルトルの「自由の刑」/哲学のゆくえ
第5章 暴力――マルクス主義から普遍的機会主義へ
1 革命の無意識
五月革命/ライヒの「性革命」/精神分析/フロイトの「無意識」/エディプス・コンプレックス/精神分析のその後/ラカンの「鏡像段階」/構造化された無意識/どのような意味で構造主義か
2 フランクフルト学派
ベンヤミンの「暴力論」/神的暴力/亡命ユダヤ人思想家たち/アドルノとホルクハイマーの「啓蒙の弁証法」/フロムの「自由からの逃走」/マルクーゼの「人間の解放」/資本主義からの逃走
3 アンチ・オイディプス
ドゥルーズとガタリの「欲望する機会」/狂人たち/無意識は表象しない/国家/野生と野蛮/資本主義社会/メルロ=ポンティの「現象的身体」/マルクスの「非有機的肉体」/フロイトの「死の衝動」/アルトーの「器官なき身体」/ドゥルーズとガタリの「千のプラトー」/自由から逃走へ
4 ポスト・ヒューマニズム
現代フランス思想/ニーチェの「神の影」/機械と人間/カフカの「エクリチュール機械」/自然と文化の二元論/機械としての人間/カンギレムの「生命と人間の連続史観」/機械一元論哲学/ドゥルーズとガタリの「普遍的機会主義」
5 機械と人間のハイブリッド
ハラウェイの「サイボーグ宣言」/女性/人間はみな畸形である/ハラウェイの「有機的身体のアナロジー」/機械と生物のネットワーク/死の衝動と生の強度/生の受動性
おわりに
今日の思考/哲学の栄枯盛衰/非哲学の出現/現代哲学から現代思想へ/現代思想の諸断層
あとがき
事項索引
人名・書名索引
現代思想史キ ーワ ード年表:
1858 進化論
1876 ベル電話機発明
1886 ガソリン自動車
1905 特殊相対性理論
1927 ビッグバン理論
1942 コンピュータの発明
1953 DNA 二重螺旋
1996 インターネット
アポロ11号月面着陸
1978 初の体外受精児誕生
1986 チェルノブイリ原発事故
2006 iPS細胞
1850 1900 1950 2000
_________________________________________________
生命:
進化論 骨相学 遺伝学 DNA クローン技術
系統樹 新ラマルク説 生気論
社会ダーウィニズム 優生学 複雜系オートボイエーシス
ファシズム 民族純化 民族浄化
エコロジー ガイア仮説 ディープエコロジー
帝国主義 国家主義 公民権運動 生命倫理 生命政治論
フェミニズム ウーマン・リブ 第三波フェミニズム
_________________________________________________
精神:
相対性原理 ビッグバン説 宇宙進化論
文明進化論 創造的進化論 有機的哲学 ネオダーウィニズム
プラグマティズム
人類学 文化人類学 構造人類学 身体論
生の哲学 ニーチェ思想 哲学的人間学 実存主義
解釈学 西洋の没落 存在論 アンチ・ヒューマニズム
_________________________________________________
歴史:
新カント派 現象学 論理実証主義 分析哲学
ベルクソニスム 日常言話学派 フランス現象学 差異の哲学
世界史学 アナール派
歴史言語学派 青年文法学派 構造言語学 構造人類学 記号学 構造主義 フーコー学
民族学 心理学 精神世界
精神分析 構造主義的マルクス主義
_________________________________________________
情報:
モダニズム建築 ポストモダン建築
印象派 現代芸術 前衛芸術 アンチロマン 脱構築 イェール学派
カウンターカルチャー ポストモダン思想
管理社会 大衆社会論 情報化社会論 ポスト構造主義 文明の衝突
文明批評 メディア論 未来学 文化批評
マルクス主義 大学紛争 新左翼
__________________________________________________
暴力:
精神分析 性革命 五月革命
ラカン派 性科学
フランクフルト学派 アンチ・オイディプス
現象的身体 器官なき身体 ポスト・ヒューマニズム
人間工学 サイバネティックス サイボーギズム
フランス認識論 普遍的機械主義
__________________________________________________
1861 アメリカ南北戦争
1868 明治維新
1889 大日本帝国憲法
1904 日露戦争
1914 第一次大戦
1917 ソ連成立
1929 世界恐慌
1939 第二次世界大戦
1968 五月革命
1989 ベルリンの壁崩壊
2001 9.11テロ
2011 東日本大震災













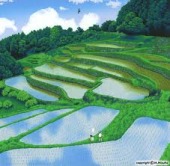


ネチャーエフ「カテキズム」が読める本は? - 文学 | 【OKWAVE】
http://okwave.jp/qa/q7397770.html
『革命家の教理問答集』あるいは『革命家の教理問答書』のタイトルでバクーニン著作集5(白水社ほか)で邦訳は読めるようです。
___
38.社民党批判6.(アナーキズムとは何か?) ( 政党、団体 ) - 安岡明夫HP(yasuoka.akio@gmail.com) - Yahoo!ブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/oyosyoka803/15341856.html?__ysp=44OQ44Kv44O844OL44OzIOS6lOS6uue1hA%3D%3D「革命家は死すべく運命づけられた人間である。彼には・・感情も愛着も・・ない。・・すべての法律、・・道徳とのあらゆるきずなを絶っている。彼にとってこの世界は容赦なき敵であり、もし彼がその中で生き続けるならば、それはこの世界をより確実に破壊せんがためにほかならない」(同p.401)。
「人民の堕落は・・権利・・」「私は人民による盗奪行為を擁護する・・」(同p.355)。
「盗賊団を人民革命の武器として用い」るべきと(同p.356)。